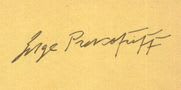フランク:弦楽四重奏曲
フランク:弦楽四重奏曲
○(PHILIPS)
形式に囚われた長ったらしい曲ではあるのだが、転調移調の新鮮さ、息の長い旋律の美しさには心奪われざるを得ない。4楽章制だが終楽章には繰り返し1楽章の主題が現れ統一感を保っている(他楽章の主題も回想されるが)。アンサンブルの面白さというものはなく、旋律と伴奏、という構造はいささかもぶれず、ろうろうとうたうファースト以外が伴奏音形で掛け合う、というなんとも・・・なところは否定できない。レーヴェングートは穴を一生懸命探しながら聴いても殆ど無い。さすがは昔から名演奏とされてきた録音である。やや線の細いからこそ美しい音のファーストに対して飽きもせず(失礼)ずっとしっかり支えていく残り三本の健闘にも○。
ドビュッシー:弦楽四重奏曲
○(DG)
旧録。LP独特の演奏。面白い(が飽きるかも)。緩急極端でディジタルなテンポ変化、音量のコントラストの激しさと常套句で言ってもなかなか伝わらないたぐいの演奏で、しいていえば「やらかしてやれ」という意気があふれつつも、諸所でその意気に演奏技術が追い付かず(とくにファースト)、緊急避難的に施されたルバートや最弱音での異様な低速・ノンヴィブ(1楽章)最強音で乱暴に響くピチカート(2楽章)などが結果として独特の聴感をあたえている。2楽章あたりはじつに面白い。4楽章は盛りだくさんなのでいろいろ楽しめる。唯、3楽章はつまらない。・・・聞けばわかるがけっこうぶっとんでいて、この団体のイメージからすると意外だ。音色に特色の少ない奏者の集団だから逆にまとまりはよく、だがその中でもとくにファーストがそれでもいろいろと特殊な音色を出そうとして奏法にさまざまな細かい変化をつけており、気持ちとしては非常にわかる(他の楽器はそつなくうまく弾き抜けている)。終楽章のクライマックスなどいにしえのフランスのカルテット張りの艶めかしいフレージングが頻出してはっとさせる。でもファーストは弱い。最後の駆け上がりがぐちゃっとなって結局ヘタッピだ(こんなんでDGはOKしたのか?)。もっともこれも気持ちは良くわかるが・・・。総じて○としておきます。私は3回目で飽きたが、1、2回目はワクワクした。,
○(CND)LP
モノラル末期のフランス録音。折り目正しくきちんとした演奏ぶりは寧ろ「なんじゃこりゃ」と思わせる雰囲気を漂わせた遅さだが、ドイツ的というか、引き締まった演奏方法が慣れてくると独特のタテノリになり心地よくなってくる。確かに独特の演奏で、当時としても特異だったからこそ評判になったのだろう。正確さを狙ってるのではなく、高音などハーモニーが揃わなかったりするが、カペー師匠に教わった若干引き芸の部分を伸張させ、緊張感をもって構成的な演奏を展開する、中間楽章から徐々に、そして終楽章ではまあまあの感興を催される。VOX録音があるのでこれに拘る必要はなく、モノラル末期特有の重厚な音があるとはいえ状態のいいものは高い可能性があるので(私はひさびさディスクユニオンに行って、あの大量消費中古店でもそれなりの値段がついていたものを、半額セールで買ったのだが、それでも裏表音飛びまくりの磨耗ディスクだった・・・半額じゃなければ何か文句言ってるところだ)。海外じゃ安くて原価2000円くらいか。
△(VOX)LP
新規メンバーによるステレオ録音。非常に厳しい演奏。遊びのない独特の解釈表現は特筆ものだ。録音も硬質で金属的な感じがありキンキンと聞きにくい箇所もある。そしてこのファーストヴァイオリンのあつかましさ!ぎりぎり弦の軋む音が聞こえるじつに耳障りな音。演奏レベルは初代にくらべ格段に上がったかもしれないが、この終始力んだような音色は耐えられないレベルに達している。ドビュッシーがこれほどあけっぴろげに弾かれたのを始めて聴いた。ニュアンスもへったくれもない、ただ3楽章にちょっと聞ける箇所がある程度。勉強用の見本としては存在価値はあるかも。フランセの四重奏では柔らかく軽妙なところを見せているというのに、なぜこういう力みかたになってしまったのか、不思議だ。,
ラヴェル:弦楽四重奏曲
○(DG)LP
独特の演奏。面白さで言えばカップリングのドビュッシーに軍配があがるが、技術面もふくめ完成度はこちらのほうが高い。終楽章の5拍子が最初は最後に1拍「ウン」と思い直すような拍が入って6拍子に聞こえる(3拍子が2拍子になっているバーンスタインの「ライン」冒頭みたいな感じだ)のがちょっと面白かった。無論解釈であり、先々のつじつまはあっているし、途中5拍子に戻るときにはしっかり5拍子で聞こえるからいいのだ。繰り返しになるが線が細く力感がない、小手先は巧いが音色が単純というハンディ?をかかえた団体なので、工夫をすることで独自性を見せているところがある。4本が重なったときの音の純度が高いことも付け加えておこう。4本が音色的にも技術的にも平準化されているがゆえの長所だ。この団体の短所でもあり長所でもある。弱音でのノンヴィブ表現にも傾聴。この演奏は全楽章解釈に手を抜かず起伏があって聞かせる力がある。但し・・・私は2回目で飽きた。ので、○はひとつにとどめておきます。でもぜひいい音でCD復刻してもらいたいものだ。,
○(CND)LP
モノラル末期のフランス録音。ドビュッシーよりラヴェルのほうがいいという特異な団体である。そくっと入り込むような1楽章から、終始穏やかできちっとした(一種お勉強ふうの)演奏が繰り広げられるが、技術的に完璧ではないものの、演奏的に隙がない。まあまあ。VOX録音があるのでこれに拘る必要はなく、モノラル末期特有の重厚な音があるとはいえ状態のいいものは高い可能性があるので(私はひさびさディスクユニオンに行って、あの大量消費中古店でもそれなりの値段がついていたものを、半額セールで買ったのだが、それでも裏表音飛びまくりの磨耗ディスクだった・・・半額じゃなければ何か文句言ってるところだ)。
(VOX)LP
ステレオ録音。ドビュッシーよりは柔らかくニュアンスのある演奏。ハーモニーの変化や個々のモチーフの表現は実によく計算されて明確であり、「ここで内声部に既に次のモチーフが顕れてたのか!」みたいな発見がある。ただ、やや危ないというか、変なところがある。このストバイ(ファーストヴァイオリン)、刻みが微妙に拍から遅れるのはどういうわけだろう?2楽章の中間部前・下降音形の三連符の刻みや4楽章の一部、「弾き過ぎて」リズムが後ろにずれていくように聞こえる。他の楽器がちゃんと弾いているので破綻しないで済むのだろうが、ちゃんと刻めないのか?と疑ってしまう。また、2楽章で中間部の最後・副主題の再現前に印象的なハーモニクスを含む跳躍があるが・・・弾けてない!ぐぎっ、というような力んだ音がするだけである。決して技術的に劣っているのではなく、こういう弓圧を思い切りかける奏法なものだから軽くトリッキーな場面で音の破綻をきたすことがあるのだろう。技術うんぬんで言えば1楽章などの分散和音のピチカートはハープと聴き枉ごうばかりの美しさでひびいておりびっくりする。こういうことが出来るのだから技術が無いわけではなかろう。まあ、3楽章の聴きどころとなっている美しいアルペジオがちっとも響いてこないなど、ちぐはぐな技術ではあるのだが。そのアルペジオに載って入るチェロ(だったかな?)が美しい。楽団によっては低音楽器による主題提示が今一つ聞こえてこないこともあるから新鮮だ。これもストバイのアルペジオが下手だから際立ってきたのだが・・・あ、下手って言っちゃった。総じて無印。,
フォーレ:弦楽四重奏曲
○(VOX)
正直この団体がなぜこんなにもてはやされるのかわからない(マニアに)。フランスのパレナンあたりとだいたい活動は同時期か少し前のような感じで(メンバーチェンジあり)戦後モノラルからステレオ期長く活動した団体であり、スタイルも変動はあるがパレナン同様比較的現代的である。したがって古物マニアに受ける要素というのもあんまりない気がする。この演奏はフォーレの淡い色彩の上で展開されるロマン性、晩年作ならではの結構現代的な音線にハーモニー変化をどぎつく強調することなく、どちらかといえばさらっとした肌触りで仕上げている。しかし二楽章などこの慟哭に近い魅力的な旋律を聞き流させるのはちょっと惜しい。逆に一楽章のような晦渋な楽想にかんしては上手く流し美感を損なわないようにしている。全般あまり特徴的なものはなく、フォーレの中でもドビュッシーら後発組の先鋭的作品群の「あと」に作られた特異な作品であるという点を余りに「強調し無さ過ぎる」がゆえ、もったいない感じ。いずれ精度面で○ではある。音色への好みというところもあるんだろうな。フランス派ならではの音というのは確かにある。
ルーセル:弦楽四重奏曲
○(DG)LP
旧盤という呼び方でよろしいんでしょうか。モノラルだがとても整理されて聞きやすい。あ、ルーセルってフランスだったんだ、という改めての確認ができる(ミュンシュ的力技の暑苦しさを排し不協和音の繊細な美しさを忠実に浮き彫りにしたブーレーズの3番シンフォニーの演奏なんかでも感じるところだ)。それ以前に音楽に入りやすい。構造が入り組み重なりすぎて(ハーモニーが重過ぎるということもある)旋律線が埋もれがちなルーセル後期の作品は、余り解釈しようとせずに演奏すると、各奏者は面白いが(構造が売りな作曲家なだけに旋律じゃなくてもちゃんと面白く弾けるようにできているのだ)聞く側はわけがわからない晦渋さや耳障りの悪さを感じるだけで、フランス派の単純に美しい音楽を期待する向きはうっときてしまうことが多い。フルートと弦というような組み合わせで音色で描き分けがなされているぶんにはわかりやすいのだが、弦3本、弦4本となると慣れていないと音楽として分析できない(分析しないとわかりにくいのは曲的にどうなのかとも思うが)。レーヴェングートの巧いところは決して奇をてらわず勢い任せにもせず、注意深くバランスを保ちオーソドックスに弾いているところで、音色にも奏法にも特に面白いところはないが、わかりやすい。2楽章の晦渋さはどうしてもぬぐえないが理知的に配置された旋律の美しさがさりげなくもくっきり浮き立たせられているために後半楽章での変容再現が聞く者に鮮やかに印象付けられる。後期ルーセルは構造を無視して弾くことはできない。構造の上に実はちゃんと旋律がのっかっているということを常に意識してやらないと、構造のみを聞かせるマニアライクな曲になってしまう。ルーセルのカルテットが売れないのはひとえにそこの難しさがあるが、この曲を得意としていた数少ない団体であるレーヴェングートの旧盤、学ぶべき部分はたくさんある。でもオーソドックスすぎるので○。ミュンシュもそうだけどルーセルは元々ぎっしり詰め込まれた曲をかくので暑苦しく表現しようとすると濃密すぎてうっときてしまうんですよね。。
型式重視。こんなに晦渋でも新古典主義の作曲家と位置づけられるのはそのせい。
○(VOX)CD
二代目メンバー。この曲は案外この楽団にあっているようだ。晩年のルーセルの行き着いた晦渋な世界、余りに渋すぎるその楽想、やたらと厚ぼったく身の詰まった響き(それは四本の楽器によって演奏されるには余りに重過ぎる)、下手に演奏するとほんとに聴いてられないような重くてわけのわからない曲に聞こえてしまうが、この演奏だと多少軽さがあるというか、響きが整理されていて聴き易い。とくに晦渋な緩徐楽章(2楽章)の本当の美しさ・・・旋律線の仄かに甘やかな揺らぎ、線的に絡み合う音響の妙味・・・が出ていて凄くいい。硬質で冷たい抒情が持ち味のルーセル円熟期の緩徐楽章、この演奏だといくぶん温もりすら感じられるのが特筆もの。ルーセルの室内楽はアンサンブルする側にしてみれば非常にかっちり書かれているので面白いが、聴く側からすると主題がわかりにくいままにだらだらと引きずっていくように聞こえるところがある。この曲だと終楽章がそうだ。弦楽三重奏曲終楽章の美しき軽さに通じるパッセージが楽章後半に徐に出てきて非常に魅力的なのだが、それで解決大団円にすればいいものを、ルーセルは再び音楽を構造の中に埋め立てていってしまう。それはこの楽団をもってしてもいささか長ったらしく感じさせてしまう。曲のせいだから仕方あるまい。晩年のルーセルはわかりやすさや素直な感情の吐露を捨ててひたすら構築的で複雑な音楽を求めた。それは作風は違うがレーガーなどと通じる感覚だ。ドイツ・オーストリアで一定の人気があったのはわかる気がする。フランスでは独特の位置にいる作曲家だった。○。, (2005以前)
VOXBOXでCD化されていた新録だが現在はNMLなどweb配信で容易に聴ける。しょうじき音程感は甘いところもあるが曲の主軸を要領よく浮き彫りにしてゆき、美しい旋律と微妙な転調の、リズムよく動くさまが簡潔あきらかで聴き易い。とにかく響きが重くならないので、ドビュッシーから連なるフランス派の弦四として同曲を認識し直すことが可能。透明感はないが二楽章の感傷には心惹かれるものがある。○。 (2011/1/31)
ロジェ・デュカス:弦楽四重奏曲第2番
○(MANDALA)1954/2/27パリ・CD
楽団に敬意を表して○にしておくが、駄作。絶筆であり作曲後間もない録音であり資料的価値はある盤にせよ音楽はまとまりがなくひたすらだらだら長い。フランクよりは新しいだけあって新旧様式混淆の多様な聞かせかたをしてくるが、明らかに「アメリカ」を意識したような前時代的な表現に、フォーレの室内楽の作法を重ね合わせ、国民楽派の影響をうけるもドビュッシーにまで踏み出せないフランス派SQとしか言いようのない1楽章からしてうんざり。楽章が進むにつれフランク的マンネリズムを打破しようというような暴力的なリズムや不協和音がおりまざるも、ルーセルの明快さもオネゲルの思索性もない、思い付くままの老いた繰り言。よくわからない構成以外、新味がない。3楽章はかなりつらい。この盤で17分、アダージォだ。4楽章制を守るはいいが、全部で50分となると、時間配分は完璧だが(この盤で14、7、17、11分くらい)、全部が長すぎる。4楽章で型にはめたようにわかりやすい五音音階を繰り返すにいたり、ウォルトン10代の佳作ピアノ四重奏曲か!と80代の作曲家に突っ込みたくなった。むろんもっと捻った構成に組み込んだものではあるが。フランクやショーソンの室内楽好きならいけるのかな。あと、私がデュカそしてフローランが余り得意ではないことを付け加えておく。レーヴェングートQの新しい録音を早く復刻してくださいdoremi。かれらはベトも得意だったけど、十字軍だったのだから。
ミヨー:弦楽四重奏曲第3番
○デュモン=スルー(msp)(vox)1960年代・LP
レーヴェングートらのミヨーはフランス近代の一連のvox録音ではこれだけ、あとはライヴ録音があるのみである(恐らく既記のものだけ)。しかも作風を一変し晦渋な曲想で通した異色作という、溌剌とした技巧的表現を持ち味とした後期レーヴェングートQにはどうにも合わないように感じるのだが、聴いてみれば意外とロマンティックというか、旋律の流れを素直になぞる聴きやすい演奏となっている。シェーンベルクの影響を受けた最初のSQであり歌唱が導入されるのもそのためと思われるが、無調には踏み込んでいない。寧ろ後期サティ的な単純さが感じられる。比較対象が少ないので評は難しいが、透明感ある演奏が重い響きを灰汁抜きして美しい暗さに昇華している、とだけ言っておこう。○。
ミヨー:弦楽四重奏曲第7番
○(FRENCH BROADCASTING PROGRAM他)LIVE
レーヴェングートSQのミヨー録音は2,3あるらしいのだが手元にはこの英語放送音源しかない。放送用ライヴではなく公衆ライヴ録音の放送のようである。ちなみにこの音源、アナウンスと本編がそのまま収録されジャケットも内容も一切記載されないのだが、昔「夏の牧歌」などエントリした盤については本編にも演奏家について触れた部分がなく且つ恐らく通常のスタジオ録音の切り貼りだった。この二枚組はライヴとスタジオが半々のようで、全貌のよくわからない音源ではある。
演奏のほうは、ミヨーを「ちゃんとした同時代演奏家たち」がやればこうなるのだ、というかなり感情を揺さぶられるものになっている。暖かい音色が違う、フレージングの柔らかさ、優しいヴィブラート、技巧と音楽性の調和、即興的なアンサンブルのスリル、どれをとってもミヨーを新しいスタジオ録音(と現代の生演奏)でしか聴いていない者にとっては目から鱗の「ほんもの」である。しかも曲がミヨーの中ではやや抽象度の高く旋律主義ではない、晦渋さもあるアンサンブル重視のものだけに(それでもまあ小交響曲にかなり近似しているのだが)、こういうふうにやればスカスカの音響に惑わされず緊密で適度な美観をもった演奏になるのか、と納得させる。もっとも技術的に難のある箇所もあるし、ミヨー特有の超高音での音程の悪さはプロらしくないが、しかし、盛大な拍手もさもありなん。モノラルで環境雑音もあり、曲も短く比較対象になる演奏もないのでひとまず○にとどめておく。
フェルー:弦楽四重奏曲ハ調
○(vox)1960年代・LP
ミヨーとのカップリング。六人組と同世代でフローランの弟子筋の夭折の作曲家兼批評家である。作風は親しかったプーランクよりイベールに似ており、やや保守性をしめし、構造への執心は師匠に近い。ミヨーを思わせる晦渋な響きも聴かれるが、そういった点からも新古典主義というより折衷的作曲家であるように感じる。室内楽に強い作曲家という面があり、フォーレ的な暗い魅力をもつこの晩年作(とはいえ事故死のため死の予感どうこうというのはないが)も非常に鋭敏な感覚でマニアックに作り込んだアンサンブルが印象に残る。ピチカートを織り混ぜた清新な響きの競演はイベールのそれよりも手が込んでいる。リリシズムをたたえたレーヴェングートQの演奏ぶりは、とても上手くまとめているといったふう。技巧的に難しいところも難なく切り抜けている。○。
イベール:弦楽四重奏曲
○(EMI)1946/9・CD
グラモフォンに録れたドビュッシーのばらけた演奏ぶりが信じられない出来である。個性という点ではどうかわからないが、統一された美しい音色~アマティの銘器で統一された~による極めて緊密なアンサンブルには括目させられる。とにかくこの速さは尋常ではないし、溌剌とした運動性もこの曲にはふさわしい。フランスの団体の草分けのひとつとしてメンバーチェンジを重ねながらも70年代までじつに40年以上活躍した団体であり、録音も数多いものの復刻が進んでおらず比較的新しいLPでもしばしば高値がつけられている。カペーやカルヴェ、クレットリと並び称されるほどの古の有名団体でありながらメンバーはじつに若く、主宰のファーストヴァイオリンなどは大正元年生まれという異例の若さである(10代で組織したのだ)。まずは明瞭で技巧的なアンサンブルの妙味、そして赤銅色の美音(この曲では一番地味な2楽章でとくに味わえる)。それらを楽しむにはふさわしい演奏だ。1、3楽章は「うわーこんなの弾けない」と思わせるようなエスプリと煌きを放っており、さすがだと感銘を受けさせる。2楽章は元々の曲がややわかりにくい構成のため今ひとつ魅力が浮き立ってこないが、2回繰り返される長大な名旋律は控えめながらも味わい深く響いている。3楽章はピチカートだけの楽章ながらもさすがアマティ、音色に艶があり、たんなるチャイ4の3楽章に落ちないカルテットでなければ表現できないような輝きを瞬発的に放っている。鋭さはないが速さの中に和声的なバランスが巧くとられておりこの比較的古い録音でも十分にイベールのサロン風ハーモニーの妙を楽しめる。敢えて速く奏することで4楽章の序奏としての役割を果たさせることにも成功している。4楽章はベートーヴェンを得意としたこの団体らしいかっちりしたところを見せる。アンサンブル力のみせどころだ。総じてまとまりすぎて小粒にも感じられるが、イベールの演奏としては一位に置けるくらいのものになっていて素晴らしい。個性に拘る私は○ひとつに留めておくが、◎になってもおかしくない内容だと思う。グラモフォンのフランスものの録音と比べてのこの違いはなんだろう。数年のうちにファーストが狂ったとしか言いようがないが、狂ったと言っても個性的とみなす私はグラモフォンの芸風のほうが好きだと付け加えておく。戦後の録音であるせいか古くてもしっかり楽しめる録音レベルには達している。,
フランセ:弦楽四重奏曲
◎作曲家指揮(ACHARLIN)
ちょっとピッチが高めだが録音のせいか。この団体の盤はどのセコハン屋でもすっかり貴重盤扱いだが、それほど人気があるのだろうか。フランクやルーセルの盤などとても手が出ない高額にはねあがっている(ちなみにこの団体CDは1、2枚くらいしか出ていないはず)。フランスの団体らしい謡い廻しや遊びがない実直な演奏を行う。弱い弓圧で繊細な音色を引出しているところは個人的に非常に好きだが、全員、線が細すぎると思うのは私だけだろうか。そのほうがアンサンブルとしてまとまりやすいから技術面に注視する向きに受けるのだろうか。表面的であからさまな表情を見せないからといって叙情的な面に欠けているわけでもなく、寧ろ「総体の音色」で語れる珍しいカルテットである。この曲はフランセの水準からいってけして良い出来ではない。でも、この演奏はぐっと引き込まれるものがあった。正攻法であっさりした解釈なのに、柔らかく細い音色の美妙な綾を利用して、とても爽やかな叙情味溢れる演奏を繰りひろげている。なかなかやるのだ。遂にはフランセの骨頂である懐かしい時代のパリをまさに思わせるエスプリを演じあげている。あなどれない。4本が技術的に同格のため内声部が生きて聞こえるせいもあろう。ファーストはプロとしては派手さが無く、技術的にけして高度なわけではない。あからさまな感情を音にできないのではなかとすら思わせる。でもそのために逆にレベルの揃った見事なアンサンブルが出来ているのではないか。ドビュッシーなどを聞いても内声が大きく響き構築的な響きを造り上げていて秀逸。ああ、フランセの曲でしたね。フランセの同曲の演奏としては、間違いなく◎。こういう中身を適切に抉った演奏で触れる人が増えれば、この佳曲も有名になるかもしれない。
(後補)この演奏、改めて聞くとそれほどには細くて下手な演奏ではありませんでした(泣)ドビュッシーやラヴェルはそうなんですけどね。。,
フランセ:羊飼いの時間
◎作曲家(P)他(A.Charlin)
うん、これは楽しい。猫の鳴き声から始まってパリ夜のランチキ騒ぎのような世俗的な音楽、メロディも和声も懐かしく馴染みよくレーヴェングートのねっとり、でも小洒落たアンサンブルに対してフランセ自身のピアニズムがしっかり芯を通す、やはりこの人の芸風は自分の作品に最もあっているんだなあと思う。フランセのあまたある作品の中でもかなり上位に置けます。◎。
フランセ:三つのエピグラム
○他(A.Charlin)LP
男声・女声と小規模室内楽という編成や5分程度の演奏時間からしてもミヨーのミニチュア歌劇を思わせる音楽で、いつもの子供っぽい心地も旋律にはあるけれども、実はけっこう声楽を伴う曲も書いている人らしく、サティのソクラートに近い極めて削ぎ落とされた音楽はしんと響くものである。かなり真摯でアルカイックな雰囲気をかもし、演奏陣の精緻で注意深い配慮も効いている。言葉と音楽の不可分な感じはフランスの近代作曲家の多聞に漏れない。○。
ドルリュー:弦楽四重奏曲第1番
○(FRENCH BROADCASTING PROGRAM)LP
映画音楽作曲家として名をはせたドルリューは表題なしの弦楽四重奏曲をニ曲残している。パガニーニ四重奏団のレパートリーにもなっておりなかなかしっかりしたクラシカルな作品だ。この曲は師ミヨーの書法を踏襲しながらも独自の甘やかな旋律や他の、とくにルーセルやイベールの弦楽四重奏曲の気分を彷彿とさせる響きや構成で多彩なところをみせている。その緊密さは楽団の技量そのまま反映して素晴らしい。○。
プロコフィエフ:弦楽四重奏曲第2番
○(DG)LP
よく見る盤だが昨今の初期盤ブームとおフランスブームで高値安定の中古市場。DG盤の質や録音特性の好き好きはおいておいて、演奏はなかなか大人である。フランス的な甘い軽やかな響きと不安定な細い描線がかもすのはかつて作曲家が憧れた往年のフランス派、たとえばミヨーのプロヴァンスふう室内楽のような雰囲気であり、清澄さと繊細さをもたらして民族的な凡演と一線を画している。現代的な団体だなあと思わせるのは2楽章冒頭からの教会的な音楽の部分で、まるでショスタコ晩年の諦念のような悲痛なかなしみが滲み出ている。ユーモア溢れる終楽章でさえ、随所に深淵をのぞかせている。この演奏は素直に民謡室内楽として聴けない何か踏み込んだものをかんじさせる。技術的にはそれほどでもなかろうが、曲理解のために聴く価値はあります。
※2012-04-04 15:30:27