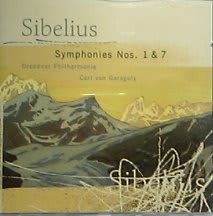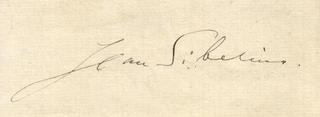バルビローリ指揮ハレ管弦楽団(DA:CD-R)1969live
個人的にバルビのシベリウスやRVWのシンフォニーは音のキレが甘く、テンポがもったりした感じがして余り好きではない。もちろん時期や作品、また楽章によっても違うが、ディーリアスあたりまでの響きの分厚い後期ロマン派作品、やはり独欧系の楽曲に適性をかんじる(リヒャルトやマーラーのような)。ハレとなるとなおさら出来不出来があり、アンサンブルはともかく個人技的にはレベルがばらけた印象が否めない。この作品は過渡期的とはいえ前期の覇気に満ちた主情的な書法と後期の精緻な構造からなる主知的な書法が共存する妙味があり、1,2番の冗長さからも4番以降のとりとめのなくなりがちな性向からも離れた一般的な魅力に溢れた作品だと思う。とくに1楽章は民族的リズムのキレが要であり、大昔これをきくとマーラーの巨人の舞曲楽章を思い浮かべたものだが、ハレでバルビだと重量感も余り感じられずノリが半端な感が否めない。好き好きだろうが、私は余りのれなかった。もちろん、これが最晩年の演奏様式にのっとっているせいもあるだろう。中間楽章(緩徐楽章)の旋律的魅力が4番以降より劣っている感もあるのでなおさらバルビの歌心が生かせない曲でもあるのかもしれない。無印。ステレオ。
個人的にバルビのシベリウスやRVWのシンフォニーは音のキレが甘く、テンポがもったりした感じがして余り好きではない。もちろん時期や作品、また楽章によっても違うが、ディーリアスあたりまでの響きの分厚い後期ロマン派作品、やはり独欧系の楽曲に適性をかんじる(リヒャルトやマーラーのような)。ハレとなるとなおさら出来不出来があり、アンサンブルはともかく個人技的にはレベルがばらけた印象が否めない。この作品は過渡期的とはいえ前期の覇気に満ちた主情的な書法と後期の精緻な構造からなる主知的な書法が共存する妙味があり、1,2番の冗長さからも4番以降のとりとめのなくなりがちな性向からも離れた一般的な魅力に溢れた作品だと思う。とくに1楽章は民族的リズムのキレが要であり、大昔これをきくとマーラーの巨人の舞曲楽章を思い浮かべたものだが、ハレでバルビだと重量感も余り感じられずノリが半端な感が否めない。好き好きだろうが、私は余りのれなかった。もちろん、これが最晩年の演奏様式にのっとっているせいもあるだろう。中間楽章(緩徐楽章)の旋律的魅力が4番以降より劣っている感もあるのでなおさらバルビの歌心が生かせない曲でもあるのかもしれない。無印。ステレオ。