時代を駆ける:土井香苗/5 難民裁判負けたが意義は大
<00年10月に弁護士登録。引き受け手のない外国人の刑事事件が初弁護だった>
中国人による窃盗事件でした。通訳2人に助けられました。1人の男性は、留置所に入ったことのある在日中国人で、食べ物は差し入れられないとか、午前中にたばこをもらえるとか、“実務”を教わりました。もう1人の女性には、中国の社会背景を学びました。被告は中国の中でも貧しい地域の出身でした。生活ぶりを濃密に聞き、なぜ罪を犯したかを聞きました。同じ空間にいながら、私と彼との間の生まれながらにしての格差を感じました。有罪判決でしたが、初めて1人の人間の事件を請け負い、正義感をぶつけました。
<01年9月11日に米同時多発テロが起き、翌月に米国などがアフガニスタンで開戦。日本では同月、アフガン人の難民申請者9人が突然、東京入管に強制収容される「アフガニスタン難民一斉収容事件」が起きた>
タリバン政権に迫害されて逃れてきた難民申請者が、アフガン人だという理由だけで、家宅捜索され拘束されました。テロ対策といえば何をしてもよいと言わんばかりの人権侵害で、“冤罪(えんざい)”です。20人ほどの弁護団に加わりました。
01年11月、東京地裁が強制収容を違法と決定し、難民は収容所からカトリック教会へ移りました。しかし翌月に東京高裁が決定を覆し、再収容を決めました。難民たちに告げ、事情を説明すると、私が担当していたモハマドさん(仮名)は小さな声で「喜んで従います」と言われました。それだけ私たちを信用してくれていました。自分の足で収容所へ歩く姿を見るのはつらかった。
<「立てこもり」も検討した>
実は再収容を拒否する「立てこもり」を提案し、弁護団でも議論しました。弁護士と支援者で見守る24時間シフトも決めました。泣き叫ぶ難民を入管職員が引っ張っていく映像は国民に衝撃を与えるはず。国際法(難民条約など)に反した国内の悪法に従う義務はありません。しかし安全に責任を持てないという結論に至りました。
それまで、(アフリカの)エリトリアで難民キャンプを見学したことはありましたが、世界で何が起きているのか、初めて直接触れる機会だったとも感じます。人間の尊厳がここまで踏みにじられているか、と。
<裁判闘争は負けた>
「大衆的裁判闘争」でした。NGO(非政府組織)と連携し、メディアに訴え、デモをして世論に訴える手法の有効性を知りました。その一方で、国家を変える難しさも知りました。検察の「女性枠」問題では、権力と対峙(たいじ)している実感はありませんでした。無邪気に取り組み、うまくいった。アフガン弁護団は、何十人もの弁護士が何年もかけて全精力を投入しても難しかった。裁判は、結果的に全部負けました。
<得たものは大きかった>
難民申請者の権利拡大という意味では、無駄ではありませんでした。
瀋陽総領事館に北朝鮮人が亡命を求めた事件(02年5月)を機に、難民認定制度が一部変わりました。難民不認定処分への異議申し立てに対し、新たに設けられた難民審査参与員の意見を聞くことになりました。中途半端とはいえ、処分の実態が初めて第三者の耳にはいるようになった意義は大きいと思います。私たちの事件も影響したはずです。
法務省の中でも、ある程度、思いは共有されていたのだと思います。この10年で難民認定数は増えました。新聞とテレビも国家の大事な課題として取り上げるし、多くの大学生が支援団体に加わり、“自己増殖”しています。アフガン難民問題で激しくやり合った入管職員が、ヒューマン・ライツ・ウォッチでの今の活動を知り、いきなり「新聞で見た」と携帯電話に連絡してきたこともありました。私を「敵」だと思っていたら電話はしてきません。
モハマドさんは今、ドバイにおられます。日本で幸せになるのが一番良かったのですが、「結婚した。子供もいて幸せだ」と聞き、良かったなと思います。当時、(一時的にでも)送還を防いだ意味は大きかったし、日本が良くなるきっかけになると信じています。
毎日新聞 2010年3月9日 東京朝刊
時代を駆ける:土井香苗/6止 人権外交を“書く”存在に
<弁護士業務を中断して05年9月~06年5月、米ニューヨーク(NY)大学の法科大学院へ留学して国際法修士課程を修了。NY州の弁護士資格も取得した>
「世界の人権侵害を止めたい」という思いはずっと強く持っており、その勉強のために留学しました。
少人数のゼミで体験を共有したのが楽しかった。留学生はみな、母国の豪州、チリ、グルジア、中国などで既に人権や環境問題などに取り組む公益弁護士として経験を積んでいました。私たちより少し若く、弁護士を目指す米国の院生がそれに加わります。
例えば中国人の愛称ジャックさん。北京大学卒業後に「人民のために弁護活動をしたい」という熱い思いで、最初は大連で役人になりました。困窮世帯に住居を提供する部署に配属され法務サービス事業を設立しました。ところが汚職を見つけて変革を訴えると、上司に事業をつぶされました。辞職し、傷心のままの留学です。偉いと思うし、中国で人権派弁護士を務める難しさを実感しました。
<公益弁護の手法を学んだ>
ゼミの指導教授は、公益弁護が専門。環境問題や人権問題に直面し、弁護士が法廷に立つだけでなく、国会議員や報道機関に働きかけて大衆運動を起こし、役所と交渉して社会を変える手段を研究していました。まさにアフガン難民弁護団のような活動です。
教授は日本と中国の法律に詳しく、水俣病訴訟を分析し、解放運動や男女賃金差別訴訟などもよくご存じでした。大学院で、日本の弁護士活動が世界でもすごく高いレベルにあることに気付かされました。日本の弁護士が生活のかなりの部分を割いて被害者とかかわり、全体を救済する運動をしています。
<ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)との縁ができた>
NY大を選んだのは、主にフィリップ・アルストン教授の授業を受けたかったからです。国際人権法では随一の学者です。授業は、本物の人権侵害例を取り扱います。「問題が生じている政府へ書簡を書きなさい」という課題が出て、「模範解答」としてHRWの書簡が紹介されることが多いのです。HRWで勉強したいと強く思いました。
<06年9月~07年7月、HRW本部で活動した>
国際交流基金(東京)のフェローシップ(奨学金)付きで本部のフェローにしてもらいました。「日本国内の人権状況の調査員」として申し込むと、逆に「日本政府などへのアドボカシー(政策提言)担当でなら」と提案されました。その視点に「ほーっ」と思いました。
「日本政府はもっとできる」ということです。大きな人権侵害を無くすには、最も力のある人を動かすと効果的。日本が「力のある人」です。フェローを終えるころに東京オフィス開設の話が持ち上がりました。
<昨年4月、HRW東京オフィス開設に向けチャリティーディナーを開いた。世界の人権侵害を日本から止める活動が動き出した>
東京オフィス開設が、この1年の最大の成果です。NGO(非政府組織)にはお金集めという大きな壁が立ちはだかります。プロとしての能力とプロダクト(提供できる事業)があり、魅力もあっても、資金が無ければ無駄になります。
開設時の目標は年間2500万円。本部と同じやり方で、ディナーを開くことにしました。テーブル席(8人)100万円、そのほかに1席3万5000円のチケットを用意。企業人の知り合いもほとんどおらず、不安はありました。
司法試験の勉強仲間だった岩瀬大輔さん(ライフネット生命副社長)にお願いしてみました。そして、人々が理不尽な目に遭うことに怒り、同情する心を持つ企業人が多いことを知りました。岩瀬さんが留学した米ハーバード大学ビジネススクールは、企業の社会的責任について教えるそうです。紹介していただいたマネックス証券CEO(最高経営責任者)の松本大(おおき)さんも含め、結局160人がチケットを購入してくださり、目標にほぼ達しました。
私たちは、日本政府の人権外交政策を“書く”存在になりたい。総理大臣が人権危機の現場に行き、その発言が国内メディアだけでなく、英BBCなど海外メディアも注目するような存在にしたい。その時、HRWがメディアに登場する必要もなくなります。=土井さんの項おわり
毎日新聞 2010年3月10日 東京朝刊

















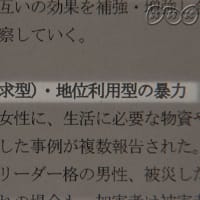

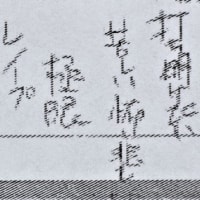






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます