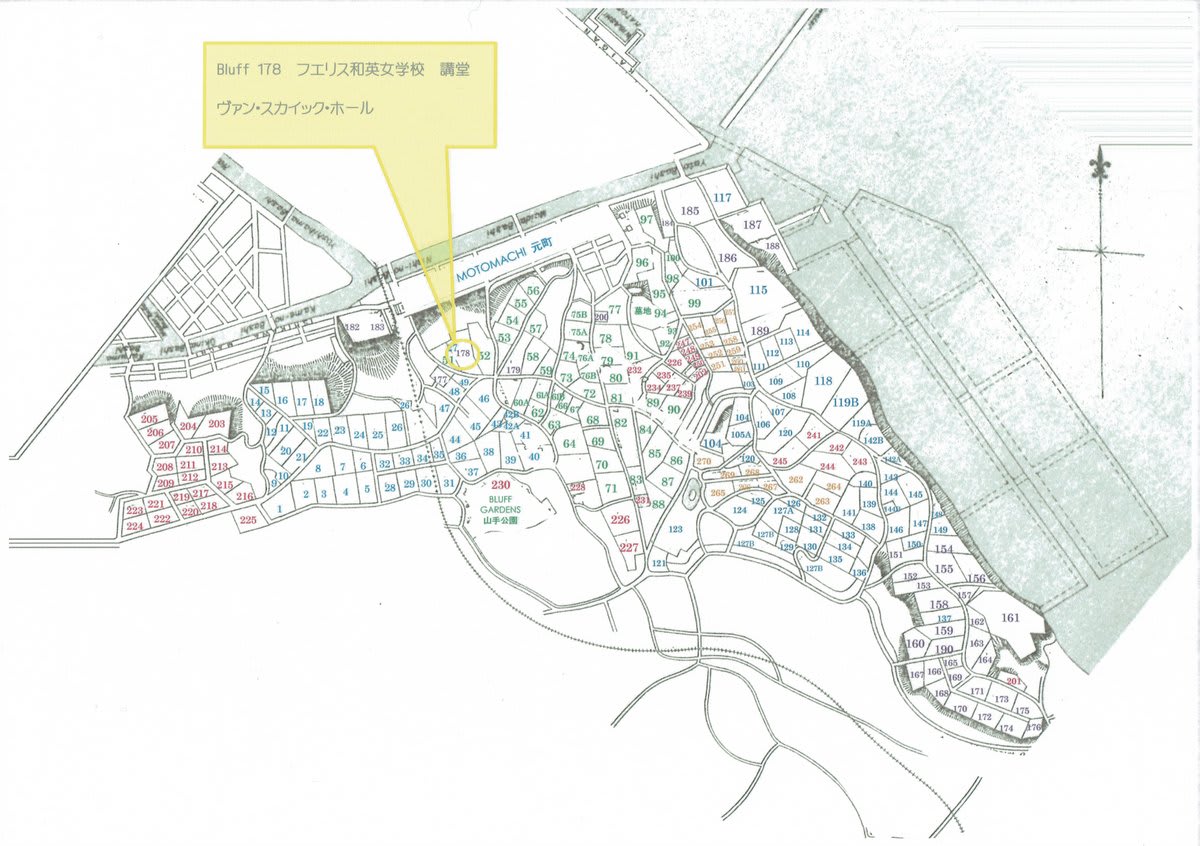モリソン氏は厚く堆積した時を掘り起こすかのように、かつての横浜の様子を語り続けた。
英国人らしく、時に笑いを誘う巧みな語り口に、人々は熱心に耳を傾けていた。
東京横浜間の日本初の鉄道開通について少しお話しましょう。
光栄にも外国人商工会議所の会員として私も臨席しました。
それは1872年のことで、お察しの通り極めて印象的な儀式でした。
§
天皇陛下と高官たちが横浜にお越しになりました。
全員が古式ゆかしい宮廷の衣装に身を包み、今では古い絵の中でしか見られないような錦の裾を引き、奇妙な被り物をしていました。
§
何千人という日本人の姿が見られ、外国人コミュニティー全員が商工会議所の委員会に率いられて繰り出していました。
会頭は故マーシャル氏で、帝に祝辞を述べました。
§
何人かの外国人がこの貴重な機会に陛下に拝謁しましたが、今、日本に残っているのは私の知る限り我らが古き友、ウィーラー医師だけです。
当時は東京の英国領事館の医官を務めていました。
§
居留地で誰知らぬ者のないウィーラー医師の名前が出ると、会場から大喝采が起こった。
モリソン氏の話は鉄道開通から当時の生活の様子へと移っていく。
§
まずビジネス ライフから始めましょう。
それは現在とは全く異なっていました。
ずっと楽なものでした。
まず、煩わしい電報というものがなく、月に2回手紙が届くだけでした。
P&O(ペニンシュラー アンド オリエンタル スチーム ナビゲーション)とフレンチ メールで、いずれも上海経由でした。
§
当時、手紙は重要なものでした。
1週間もかけて書き続け、しばしば夜更けまでかかりました。
しかし手紙を出してしまえば商人たちのコミュニティーには安堵感が広がり、手紙の次の日はほとんど常に、当たり前のように休日と見なされていました。
馬に乗ってピクニックに行ったり、クリケットの試合をしたり、その季節にふさわしい気晴らしにふけることができたのです。
§
よく思い出すのは親愛なる老ハリー・リーマンのことです。
ギルマン商会に勤めていた人で、家は64番地の平屋でした。
現在はインターナショナル バンクが建っているところです。
灌木に囲まれた美しい庭があり、客を温かく出迎えるドアの前には池があって、魚が泳いでいました。
§
リーマンは幸運にもフランス人のシェフを雇っていました。
彼はよく友人たちに一種の回状式招待状を出したものです。
こんな具合です。
「壮健なる若者数名を何月何日に求む」―もちろん手紙の翌日です。
「ゲーム パイやらなにやら、季節の珍味についてのアルフォンソの最新の試みを正しく評価することにご協力いただきたい」。
お察しの通り、我われ全員が応じました。(笑)
§
当時は、煩わしい電報などなかったと申し上げましたが、まれには例外もありました。
ヨーロッパと電線で直接連絡がとれる場所のうちで一番近かったのはセイロンでした。
そこで当然のことながら日本にいるすべての商人はメッセージのやり取りのためにセイロンに通信員を置いていました。
§
その頃の暗号は極めて原始的で、私が覚えている自分の最初のものはごく普通の通帳で、皆様に今宵お目にかけたかったのですが、ほかの古い記録とともにガラクタ用のゴミ捨て場、すなわち倉庫に埋もれてしまっていました。
§
当時、電報で使われる暗号はシンプルな言葉の方が、危険が少ないと思われていました。
ただ、私自身の経験はこの考えを裏付けるものとは言えませんでした。
次のような出来事があったことから明らかです。
§
あるとき600箱の窓ガラスを注文したところ、リバプールにいた私の友人たちは石炭の積み荷を送って来たのです。(会場爆笑)
電報を受け取った時、積載量600トンの小さな船を手配できませんでしたが、力を尽くして850トンのドイツ船はチャーターすることができました。
余計の250トンでお困りにならないとよいのですが、と書かれていました。(再び爆笑)
§
当時、貨物はすべて帆船で喜望峰を回って送られてきたと申し上げたら、興味を持っていただけるかもしれません。
片道200日は当たり前、220日かかることさえありました。
§
ここで思い出すのはブリリアントという名の小さな船のことです。
リバプールの友人たちから送られてくる貨物用に使っていたのですが、航海日数は常に100日以内でした。
§
この船は有名なジャパニーズ ティー クリッパー(日本茶の輸送に使われた大型帆船)の一つで、ベネファクターとベネファクトレスというアメリカ船とともに名誉を分かち合っていました。
主だった茶の輸出商の間には常に厳しい競争があって、どの船でも、たまたまそこにあるか、または声をかけられるところにあれば、チャーターしてシーズン最初の収穫をニューヨークかサンフランシスコに届けようとしました。
§
茶の話といえば、私が上海で製茶検査人をしていたことはご興味を引くかもしれません。
スエズ運河経由の蒸気船ではじめて茶が出荷された時です。
最初の船はたしかアガメムノンというホルト社の船だったと思います。
§
製茶検査人をしていたときのことで覚えているのは、茶を扱う上海の業者の間で、新茶もしくはどんな種類の茶でも、鉄製の蒸気船に密閉されたまま熱帯を通過することに耐えうるかという問題が議論され、ロンドンのドックに到着したときいかなる状態を呈するかということについて、多くが深刻な疑念を抱いていたことです。
後になってみれば、当時私たちを悩ませていた疑念や不安を笑うこともできましょうが、40年前、それらはまさに現実的で重大なことと考えられていたのです。(次回に続く)
図版:「鉄道開通式:帝に向けて横浜の商人達からの祝辞を述べるマーシャル氏」The Illustrated London News, Dec. 28 1872
参考資料:
・The Japan Weekly Mail, January 9, 1909, January 16, 1909
・J. P. Mollison,‘Reminiscences of Yokohama', Japan Gazette, Yokohama, January 11, 1909
・斎藤多喜夫『横浜外国人墓地に眠る人々』(有隣堂、2012)