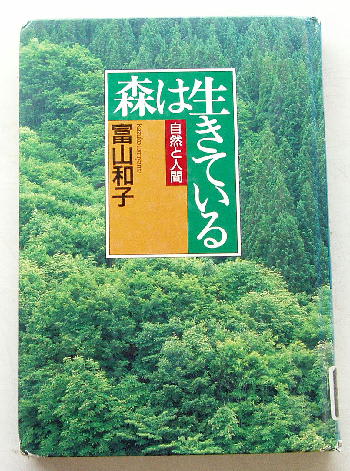電子辞書が壊れてしまい 不自由していました
新しく買おうと思ったら 結構お高くて 断念!
昔使った、国語辞典を出してきて パソコン周りに置いてあります
あまり分厚くない お手ごろサイズの 新明解・国語辞典

これ↑は 第4版ですが 現在は 第6版が売られているようです
たまたま 気になっていた言葉↓を調べてみました

耕耘機 か 耕運機 か・・・? ずっと疑問に思っていました
ちなみに、携帯(ドコモのらくらくホンⅤ)の変換では
耕耘機は出ません 耕運機と出ます
新明解の説明だと…
耘 という字は 〔田畑の雑草を除き去る意〕 とありますねぇ
私は 草を取ってから 耕耘機をかけていましたが
草を取らずに 耕耘機 かけちゃっても いいのかな~?(笑)
この新明解・国語辞典は
語釈や用例に独特の表現を用いており ファンが多いそうです
1996年、赤瀬川原平著『新解さんの謎』 で
その個性が取り上げられ ベストセラーになったそうです
私も 『新解さんの謎』は 持っていたはずなのに
処分したようで 書架にありませんでした
ネット上にも いろいろ面白いページがあります
読んでいると 笑っちゃったりします
電子辞書が 買えないおかげ(?)で ちょっとした 暇つぶしになりました
暇なときは “新解さん”と 遊ぶのも良さそうです
新しく買おうと思ったら 結構お高くて 断念!
昔使った、国語辞典を出してきて パソコン周りに置いてあります
あまり分厚くない お手ごろサイズの 新明解・国語辞典

これ↑は 第4版ですが 現在は 第6版が売られているようです
たまたま 気になっていた言葉↓を調べてみました

耕耘機 か 耕運機 か・・・? ずっと疑問に思っていました
ちなみに、携帯(ドコモのらくらくホンⅤ)の変換では
耕耘機は出ません 耕運機と出ます
新明解の説明だと…
耘 という字は 〔田畑の雑草を除き去る意〕 とありますねぇ
私は 草を取ってから 耕耘機をかけていましたが
草を取らずに 耕耘機 かけちゃっても いいのかな~?(笑)
この新明解・国語辞典は
語釈や用例に独特の表現を用いており ファンが多いそうです
1996年、赤瀬川原平著『新解さんの謎』 で
その個性が取り上げられ ベストセラーになったそうです
私も 『新解さんの謎』は 持っていたはずなのに
処分したようで 書架にありませんでした
ネット上にも いろいろ面白いページがあります
読んでいると 笑っちゃったりします
電子辞書が 買えないおかげ(?)で ちょっとした 暇つぶしになりました
暇なときは “新解さん”と 遊ぶのも良さそうです