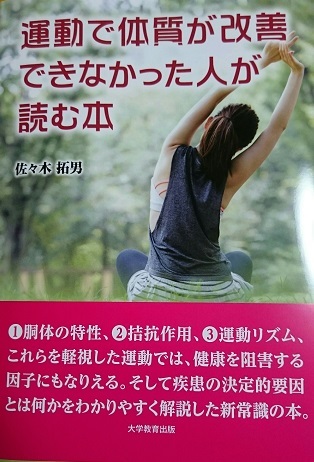最近夏風をひかれている方が本当に多いです。寒暖の差にご注意下さい。ということで、今回はメルマガ10話目をご紹介致します。まだ、ダイバーさん対象の記事ですが。以下に。
最近、何となく身体がだるいと訴える患者さんが多いようです。
特に働き盛りの女性に多くみられます。確かに季節の変わり目なので、湿度の上昇・気圧の変化などに身体が対応しきれず、自律神経のバランスを崩しやすくなっています。またこの時季、会社や電車などで冷房を始めていますね。しかも寒さを感じるほどで、設定温度が低すぎます!男性の仕事着に合わせているのはわかりますが、これは異常です。特に冷え性の方には、冬よりもむしろ夏の冷房による冷えがつらいと訴える方が少なくありません。
まずは、冷たい風が直接肌に触れやすい首回りに留意しましょう。
以前、風邪の対処法としてコラムで紹介したと思いますが、首の付け根の後ろにはたくさんのツボがあり、脊椎的にものどや肺などの神経根が集中しています。
そこを冷やすと、風邪をひきやすいだけでなく血流が悪くなり、首や肩の凝りの原因にもなります。スカーフなどを巻いて、絶対に冷やさないようにして下さい。また体温を下げないように、ホッカイロや腹巻などでお腹を暖めましょう。こうすることで内臓の冷えを防ぎ、副交感神経を活発にし、体全体の血流を手や足先に至るまで改善できます。
できれば出勤前後に早歩きをしたり、半身浴で汗を流したり、ストレッチを行なったりして、一日の代謝量を上げたいものです。これにより自律神経のバランスが保たれます。
男性は外出先から戻ったら、冷たい物を飲みながら5分ほど扇風機にでもあたってください。またデスクの下に氷を入れたビニール袋などを素足の下に置き足を冷やすと、身体の熱も収まるでしょう。
この夏、電力の不安がささやかれているわけですから、省エネを意識しましょう。そうしないと、いつまでたってもヒートアイランド現象の悪循環は断ち切れません。エアコンの設定温度を上げるなど、皆さんの意識改革が必要です!自然を愛するダイバーの皆さんは、温暖化などによる環境破壊を誰よりも憂慮されているのではないでしょうか。率先して地球にやさしい環境作りを行なって頂きたいと思います。
今回は整体のみならず地球環境についても意見を述べさせて頂いたため、私自身が熱くなってしまいました。