いずみたかひろ作『カッチン』(小峰書店)
『カッチン』の舞台は、昭和34年から35年の神戸。
いずみたかひろさんの自伝的ともいえる長編(短編連作)です、
高度経済成長期がはじまったばかりの、空気感が伝わってきます。
恥ずかしながらワタクシメ、最近「長編作品」を読むことから逃げておりましたが(/ω\)
「カッチン」を読み始めたら止まらず、ずっぼりとワタクシメが生まれる前の神戸の街にタイムスリップし、
カッチンの仲間の一人になったような気分になりました。
余談になりますが・・・「カッチン」を読みながら、
ーーこの感覚が「読書の楽しさ」なのだと、ワタクシメの冬眠していた感覚をも目覚めさせてくれた一冊です。

【本の帯より】
いつも運河は、この街のかたわらを流れている。
みんなの生きているこの街を見守っていてくれるようだ。
カッチンの駆けぬけたこの街。
あの時代の風景は、今はもうないかもしれない。
でも、昔のように運河は流れ、生きる人びとの心は、
今も、あたたかい。
人がいて人とふれあい、自分という人間は独りで生きているのではないことの喜びにであえる物語。
子どもを取り囲むコミュニティ
ただいまは、どうしたって「川崎中1殺害事件」のことが頭から離れません。
事件の全容がわからないので、直接的なことを書くのは控えますが・・・
「カッチン」と川崎の事件とはクロスする所があります。
しかし、「カッチン」の生きる世界には希望があるのです。
ーーなにが・・・どう違うのか?
今日も近所の学童保育クラブの卒所式にお招きいただき、「どうして、どうして?」と考えていました。
たぶん来賓であいさつされた方たちや児童館のスタッフも、あの事件を受けて想いは一つだったことでしょう。
学童保育クラブは卒業だけど、児童館にはいつでも来ていいんだよ。
もちろん学校の先生も、
地域の、隣近所の人でも、
困ったことがあったら相談して・・・と、例年よりも力がこもっていた気がします。
それは子どもに対してだけではなく、保護者に対しても、です。
卒所式に出席するメンバーは常にそういうスタンスをお持ちでしょうが、
おとな一人一人が「子どものコミュニティ」を正しくサポートしなければいけない思います。
話を「カッチン」に戻しますが・・・この作品の登場人物=子どもたちはそれぞれ大きな荷物を背負っています。
カッチンこと和男は、野球が大好き。まっすぐで熱い性格で、友だちのためなら、泥だらけキズだらけになろうとも突き進みます。
仲のいい俊介、ユージ。
運河のダルマ船で暮らす桃子は「家なしっ子」とからかわれて、街を去っていきました。桃子はカッチンの初恋の相手か?
浪曲を語るのがうまい拓ボン。
野球がうまくて喧嘩が強い龍成は実は朝鮮人で、祖国に帰ってしまいます。
柊太は病気がちな家族を支えるためにをくず鉄集めに忙しく、学校にもなかなか行かれません。
カッチンたち子どもは悲しみや悔しさを抱えながらも、それを「絆」にして成長していきます。
そして、おとなたちも人間味があふれています
学校の先生たちにも「情」ありました。
自転車を「女乗り」する優しいヤッサンは喫茶店のウエイター。カッチンたちをいつも応援してくれます。
街全体が子どもたちを見守り、「コミュニティ」を作り上げていた様子がよくわかります。
おとなに読んでほしい、児童文学
「カッチン」は児童文学として描かれていますが、おとなが読むべき作品です。
いびつになってしまった「子ども社会」を修復するのはおとなの責任ですから、半世紀ほど前に立ち返り、現在を見つめ直す必要があります。
タイムリーに、今、ぜひ、読んでいただきたい作品です。
『カッチン』の舞台は、昭和34年から35年の神戸。
いずみたかひろさんの自伝的ともいえる長編(短編連作)です、
高度経済成長期がはじまったばかりの、空気感が伝わってきます。
恥ずかしながらワタクシメ、最近「長編作品」を読むことから逃げておりましたが(/ω\)
「カッチン」を読み始めたら止まらず、ずっぼりとワタクシメが生まれる前の神戸の街にタイムスリップし、
カッチンの仲間の一人になったような気分になりました。
余談になりますが・・・「カッチン」を読みながら、
ーーこの感覚が「読書の楽しさ」なのだと、ワタクシメの冬眠していた感覚をも目覚めさせてくれた一冊です。

【本の帯より】
いつも運河は、この街のかたわらを流れている。
みんなの生きているこの街を見守っていてくれるようだ。
カッチンの駆けぬけたこの街。
あの時代の風景は、今はもうないかもしれない。
でも、昔のように運河は流れ、生きる人びとの心は、
今も、あたたかい。
人がいて人とふれあい、自分という人間は独りで生きているのではないことの喜びにであえる物語。
子どもを取り囲むコミュニティ
ただいまは、どうしたって「川崎中1殺害事件」のことが頭から離れません。
事件の全容がわからないので、直接的なことを書くのは控えますが・・・
「カッチン」と川崎の事件とはクロスする所があります。
しかし、「カッチン」の生きる世界には希望があるのです。
ーーなにが・・・どう違うのか?
今日も近所の学童保育クラブの卒所式にお招きいただき、「どうして、どうして?」と考えていました。
たぶん来賓であいさつされた方たちや児童館のスタッフも、あの事件を受けて想いは一つだったことでしょう。
学童保育クラブは卒業だけど、児童館にはいつでも来ていいんだよ。
もちろん学校の先生も、
地域の、隣近所の人でも、
困ったことがあったら相談して・・・と、例年よりも力がこもっていた気がします。
それは子どもに対してだけではなく、保護者に対しても、です。
卒所式に出席するメンバーは常にそういうスタンスをお持ちでしょうが、
おとな一人一人が「子どものコミュニティ」を正しくサポートしなければいけない思います。
話を「カッチン」に戻しますが・・・この作品の登場人物=子どもたちはそれぞれ大きな荷物を背負っています。
カッチンこと和男は、野球が大好き。まっすぐで熱い性格で、友だちのためなら、泥だらけキズだらけになろうとも突き進みます。
仲のいい俊介、ユージ。
運河のダルマ船で暮らす桃子は「家なしっ子」とからかわれて、街を去っていきました。桃子はカッチンの初恋の相手か?
浪曲を語るのがうまい拓ボン。
野球がうまくて喧嘩が強い龍成は実は朝鮮人で、祖国に帰ってしまいます。
柊太は病気がちな家族を支えるためにをくず鉄集めに忙しく、学校にもなかなか行かれません。
カッチンたち子どもは悲しみや悔しさを抱えながらも、それを「絆」にして成長していきます。
そして、おとなたちも人間味があふれています
学校の先生たちにも「情」ありました。
自転車を「女乗り」する優しいヤッサンは喫茶店のウエイター。カッチンたちをいつも応援してくれます。
街全体が子どもたちを見守り、「コミュニティ」を作り上げていた様子がよくわかります。
おとなに読んでほしい、児童文学
「カッチン」は児童文学として描かれていますが、おとなが読むべき作品です。
いびつになってしまった「子ども社会」を修復するのはおとなの責任ですから、半世紀ほど前に立ち返り、現在を見つめ直す必要があります。
タイムリーに、今、ぜひ、読んでいただきたい作品です。












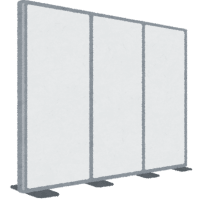








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます