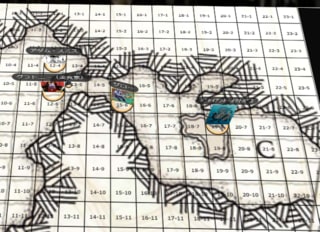恐怖の地下神殿を脱出してもまだ危険な状況に変わりはない。ジャングルにはまとわりつく不快な羽虫だけではない。回復困難な毒や病気を与える毒虫や致命的な怪物が至るところを徘徊している。しかしヒューマンを超越した野生の感覚と隠密能力を持つクレシダ、超人的なモンクの肉体を持つグラトニー、そしてここよりもっと恐ろしい世界から来たザローが一心同体となれば、ただのサバイバル程度はピクニック同然だ。
ファルジーンの門までは問題なくたどり着いた。門の周囲の人はまばらだが、隠しようのない緊張が漂っている。守衛は街の外よりも中を警戒しており、ジャングルから現れたグラトニーとザローがすぐそばに来るまで全く気づかなかった。
「お前たち何故戻ってきた」二人に気付いた守衛が言った。
「何故?、この島で他に行くところがありますか?」おかしなことが、町で進行していることを感じながら、ザローは率直に問い返す。
「…。とにかく、少しここで待て」守衛が仲間に合図を送ると、1人がどこかへ急いで向かった。
しばらくすると、伊達者食屍鬼のラプトンが手下のグールを引き連れてやってきた。
「こんにちは皆さん、探し物は見つかりましたか?ネコちゃんでしたか、ワンちゃんでしたか?」
「ああ、見つけたが、散々暴れまくった挙句、穴の底に埋まってしまったよ」グラトニーがラブトンに顔を近づけ、鋭い犬歯を見せつけながら、ひと言ずつ区切るように言った。
「それは骨折り損のくたびれもうけ。でもまあ、可愛い猫ちゃんは他にもたくさんいるから、大丈夫ですよ」
通りの向こうから、モマオが数人の部下を連れてやってきた。その1人はロタールを上回る立派な体格をした大男だ。
「なんだ、もう来たんだ。せっかくお喋りを楽しんでいたのに」
「急ぐようにとのご命令だったので」
「全く貴方は真面目ですね。怠け者のロタールとは大違いです。残念だけどお喋りはお終いです。モマオ、彼らを拘置所にお連れして」
モマオはグラトニーを見てかすかに頷く。
《モマオには何か考えがあるようね》
「では。君たちまた後ほど。次はこれほど穏やかではいられないかもね。ああそうだ、大事なお客様だから、ここにいるグールの諸君も同行させないとね」ラプトンは親しげな仮面の下にある狡猾さを覗かせる。
拘置所まであと少しのところで、モマオは剣を引き抜くと、脇にいたグールの腹に柄まで突き刺した。それを合図に他の警備兵もグールに攻撃を開始した。ひときわ目立つ大男の戦いぶりは激しく、グールをまるで綿を詰めた布の人形のように軽々と振り「回し、叩き潰している。モマオは今急に目覚めたかのようにまばたきをして、大男を見た。
「そういえば…、お前は誰だ!?」
「僕の名はアダム・スミス。君たちに世界の危機を警告するため、次元を超えて来た」両手を岩のように固めて最後のグールを叩き潰つぶすと、巨漢の漢はゆっくりと近づく。
モマオはザローとグラトニーの二人がそろって目を閉じ、首を振るのを見て答える。
「世界の危機とはただ事ではないな。私には君の方がよっぽど剣呑に感じるが」
アダムはモマオが何を言っているのか理解できないという風に首をかしげ話を続ける。
「白猫の予言によれば、この地では大いなる邪悪な力が目覚めつつある。しかるべき時、しかるべき場所に予言された英雄が現れなければ、世界は滅びてしまう。僕は予言を成就させるためこの地に遣わされた」
《この会話…?》
「アダム・スミスさん、はじめまして。ザローと申します。次元に関しては、私たちは不案内ですので残念ながらご理解致しかねます。申し訳ありません。その上で貴方のお話を思惟すると、私たちに協力するというご提案であると考えて宜しいでしょうか?」
「その通り!!」
モマオと別れ、ザロー、グラトニー、クレシダにアダム・スミスを加えた一行は町からの脱出を図る。ここでもクレシダの隠密能力が発揮される。猫にとってはジャングルよりもむしろ町の方がその能力を発揮しやすい。人は猫を見ても、その存在を無視する。一部の人間は積極的に触れようとするが、それでも猫の行く手を阻むものではない。人気のない外壁にたどり着いた一行は密かに壁を越えジャングルに姿を消した。

先に町を脱出した人々もジャングルに逃げ込んでいる。しかし彼らにはこのジャングルは過酷だ。土地に生息する野獣ですら出会ったら生き残れるか分からないのに、この島には神話的怪物さえもが出現する。バイヤキーに襲われていた家族を助けた後、脱出者のキャンプにたどり着いた。
「お前たち無事だったか」
船大工のオーベッド・ヴェルトがこのキャンプのリーダだった。
「食屍鬼どもがどこから湧いて出たのかは分からん。おそらく島の外から来たのだろう。奴らが我が物顔で町を練り歩きだして-恥知らずなアルウィイのせいだ-、少なくない人々がジャングルに逃げ込んだ。そして皆ここにたどり着いたのだ。ドルイドとしての俺のパワーで皆を保護しているが、それもそろそろ限界だ」
「ロタールさん達はここには来ていないのですか?」疲れ果てた様子の難民達を見まわし、心配そうにザローが尋ねる。
「そう、彼が来てくれたら皆希望を取り戻せるのだが。一体どこに行ったのやら」
《センサ船長はどうしたのかしら?》
ザローはクレシダに頷いて、さらにオーベッドに尋ねた。
「それは残念です。ところでセンサ船長がどうしているか分かりますか?」
オーベッドは首を振り、辛そうに言った。
「彼女はアプトンに追われていた。忌々しい服装倒錯者め。最後に私が見たとき、彼女は海岸の方へ追い込まれていた。おそらく逃げ切れないだろう」
「そうですか」ザローはため息とともに言った。
明日への不安を抱えながらも、質素ながらも暖かい食べ物と見知った人々に囲まれた安心を感じていた。そのとき形のはっきりしない白いシフトドレスを着た女性が野営テントの中に実体化し、クレシダのと隣に腰掛け、彼女のビロードのような黒い毛皮を撫でながら言った。
「ファルジーンとその人々の運命よりももっと重要なことがあります。想像を絶する力を持つ、恐ろしい、古き異質な存在が、復活と、監禁からの解放のために、最初の一歩を踏み出しました。来るべき大変動を生き延びるには、あなたたちの助けが必要です。あなたたちは自分が何を相手にしているのかを知らなければなりません。その知識には代償が伴い、一度学んだら忘れることは出来ません」
「お前は誰だ?」グラトニーは霊体の女性を睨みつけながら言った。
「私は光の女神の司祭、ポンペア。私の肉体は敵の手により永劫の檻に囚われました。今私は貴方たちの心に直接話しかけています」
《私の力と似たようなものね》
「その通りです。今、私の精神は安全な別の次元にいます。私は貴方たちの疑問に答え、進むべき道を伝えるためにやってきました」
なおも警戒を解かないグラトニーが言った。「お前の身体は既に土砂の下、埋葬されたと言えなくもないな」
ポンペアは肩をすくめて笑った。「私の呪われた身体はもはや必要はありません。貴方たちは女神のお力を借りなければなりません。かつて光の軍団が悪鬼の教団を駆逐したように」
彼女の姿は揺らぎ、霞のようにゆっくりと蒸発していった。
難民の出現はジャングルの捕食者たちに気付かれずにはいられない。その朝、最も忌まわしい獣が食料を求めて現れた。何本もの触手、何本もの脚、何かがこすれるようなささやき声を出す無数の口をもつ怪物が、ジャングルの暗がりから現れた。円筒形の身体は、熱病に浮かされて見た最も恐ろしい悪夢を反映したようだ。雲のようにうごめく触手の1本が伸びて、催眠術にかかったかのように身動きしない島民をつかんで、のこぎりのような歯で覆われた口の一つに押し込んだ。
「あの足を見ろ、あれは山羊の足だ。無数の仔山羊の足だ。ああ、村人が仔山羊の群れに飲み込まれている!」
怪物の恐ろしい姿を見て、精神に支障をきたしたアダム・スミスが麻痺したかのように叫んでいる。
「しっかりしろアダム・スミス。あれは仔山羊の群れなどではない。少しばかり大きなカリフラワーの怪物だ。きっと喰ったらうまいぞ!」
《まったく、おかしな人たちばかりだわ》

仲間に励まされたアダム・スミスは正気を取り戻し、大きな体で敵の正面に立ちはだかる。グラトニーが死角から飛び出し、力みのない流れるような一撃で怪物の動きを止める。
「食屍門朦朧撃、神経締め。新鮮な食材の下拵えこそが究極の調理法!」
「禍福は表裏一体、ここでロタールが到着したのは正に慶賀。ですね」ザローは打ちひしがれていた人々の目に希望が戻るのを見て、心の底から言った。
「そうだな。あれほどの巨体、ここの人々の腹を満たすには十分だ」
《…どういう意味?》
「最高の誉め言葉だ」
ザローとグラトニーはロタールから町に潜入して武器を持ちだすように依頼された。
「それと私の斧を持ち帰ってくれたら、これまでの君たちの活躍への町からの感謝に加え、私個人としても永遠の友情を誓おう」ロタールは二人と固い握手を交わす。
オーベッドが進み出て言う。「武器の運搬にはこの魔法の袋を使うといいだろう。他に宝を見つけたらそれらはすべて君たちのものだ。入るだけ持ってくると良い。町へはこの裏の溶岩洞をから行けるはずだ。コウモリたちがそう言っている」
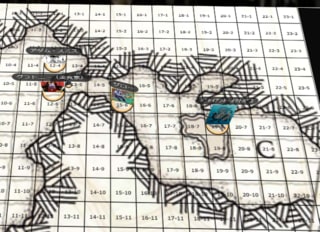
ファルジーンの門までは問題なくたどり着いた。門の周囲の人はまばらだが、隠しようのない緊張が漂っている。守衛は街の外よりも中を警戒しており、ジャングルから現れたグラトニーとザローがすぐそばに来るまで全く気づかなかった。
「お前たち何故戻ってきた」二人に気付いた守衛が言った。
「何故?、この島で他に行くところがありますか?」おかしなことが、町で進行していることを感じながら、ザローは率直に問い返す。
「…。とにかく、少しここで待て」守衛が仲間に合図を送ると、1人がどこかへ急いで向かった。
しばらくすると、伊達者食屍鬼のラプトンが手下のグールを引き連れてやってきた。
「こんにちは皆さん、探し物は見つかりましたか?ネコちゃんでしたか、ワンちゃんでしたか?」
「ああ、見つけたが、散々暴れまくった挙句、穴の底に埋まってしまったよ」グラトニーがラブトンに顔を近づけ、鋭い犬歯を見せつけながら、ひと言ずつ区切るように言った。
「それは骨折り損のくたびれもうけ。でもまあ、可愛い猫ちゃんは他にもたくさんいるから、大丈夫ですよ」
通りの向こうから、モマオが数人の部下を連れてやってきた。その1人はロタールを上回る立派な体格をした大男だ。
「なんだ、もう来たんだ。せっかくお喋りを楽しんでいたのに」
「急ぐようにとのご命令だったので」
「全く貴方は真面目ですね。怠け者のロタールとは大違いです。残念だけどお喋りはお終いです。モマオ、彼らを拘置所にお連れして」
モマオはグラトニーを見てかすかに頷く。
《モマオには何か考えがあるようね》
「では。君たちまた後ほど。次はこれほど穏やかではいられないかもね。ああそうだ、大事なお客様だから、ここにいるグールの諸君も同行させないとね」ラプトンは親しげな仮面の下にある狡猾さを覗かせる。
拘置所まであと少しのところで、モマオは剣を引き抜くと、脇にいたグールの腹に柄まで突き刺した。それを合図に他の警備兵もグールに攻撃を開始した。ひときわ目立つ大男の戦いぶりは激しく、グールをまるで綿を詰めた布の人形のように軽々と振り「回し、叩き潰している。モマオは今急に目覚めたかのようにまばたきをして、大男を見た。
「そういえば…、お前は誰だ!?」
「僕の名はアダム・スミス。君たちに世界の危機を警告するため、次元を超えて来た」両手を岩のように固めて最後のグールを叩き潰つぶすと、巨漢の漢はゆっくりと近づく。
モマオはザローとグラトニーの二人がそろって目を閉じ、首を振るのを見て答える。
「世界の危機とはただ事ではないな。私には君の方がよっぽど剣呑に感じるが」
アダムはモマオが何を言っているのか理解できないという風に首をかしげ話を続ける。
「白猫の予言によれば、この地では大いなる邪悪な力が目覚めつつある。しかるべき時、しかるべき場所に予言された英雄が現れなければ、世界は滅びてしまう。僕は予言を成就させるためこの地に遣わされた」
《この会話…?》
「アダム・スミスさん、はじめまして。ザローと申します。次元に関しては、私たちは不案内ですので残念ながらご理解致しかねます。申し訳ありません。その上で貴方のお話を思惟すると、私たちに協力するというご提案であると考えて宜しいでしょうか?」
「その通り!!」
モマオと別れ、ザロー、グラトニー、クレシダにアダム・スミスを加えた一行は町からの脱出を図る。ここでもクレシダの隠密能力が発揮される。猫にとってはジャングルよりもむしろ町の方がその能力を発揮しやすい。人は猫を見ても、その存在を無視する。一部の人間は積極的に触れようとするが、それでも猫の行く手を阻むものではない。人気のない外壁にたどり着いた一行は密かに壁を越えジャングルに姿を消した。

先に町を脱出した人々もジャングルに逃げ込んでいる。しかし彼らにはこのジャングルは過酷だ。土地に生息する野獣ですら出会ったら生き残れるか分からないのに、この島には神話的怪物さえもが出現する。バイヤキーに襲われていた家族を助けた後、脱出者のキャンプにたどり着いた。
「お前たち無事だったか」
船大工のオーベッド・ヴェルトがこのキャンプのリーダだった。
「食屍鬼どもがどこから湧いて出たのかは分からん。おそらく島の外から来たのだろう。奴らが我が物顔で町を練り歩きだして-恥知らずなアルウィイのせいだ-、少なくない人々がジャングルに逃げ込んだ。そして皆ここにたどり着いたのだ。ドルイドとしての俺のパワーで皆を保護しているが、それもそろそろ限界だ」
「ロタールさん達はここには来ていないのですか?」疲れ果てた様子の難民達を見まわし、心配そうにザローが尋ねる。
「そう、彼が来てくれたら皆希望を取り戻せるのだが。一体どこに行ったのやら」
《センサ船長はどうしたのかしら?》
ザローはクレシダに頷いて、さらにオーベッドに尋ねた。
「それは残念です。ところでセンサ船長がどうしているか分かりますか?」
オーベッドは首を振り、辛そうに言った。
「彼女はアプトンに追われていた。忌々しい服装倒錯者め。最後に私が見たとき、彼女は海岸の方へ追い込まれていた。おそらく逃げ切れないだろう」
「そうですか」ザローはため息とともに言った。
明日への不安を抱えながらも、質素ながらも暖かい食べ物と見知った人々に囲まれた安心を感じていた。そのとき形のはっきりしない白いシフトドレスを着た女性が野営テントの中に実体化し、クレシダのと隣に腰掛け、彼女のビロードのような黒い毛皮を撫でながら言った。
「ファルジーンとその人々の運命よりももっと重要なことがあります。想像を絶する力を持つ、恐ろしい、古き異質な存在が、復活と、監禁からの解放のために、最初の一歩を踏み出しました。来るべき大変動を生き延びるには、あなたたちの助けが必要です。あなたたちは自分が何を相手にしているのかを知らなければなりません。その知識には代償が伴い、一度学んだら忘れることは出来ません」
「お前は誰だ?」グラトニーは霊体の女性を睨みつけながら言った。
「私は光の女神の司祭、ポンペア。私の肉体は敵の手により永劫の檻に囚われました。今私は貴方たちの心に直接話しかけています」
《私の力と似たようなものね》
「その通りです。今、私の精神は安全な別の次元にいます。私は貴方たちの疑問に答え、進むべき道を伝えるためにやってきました」
なおも警戒を解かないグラトニーが言った。「お前の身体は既に土砂の下、埋葬されたと言えなくもないな」
ポンペアは肩をすくめて笑った。「私の呪われた身体はもはや必要はありません。貴方たちは女神のお力を借りなければなりません。かつて光の軍団が悪鬼の教団を駆逐したように」
彼女の姿は揺らぎ、霞のようにゆっくりと蒸発していった。
難民の出現はジャングルの捕食者たちに気付かれずにはいられない。その朝、最も忌まわしい獣が食料を求めて現れた。何本もの触手、何本もの脚、何かがこすれるようなささやき声を出す無数の口をもつ怪物が、ジャングルの暗がりから現れた。円筒形の身体は、熱病に浮かされて見た最も恐ろしい悪夢を反映したようだ。雲のようにうごめく触手の1本が伸びて、催眠術にかかったかのように身動きしない島民をつかんで、のこぎりのような歯で覆われた口の一つに押し込んだ。
「あの足を見ろ、あれは山羊の足だ。無数の仔山羊の足だ。ああ、村人が仔山羊の群れに飲み込まれている!」
怪物の恐ろしい姿を見て、精神に支障をきたしたアダム・スミスが麻痺したかのように叫んでいる。
「しっかりしろアダム・スミス。あれは仔山羊の群れなどではない。少しばかり大きなカリフラワーの怪物だ。きっと喰ったらうまいぞ!」
《まったく、おかしな人たちばかりだわ》

仲間に励まされたアダム・スミスは正気を取り戻し、大きな体で敵の正面に立ちはだかる。グラトニーが死角から飛び出し、力みのない流れるような一撃で怪物の動きを止める。
「食屍門朦朧撃、神経締め。新鮮な食材の下拵えこそが究極の調理法!」
「禍福は表裏一体、ここでロタールが到着したのは正に慶賀。ですね」ザローは打ちひしがれていた人々の目に希望が戻るのを見て、心の底から言った。
「そうだな。あれほどの巨体、ここの人々の腹を満たすには十分だ」
《…どういう意味?》
「最高の誉め言葉だ」
ザローとグラトニーはロタールから町に潜入して武器を持ちだすように依頼された。
「それと私の斧を持ち帰ってくれたら、これまでの君たちの活躍への町からの感謝に加え、私個人としても永遠の友情を誓おう」ロタールは二人と固い握手を交わす。
オーベッドが進み出て言う。「武器の運搬にはこの魔法の袋を使うといいだろう。他に宝を見つけたらそれらはすべて君たちのものだ。入るだけ持ってくると良い。町へはこの裏の溶岩洞をから行けるはずだ。コウモリたちがそう言っている」