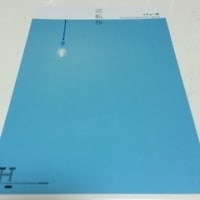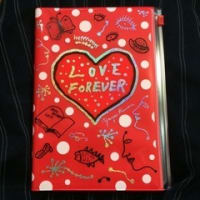見てきました
太田記念美術館
会期は2014年6月1日から2014年6月26日。
今回は相撲。
大相撲は日本固有の伝統文化で国技ともいわれています。
江戸時代"相撲錦絵"と呼ばれる浮世絵が人気を集めます。
江戸っ子は相撲が大好き、ということで、人気力士の肖像や取組、日常など様々な浮世絵が制作されました。
今回の展示は相撲絵収集家として知られる石黒和義氏秘蔵のコレクションから約100点で構成されています。
相撲だけの展示って初めてではないでしょうか。
相撲好きじゃないけど文化という点で興味あります。
そして、私一度だけ国技館で観戦したことがあるのです。
まだ朝青竜がいた時代。
升席で観戦するというより、場内の空気を楽しんでいましたが。。
実際の取り組みを見るのはおもしろかったです!!
勝川春英「邸内水入りの図」
まずは肉筆浮世絵から。
浜離宮での上覧相撲に取材しています。
水入りとなり力水を渡されている場面です。
桜が舞うシチュエーションで色彩も淡く、かなり美しい作品。
歌川芳員「勧進大角力取組図」
こちらも肉筆浮世絵。
番付は安政5年11月場所に基づくものですが、この場所は江戸大火で中止となりました。
驚くべきは観客の多さ。
あんなに遠くて見えるのか、と疑問に思います。
透視図法を使い、奥行き感じる作品です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「不知火・大鳴門」
こちらも肉筆浮世絵。
取組の様子が描かれていますが、力強い感じが出ています。
描かれているのは前年に入幕したばかりの不知火と前頭七枚目になったばかりの大鳴門。
注目の若手の取り組みです。
勝川春章「日本一江都大相撲土俵入後正面之図」
東方力士の土俵入りが終わって退場と同時に西方力士の土俵入り。
これも観客がすごいです。
透視図法によって奥行きがあり、奥まで観客ぎっしりです。
土俵がちょっと小さい印象があります。
歌川国貞(三代歌川豊国)「歴代横綱の図」
歴代の横綱が1枚に描かれたもの。
初代と第4~9代の横綱が描かれています。
最上段に初代の明石志賀之助。
彼は寛永年間に江戸で勧進相撲を始めたとされていますが、実在が疑問視されている存在です。
その人物を初代とされたのは明治に入ってから。
第12代横綱の陣幕久五郎によって初代に位置付けられました。
そのため、この絵では綱をつけていないのです。
綱をつけない状態で一番上に描かれているということは、その時代でも横綱ではなくても相撲上の重要人物ととらえられていたんですね。
歌川国貞(三代歌川豊国)「不知火諾右エ門 横綱土俵入之図」
第8代横綱です。
天保11(1840)年に横綱免許を受けました。
左には露払の黒雲龍五郎。右に太刀持ち高根山政右エ門。
柱の赤が目立ちます。
太い黒い輪郭線にはっきりとした色使い。
イラスト的です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「秀ノ山雷五郎 横綱土俵入之図」
第9代横綱。
身長は五尺四寸(約164cm)と歴代最小なんだそう。
周りと比較してもそこまで小さく見えないのはお相撲さんだからでしょうか。
二代歌川国貞「雲龍久吉 横綱土俵入之図」
第10代横綱です。
青々とした髭の剃り跡が目立ちます。
土俵入りの「雲竜型」に名を残した横綱です。
二代歌川国貞「不知火光右エ門 横綱土俵入之図」
第11代横綱。
色白美男子の人気横綱。
土俵入りの際の「不知火型」に名を残す横綱です。
男前でその華麗な土俵入りも江戸中の評判であったとか。
二代歌川国輝「陣幕久五郎土俵入りの図」
第12代横綱。
初代に明石志賀之助を置き、自らを12代目としました。
それが現在の横綱代数に使われています。
江戸最後の横綱でその後は明治維新の動乱に巻き込まれるも実業家として相撲関係の建碑事業に奔走しました。
二代歌川国輝「鬼面山谷五郎 横綱土俵入之図」
第13代横綱。
明治2(1869)年、数え44歳で横綱免許を受けました。
これは現在でも最高齢の記録です。
が、作品の中では老けている様子も見えず、周りの力士と変わらず見えます。
勝川春章「東方 鞍手山弥太夫・出水川林右衛門」
勝川春章は力士の風貌、体格をありのままに表現しようとし、相撲絵というジャンルを確立した存在です。
ここでは2人の力士が描かれています。
大きく力強い様子が伝わってきます。
鞍手山弥太夫のまわしには2頭の馬が描かれていて、ちょっとかわいい。
磯田湖龍斎「釈迦ヶ獄雲右衛門と娘」
巨人力士として明和末から安永初めに人気を集めた力士。
人差し指1本で娘を持ち上げているという何ともすごい情景が描かれています。
背は六尺六寸(約2m)、掌九寸五分(約29cm)、足は壱尺三寸(約40cm)、目方は拾八貫目余(約143kg)とものすごいサイズです。
歌川国安「大空武左衛門」
名前がいいですね。
大きくて強そう。
これは相撲を取っている場面ではなく、普段の様子を描いています。
青いストライプの着物の模様も名前のイメージと合っています。
歌川国安「大空武左エ門」
巨人力士として人気を集めましたが、実際に取組はしていません。
背は七尺五寸(約227cm)、掌壱尺二寸(約36.3cm)、足は一尺三寸五分(約41cm)、重さは三拾五貫目(約131kg)。
こちらもすごい……
描かれているのは23歳のとき、とされていますが、郷里の墓標では32歳だったそうで。。。
歌川国安「綿龍田郎」
前頭筆頭止まりでしたが、美男の力士として人気を博しました。
そう、かっこいい人ならば、幕下でも描かれたのです。
なんだか切ない世の中ですね。笑
歌川国貞(三代歌川豊国)「小柳常吉」
画面いっぱいに描かれ窮屈そうな印象も。
嘉永7(1854)年、ペリーが再来日した際にはアメリカ人水兵3人と同時に戦い、難なく打ち負かしたという逸話も残っている力士です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「生月鯨太左エ門」
手形を押す場面が描かれています。
この力士も巨人力士でしで、背は七尺五寸(約227cm)、重さは四十五貫目(約169kg)。
歌川国貞(三代歌川豊国)「生月鯨太左エ門」
さて、上の彼が押した手形です。
横浜美術館で開催された「魅惑のニッポン木版画」でも展示されていました。
その記事で「これ、本当の大きさかなぁ」と書きましたが、本人の背丈のサイズなどから考えても本当の大きさっぽいです……。
歌川国貞(三代歌川豊国)「白実弓肥太右エ門」
こちらも巨人力士。
背は六尺八寸二分(約2m)。
嘉永7年のペリーの再来日の際に米8俵を一度に運び驚かせたそう。
それは日本人でも驚くよ……
歌川国芳「鬼若力之助」
怪童力士として8歳から4年にわたり土俵入り。
後に幕内となりました。
怪童力士は出世しないとの話もあるようですが、見事です。
顔も幼く、全体的に丸いイメージです。
二代歌川国輝「東京 勝ノ浦与一右エ門」
その怪童力士のその後です。
立派になりました……笑
歌川広重「名所江戸百景 両ごく回向院元柳橋」
さて、ここからは相撲にまつわる景色など。
両国の回向院の境内から富士山と隅田川を望んでいます。
縦長の画面で描かれ空の高さ、空間の広さが伝わってきます。
青空がきれいです。
手前には相撲興行中に仮設された相撲櫓。
竹竿の先には晴天を願うため、麻の御幣がついています。
歌川広重「東都名所 両国回向院境内全図」
描かれているのは両国の回向院境内の中に建てられた相撲小屋。
とにかく巨大。
ものすごい大きさです。
近くを歩いている人と比較しても大きい。
ここに何人の人が入るのでしょうか。
歌川国郷「両国大相撲繁栄之図」
相撲興行中の旗がひしめき、米俵が積まれています。
相撲が江戸庶民の楽しみであったことなど、賑わいの伝わってくる作品です。
無款「絵番付」
番付、とは相撲における力士の順位表。
普通は力士の名前でかかれているのですが、これは力士のイラストで描かれています。
上からずらっと力士がぎっしり。
列車ごっこみたいにくっついています。
なんか迫力あります。
二代歌川国貞「相撲表四拾八手の図」
相撲の48の決まり手を簡単な解説とともに図解したもの。
おもしろいです。
ただ、何が何だか分かりません……
歌川春好「柏戸・江戸ヶ崎・谷風」
3人の力士の普段の様子です。
着物を着て歩いています。
一人は五代市川団十郎の似顔絵入りの扇子を持っています。
浮世絵で人気だったのは歌舞伎と相撲が味わえちゃいます。
歌川国輝「東都両国夕景之図」
両国橋で夕涼みをする力士と歌舞伎役者の一行。
豪華です。
が、力士が大きいため、遠近法の感覚がおかしくなりそうです。。。
以上になります。
相撲だけでこれだけの作品、、、というかもっとあるというのがすごい。
江戸時代の熱狂が伝わってくるようでした。
ブログランキングよかったらお願いします


太田記念美術館

会期は2014年6月1日から2014年6月26日。
今回は相撲。
大相撲は日本固有の伝統文化で国技ともいわれています。
江戸時代"相撲錦絵"と呼ばれる浮世絵が人気を集めます。
江戸っ子は相撲が大好き、ということで、人気力士の肖像や取組、日常など様々な浮世絵が制作されました。
今回の展示は相撲絵収集家として知られる石黒和義氏秘蔵のコレクションから約100点で構成されています。
相撲だけの展示って初めてではないでしょうか。
相撲好きじゃないけど文化という点で興味あります。
そして、私一度だけ国技館で観戦したことがあるのです。
まだ朝青竜がいた時代。
升席で観戦するというより、場内の空気を楽しんでいましたが。。
実際の取り組みを見るのはおもしろかったです!!
勝川春英「邸内水入りの図」
まずは肉筆浮世絵から。
浜離宮での上覧相撲に取材しています。
水入りとなり力水を渡されている場面です。
桜が舞うシチュエーションで色彩も淡く、かなり美しい作品。
歌川芳員「勧進大角力取組図」
こちらも肉筆浮世絵。
番付は安政5年11月場所に基づくものですが、この場所は江戸大火で中止となりました。
驚くべきは観客の多さ。
あんなに遠くて見えるのか、と疑問に思います。
透視図法を使い、奥行き感じる作品です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「不知火・大鳴門」
こちらも肉筆浮世絵。
取組の様子が描かれていますが、力強い感じが出ています。
描かれているのは前年に入幕したばかりの不知火と前頭七枚目になったばかりの大鳴門。
注目の若手の取り組みです。
勝川春章「日本一江都大相撲土俵入後正面之図」
東方力士の土俵入りが終わって退場と同時に西方力士の土俵入り。
これも観客がすごいです。
透視図法によって奥行きがあり、奥まで観客ぎっしりです。
土俵がちょっと小さい印象があります。
歌川国貞(三代歌川豊国)「歴代横綱の図」
歴代の横綱が1枚に描かれたもの。
初代と第4~9代の横綱が描かれています。
最上段に初代の明石志賀之助。
彼は寛永年間に江戸で勧進相撲を始めたとされていますが、実在が疑問視されている存在です。
その人物を初代とされたのは明治に入ってから。
第12代横綱の陣幕久五郎によって初代に位置付けられました。
そのため、この絵では綱をつけていないのです。
綱をつけない状態で一番上に描かれているということは、その時代でも横綱ではなくても相撲上の重要人物ととらえられていたんですね。
歌川国貞(三代歌川豊国)「不知火諾右エ門 横綱土俵入之図」
第8代横綱です。
天保11(1840)年に横綱免許を受けました。
左には露払の黒雲龍五郎。右に太刀持ち高根山政右エ門。
柱の赤が目立ちます。
太い黒い輪郭線にはっきりとした色使い。
イラスト的です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「秀ノ山雷五郎 横綱土俵入之図」
第9代横綱。
身長は五尺四寸(約164cm)と歴代最小なんだそう。
周りと比較してもそこまで小さく見えないのはお相撲さんだからでしょうか。
二代歌川国貞「雲龍久吉 横綱土俵入之図」
第10代横綱です。
青々とした髭の剃り跡が目立ちます。
土俵入りの「雲竜型」に名を残した横綱です。
二代歌川国貞「不知火光右エ門 横綱土俵入之図」
第11代横綱。
色白美男子の人気横綱。
土俵入りの際の「不知火型」に名を残す横綱です。
男前でその華麗な土俵入りも江戸中の評判であったとか。
二代歌川国輝「陣幕久五郎土俵入りの図」
第12代横綱。
初代に明石志賀之助を置き、自らを12代目としました。
それが現在の横綱代数に使われています。
江戸最後の横綱でその後は明治維新の動乱に巻き込まれるも実業家として相撲関係の建碑事業に奔走しました。
二代歌川国輝「鬼面山谷五郎 横綱土俵入之図」
第13代横綱。
明治2(1869)年、数え44歳で横綱免許を受けました。
これは現在でも最高齢の記録です。
が、作品の中では老けている様子も見えず、周りの力士と変わらず見えます。
勝川春章「東方 鞍手山弥太夫・出水川林右衛門」
勝川春章は力士の風貌、体格をありのままに表現しようとし、相撲絵というジャンルを確立した存在です。
ここでは2人の力士が描かれています。
大きく力強い様子が伝わってきます。
鞍手山弥太夫のまわしには2頭の馬が描かれていて、ちょっとかわいい。
磯田湖龍斎「釈迦ヶ獄雲右衛門と娘」
巨人力士として明和末から安永初めに人気を集めた力士。
人差し指1本で娘を持ち上げているという何ともすごい情景が描かれています。
背は六尺六寸(約2m)、掌九寸五分(約29cm)、足は壱尺三寸(約40cm)、目方は拾八貫目余(約143kg)とものすごいサイズです。
歌川国安「大空武左衛門」
名前がいいですね。
大きくて強そう。
これは相撲を取っている場面ではなく、普段の様子を描いています。
青いストライプの着物の模様も名前のイメージと合っています。
歌川国安「大空武左エ門」
巨人力士として人気を集めましたが、実際に取組はしていません。
背は七尺五寸(約227cm)、掌壱尺二寸(約36.3cm)、足は一尺三寸五分(約41cm)、重さは三拾五貫目(約131kg)。
こちらもすごい……
描かれているのは23歳のとき、とされていますが、郷里の墓標では32歳だったそうで。。。
歌川国安「綿龍田郎」
前頭筆頭止まりでしたが、美男の力士として人気を博しました。
そう、かっこいい人ならば、幕下でも描かれたのです。
なんだか切ない世の中ですね。笑
歌川国貞(三代歌川豊国)「小柳常吉」
画面いっぱいに描かれ窮屈そうな印象も。
嘉永7(1854)年、ペリーが再来日した際にはアメリカ人水兵3人と同時に戦い、難なく打ち負かしたという逸話も残っている力士です。
歌川国貞(三代歌川豊国)「生月鯨太左エ門」
手形を押す場面が描かれています。
この力士も巨人力士でしで、背は七尺五寸(約227cm)、重さは四十五貫目(約169kg)。
歌川国貞(三代歌川豊国)「生月鯨太左エ門」
さて、上の彼が押した手形です。
横浜美術館で開催された「魅惑のニッポン木版画」でも展示されていました。
その記事で「これ、本当の大きさかなぁ」と書きましたが、本人の背丈のサイズなどから考えても本当の大きさっぽいです……。
歌川国貞(三代歌川豊国)「白実弓肥太右エ門」
こちらも巨人力士。
背は六尺八寸二分(約2m)。
嘉永7年のペリーの再来日の際に米8俵を一度に運び驚かせたそう。
それは日本人でも驚くよ……
歌川国芳「鬼若力之助」
怪童力士として8歳から4年にわたり土俵入り。
後に幕内となりました。
怪童力士は出世しないとの話もあるようですが、見事です。
顔も幼く、全体的に丸いイメージです。
二代歌川国輝「東京 勝ノ浦与一右エ門」
その怪童力士のその後です。
立派になりました……笑
歌川広重「名所江戸百景 両ごく回向院元柳橋」
さて、ここからは相撲にまつわる景色など。
両国の回向院の境内から富士山と隅田川を望んでいます。
縦長の画面で描かれ空の高さ、空間の広さが伝わってきます。
青空がきれいです。
手前には相撲興行中に仮設された相撲櫓。
竹竿の先には晴天を願うため、麻の御幣がついています。
歌川広重「東都名所 両国回向院境内全図」
描かれているのは両国の回向院境内の中に建てられた相撲小屋。
とにかく巨大。
ものすごい大きさです。
近くを歩いている人と比較しても大きい。
ここに何人の人が入るのでしょうか。
歌川国郷「両国大相撲繁栄之図」
相撲興行中の旗がひしめき、米俵が積まれています。
相撲が江戸庶民の楽しみであったことなど、賑わいの伝わってくる作品です。
無款「絵番付」
番付、とは相撲における力士の順位表。
普通は力士の名前でかかれているのですが、これは力士のイラストで描かれています。
上からずらっと力士がぎっしり。
列車ごっこみたいにくっついています。
なんか迫力あります。
二代歌川国貞「相撲表四拾八手の図」
相撲の48の決まり手を簡単な解説とともに図解したもの。
おもしろいです。
ただ、何が何だか分かりません……
歌川春好「柏戸・江戸ヶ崎・谷風」
3人の力士の普段の様子です。
着物を着て歩いています。
一人は五代市川団十郎の似顔絵入りの扇子を持っています。
浮世絵で人気だったのは歌舞伎と相撲が味わえちゃいます。
歌川国輝「東都両国夕景之図」
両国橋で夕涼みをする力士と歌舞伎役者の一行。
豪華です。
が、力士が大きいため、遠近法の感覚がおかしくなりそうです。。。
以上になります。
相撲だけでこれだけの作品、、、というかもっとあるというのがすごい。
江戸時代の熱狂が伝わってくるようでした。
ブログランキングよかったらお願いします