
オーバーツーリズムに困惑するバルセロナ住民方々のデモ映像が流れていました。水鉄砲を観光客に向けて、発射するグループの映像もありました。160万人の住民に対して10倍の1500万人の観光客が訪れているとのこと、民泊の急増で家賃が高騰、さらに一部の観光客が私有地に侵入して写真を撮る、ごみを捨てる、注意すると暴力をふるうという悪質な行動に我慢できずのデモだったようです。最新の観光情報を入手してからお出かけ下さい
8日間のバルセロナ旅から帰ってきました。同一ホテルに六泊して、街や近郊の名所にでかけるというスタイルの旅は初めてでした。ホテルに荷物を置いたまま、まるで、自宅から出かけるような気軽な旅も良いものでした。
写真はバルセロナの通りをゲイ・フラッグを掲げて行進するゲイたちです。

 バルセロナを訪れるなら・・・
バルセロナを訪れるなら・・・5月か6月が最適なシーズン・・・この情報にはまったく間違いありません。訪れた6月23日から29日まで、郊外のモンセラット山へのハイキングで雷とパラパラとした雨に降られた以外、ほぼ快晴の毎日でした。日本の梅雨がウソのようの日和でした。
最高気温は27度、日差しが強く、夏らしい暑さでしたが、湿度が低いせいか、日陰に入ると実に快適、夕方から夜半にかけての散策を楽しむ人で賑わっていました。
 到着した6月23日はサン・ホアン祭りでした
到着した6月23日はサン・ホアン祭りでしたバルセロナの空港に午後10時に到着・・・上空から花火が打ち上げられているのが見えましたが、夏至を祝うサン・ホアン祭りの前夜祭、空港からタクシーで市内のホテルまで、爆竹の音が絶えることがありませんでした。
成田から17時間の旅でしたが、ホテルに荷物を置くと、早速、ランブラス通りへ・・・夏の到来を祝う人々で、ごった返していました。子ども連れや乳母車を押して散策する若い夫婦もおり、地元の人と夏至の夜を共にしました。バルの一軒に立ち寄り、カーニャ(生ビール)で乾杯、バルセロナ到着を祝いました。
 バルセロナは安全な街でした
バルセロナは安全な街でした出かける前に、スペイン失業率17%の報道や外務省の海外旅行安全情報などで、治安の悪化が伝えられ、かなり緊張してのバルセロナ散策でしたが、安全に、楽しく、バルセロナの旧市街やランブラス通りの散策を楽しみました。
確かに、路上に座る多くの物乞いを目にして、バラの花を売りつけようと近づく浮浪者にも出会いましたが、アジア系の地元民も多く、日本人観光客という隙を見せなければ、なんら問題はないと感じま

 ホテル:
ホテル:バルセロナの中心地、カタルーニャ広場近くのホテルの三ツ星ホテルを予約したのは正解でした。旧市街地にもランブラス通り、グラシア通りにも徒歩圏内・・・この一角にはホテルが軒を連ねていますが、いずれも19世紀にバルセロナが繊維産業で最も賑わった時期に建てられた重厚な石造りのビルが軒を連ね、内部を改装してホテルとして営業しています。そのため、部屋やレストラン、ロビーは狭く、遮音性もいまいちですが、エレベーターを設置、バスタブもあり、快適に六日間を過ごすことができました。ツインで一泊12,000円、わが国のビジネスホテル並の料金設定でした。
 タクシー:
タクシー:バルセロナは地下鉄網が完備していますが、時間的なロスと、スリなどの被害を避けるため、市内の移動はタクシーを利用しました。流しのタクシーが手軽につかまるのではないかと思っていましたが、これが意外に難しく、ホテル近くのカタルーニャ広場のタクシー乗り場から乗りました。
料金は5ユーロから7ユーロ、一番遠かった北にあるグエル公園からカタルーニャ広場までが12ユーロ、値段はメーターに表示され、チップはお釣りが少しならそれを・・・払わなくても問題はありません。空港から市内までは30ユーロ少々、スーツケース二つの料金が、メーターを止めた最後に加算されて表示されます。
渋滞時にメーターがドンドン上がるのは日本と同じです。乗り込むときに「Hola!(オラ!)」と挨拶するのが慣例、行き先の発音に自信がないときは、紙に書いた行き先を示し、「Por favor (ポルファボール お願いします!)」と言えばOKです。
 鉄道:
鉄道:カタルーニャ鉄道(バルセロナ公営)とRENFE(レンフェ・スペイン国鉄)に乗りました。
モンセラットに行くにはスペイン広場から出ているカタルーニャ鉄道で1時間、ダリの美術館訪問にはサンツ駅からフィゲラスまでRENFEで2時間の道のりです。いずれの線路も郊外に出るまで地下を走ります。
初めての体験となる切符の買い方ですが、カタルーニャ鉄道はスペイン語か英語の切り替えができる自動販売機で、RENFEでは窓口で購入します。割引往復切符(ida y vuelta イダ・イ・ブエルタ)であること、行き先を確認することで問題なく購入できます。
(後日、モンセラットとフィゲラス訪問記で詳しく報告します)
 テレビ報道:
テレビ報道:当然のことながら、日本の情報はまったく入ってきません。ただ、到着した翌日の6月24日には中村俊輔選手がバルセロナ・エスパニョールへの移籍を告げる報道で、スコットランド・セルテイックで活躍する姿を流していました。
ところで、スペイン代表と南アフリカ代表の対戦の中継をテレビ観戦しました。0-1とずっとリードされていましたが、後半戦で2-1と逆転、その直後に追いつかれ、終了間際に得点し逃げ切るという白熱したゲームでした。両チームの体格のよさ、玉回しの的確さ、攻撃の切り替えの早さ、圧倒的な攻撃力を見ていると、日本チームの4位入賞は難しいのではないか・・・と心配になりました。
ところでバルセロナ滞在中にマイケル・ジャクソンの訃報・・・テレビは朝、昼、夜と特集番組の映像ばかりとなりました。
 食事:
食事:ホテルでは取らず、街のバールとレストランを渡り歩きました。

朝食には、細長いパンの両端からスペイン特産イベリコ豚の生ハムがはみ出しているボリューム満点のボガデイ―リョ(ジョ)が気に入りました。しかしこのようなヘビーな朝食を食べているのは私たちだけ・・・スペイン人は、コーヒーとクロワッサンなどの軽い朝食でした。
もっとも彼らは11時頃にバルでもう一度食事、昼食として2時ごろにしっかりと食べ、夜は遅くまでバルで飲み食いをするという日本人とは異なる食生活のようです。
日本人に人気のパエリアには注意が必要です。値段が安いパエリアは出来合いのものを暖めるだけ、お米の味にシビアな日本人には食べられたものではありません。
やはり、専用の鉄鍋で焼き上げた本来のパエリアをレストランでいただくのがよいでしょう。
 お土産:
お土産:カタルーニャ広場に面した大手デパートEl Corte Inglesで済ませました。スペインのカラフルな色のネクタイとシャツを探しました。シャツは持参したクビ周りサイズ表を店員に見せると探し出してくれました。地下に、食料品を販売する区画があり、真空パックの生ハム、修道院で作られたお菓子などを購入しました。
ワイン類は、ロンドン経由でしたので、機内持込規制で購入できません。その代わり、ヒースロウ空港の免税店で、スコッチウイスキーを・・・二度訪れたことがあるスコットランド・スカイ島の銘酒TALISKERを見つけ、懐かしさから購入しました。
 費用:
費用:航空機、ホテル、食事、現地交通費、土産代を含めて、52万円・・・一人26万円の旅でした。
 バルセロナはスペインではない!
バルセロナはスペインではない!・・・と地元の方がよく言うとのことですが、独自の言語、文化、歴史を持ち、モデルニスモ建築の世界遺産、旧市街の中世からの町並み・・・たしかにスペインというより隣の国フランスに近い雰囲気を持っています。
地名表示、レストランのメニュー、看板など、まずカタラン語、続いてスペイン語で書かれているという具合で、地元の方々の自国語への自負心が伝わってきます。
世界遺産・カタルーニャ音楽堂のトイレに掲示されていたカタラン語、スペイン語、英語の注意書きを紹介しておきましょう。
{Si us plau, no disposition cap objecte als urinaris i WC. Gracies}
{Por favor, no espositen ningun object en los uninarios y WC. Gracias}
{Please don’t throw any object in the urinaries and WC. Thank you}














 大沼から小沼までは車で5分。付近を散策
大沼から小沼までは車で5分。付近を散策 本ブログ「
本ブログ「 到着 東京 119キロ
到着 東京 119キロ




 侮れません、筑波山!標高差621m、しかも直登です!
侮れません、筑波山!標高差621m、しかも直登です! 出発:筑波神社
出発:筑波神社
 昼なお暗い杉やヒノキの大木の中を登ります。道幅は十分な広さがありますが、徐々に勾配がきつくなり、散策気分は吹き飛んでしまいます。登山道は杉やヒノキの木々の中を進むため、到着地点までまったく眺望はまったくありません。整然と立ち並ぶ杉やヒノキの大木に筑波神社の神域に入り込んでいることが実感できます。
昼なお暗い杉やヒノキの大木の中を登ります。道幅は十分な広さがありますが、徐々に勾配がきつくなり、散策気分は吹き飛んでしまいます。登山道は杉やヒノキの木々の中を進むため、到着地点までまったく眺望はまったくありません。整然と立ち並ぶ杉やヒノキの大木に筑波神社の神域に入り込んでいることが実感できます。 唯一ホッとできるのはケーブルカーの車両が交差する中間点の空き地です。休憩しながらケーブルカーの写真を撮る絶好のポイントです。ケーブルカーに乗った家族に手を振りながら迎える方もいます。
唯一ホッとできるのはケーブルカーの車両が交差する中間点の空き地です。休憩しながらケーブルカーの写真を撮る絶好のポイントです。ケーブルカーに乗った家族に手を振りながら迎える方もいます。
 またまた、頂上鞍部まで坂の連続です。ここら辺りから後ろを歩くハイカーの激しい息使いに追われるように登ることになります。相変わらず杉やヒノキの中で見晴らしは利きません。
またまた、頂上鞍部まで坂の連続です。ここら辺りから後ろを歩くハイカーの激しい息使いに追われるように登ることになります。相変わらず杉やヒノキの中で見晴らしは利きません。 水場に出ます。百人一首にある “つくばねの峰より落つるみなの川こひぞつもりて淵となりぬる”の男女川(ミナノガワ)の源頭です。周囲はヒノキの大木が何本もあり、万葉集や古今和歌集にも詠われた歴史の山にいることが実感できます。
水場に出ます。百人一首にある “つくばねの峰より落つるみなの川こひぞつもりて淵となりぬる”の男女川(ミナノガワ)の源頭です。周囲はヒノキの大木が何本もあり、万葉集や古今和歌集にも詠われた歴史の山にいることが実感できます。
 ようやく、男体山と女体山の鞍部、御幸ケ原に到着です。広場になっておりケーブルカーの駅と数軒の茶店があり、公衆トイレもあります。見晴らしは北側の展望が利くだけですが、多くのハイカーがここで昼食を取っています。西に男体山への登り口があります。
ようやく、男体山と女体山の鞍部、御幸ケ原に到着です。広場になっておりケーブルカーの駅と数軒の茶店があり、公衆トイレもあります。見晴らしは北側の展望が利くだけですが、多くのハイカーがここで昼食を取っています。西に男体山への登り口があります。 ここから東に向かいます。女体山までは10分程度の緩やかな登り坂で、植生がガラリと替わり、ブナの木が目立つ明るい登山路を散策気分で歩けます。この辺りは遠足の小学生たちがお弁当を楽しむ姿をよく見かけます。
ここから東に向かいます。女体山までは10分程度の緩やかな登り坂で、植生がガラリと替わり、ブナの木が目立つ明るい登山路を散策気分で歩けます。この辺りは遠足の小学生たちがお弁当を楽しむ姿をよく見かけます。
 祠のある女体山山頂は一等三角点のある狭い岩場で、巨岩がせり出すように頂上を造っています。ここからの展望は筑波山のハイライトです。何度見ても見飽きない大パノラマですが、滑落しないよう十分気をつけます。
祠のある女体山山頂は一等三角点のある狭い岩場で、巨岩がせり出すように頂上を造っています。ここからの展望は筑波山のハイライトです。何度見ても見飽きない大パノラマですが、滑落しないよう十分気をつけます。 女体山からの白雲橋コースへと下ります。
女体山からの白雲橋コースへと下ります。 ここからは古来から修行僧が通った道・・・北斗岩、裏面大黒、弁慶七戻り、出船入船、母の胎内くぐりと名づけられた巨岩怪石が次々と表れます。
ここからは古来から修行僧が通った道・・・北斗岩、裏面大黒、弁慶七戻り、出船入船、母の胎内くぐりと名づけられた巨岩怪石が次々と表れます。 270年の歴史があった弁慶小屋、惜しまれつつ2006年に廃業しました。建物の基礎が俤を留めています。ここを東に曲がるとつくしが丘へ、直進すると筑波神社です。ここまでで白雲橋コースの4分の1ですが、ホッとする場所です。
270年の歴史があった弁慶小屋、惜しまれつつ2006年に廃業しました。建物の基礎が俤を留めています。ここを東に曲がるとつくしが丘へ、直進すると筑波神社です。ここまでで白雲橋コースの4分の1ですが、ホッとする場所です。 到着:筑波神社
到着:筑波神社 家族連れ筑波山ハイキング:
家族連れ筑波山ハイキング: 小さな子ども連れなら・・・
小さな子ども連れなら・・・ 小学生以上なら・・・
小学生以上なら・・・


 尾瀬ヶ原散策 6時間 「尾瀬案内人web」をご覧下さい
尾瀬ヶ原散策 6時間 「尾瀬案内人web」をご覧下さい
 「尾瀬案内人web」のこと
「尾瀬案内人web」のこと

 6月23日(火)成田(NH201)11:35→16:00ロンドン(IB4189) 19:10 → 22:10バルセロナ
6月23日(火)成田(NH201)11:35→16:00ロンドン(IB4189) 19:10 → 22:10バルセロナ


 カタルーニャ観光
カタルーニャ観光 食道楽の私にとって最も参考になったのは、レストラン、カフェやバルの情報です。
食道楽の私にとって最も参考になったのは、レストラン、カフェやバルの情報です。 今回のバルセロナ旅行でぜひ食事をしたいと考えているレストランは次の通りです。
今回のバルセロナ旅行でぜひ食事をしたいと考えているレストランは次の通りです。 航空券の購入
航空券の購入









 大森代官所跡で資料館を見学、大森町の町並み地区を散策、銀山地区を経て龍源寺間歩を訪れ、再び代官所跡まで戻りましたが、3時間かかりました。以前は龍源寺間歩までバスが運行していましたが、環境汚染を考えてか中止、中間地点の観光バス乗降所からでも、年配者にはかなりキツイ徒歩となります。
大森代官所跡で資料館を見学、大森町の町並み地区を散策、銀山地区を経て龍源寺間歩を訪れ、再び代官所跡まで戻りましたが、3時間かかりました。以前は龍源寺間歩までバスが運行していましたが、環境汚染を考えてか中止、中間地点の観光バス乗降所からでも、年配者にはかなりキツイ徒歩となります。






 午前8時31分 大田市駅発(JR山陰線) 230円
午前8時31分 大田市駅発(JR山陰線) 230円









 東京駅はまだできていませんでした。
東京駅はまだできていませんでした。














 国木田独歩の碑を訪れました
国木田独歩の碑を訪れました 田中穂積は長州藩の少年鼓手でした
田中穂積は長州藩の少年鼓手でした 「美しき天然」のメロデイが今でも歌われている国があります
「美しき天然」のメロデイが今でも歌われている国があります



 昭和村は自然豊かな村です
昭和村は自然豊かな村です
 昭和村はからむし織の里です
昭和村はからむし織の里です 一昔前まで土葬の風習が残っていました
一昔前まで土葬の風習が残っていました NHKのドキュメンタリーでは、村中の方が葬儀にかかわったことが紹介されていました。死装束を縫う人、湯潅の準備のため湯を沸かす人、墓を掘る人、棺おけを運ぶ人、食事の支度をする人、記録をつける人・・・120名の村人が葬儀にかかわったとありました。印象的だったのは、村を離れ千葉県に転居された方も葬儀に加わっていることでした。助け合いの結いの制度が綿々と村の絆を結んできた証です。
NHKのドキュメンタリーでは、村中の方が葬儀にかかわったことが紹介されていました。死装束を縫う人、湯潅の準備のため湯を沸かす人、墓を掘る人、棺おけを運ぶ人、食事の支度をする人、記録をつける人・・・120名の村人が葬儀にかかわったとありました。印象的だったのは、村を離れ千葉県に転居された方も葬儀に加わっていることでした。助け合いの結いの制度が綿々と村の絆を結んできた証です。 会津戦争で最後の激戦地となりました
会津戦争で最後の激戦地となりました 昭和村から沼田街道を辿りました
昭和村から沼田街道を辿りました 参考までに:
参考までに:

 当時の工事関係者が家族ぐるみで現場に来ていること、社宅が出来るまでは、付近の民家に家族で間借りであったことが、Nさんの記憶と合致します。また、柳津からNさんの父君が仙台の日本発送電株式会社に勤務されていますから、温泉関係の仕事が終わり、発電所の関連工事に移られたのでしょう。
当時の工事関係者が家族ぐるみで現場に来ていること、社宅が出来るまでは、付近の民家に家族で間借りであったことが、Nさんの記憶と合致します。また、柳津からNさんの父君が仙台の日本発送電株式会社に勤務されていますから、温泉関係の仕事が終わり、発電所の関連工事に移られたのでしょう。


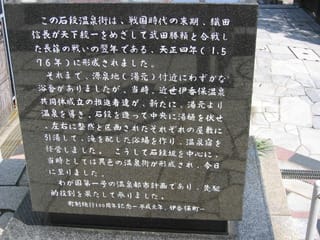
 食べる:
食べる: 


