マニラの旅のブログが終わりましたので、
名所めぐり、グルメめぐりに戻ります。
築地駅に行きました。

そのすぐそばにあるのが、
築地本願寺(つきじほんがんじ)。

浄土真宗本願寺派の寺院で、
京都市にある西本願寺の直轄寺院。

江戸時代の1617年に、
西本願寺の別院として
浅草御門南の横山町に建立。
しかし明暦の大火(振袖火事)により本堂を焼失。
江戸幕府による区画整理のため
旧地への再建が許されず、
その代替地として八丁堀沖の海上が下付されました。
そこで佃島の門徒が中心となり、
本堂再建のために
海を埋め立てて土地を築き、
(この埋め立て工事が地名築地の由来)
1679年に再建。
1923年9月1日の関東大震災では、
地震による倒壊は免れましたが、
すぐ後に起こった火災により再び伽藍を焼失。

関東大震災で失われた旧本堂の復旧事業として
現在の本堂が1934年に竣工。
設計者は伊東忠太。
古代インド様式をモチーフとしており、
当時の宗教施設としては珍しい鉄筋コンクリート造で、
大理石彫刻がふんだんに用いられています。
重要文化財に指定されています。

浄土真宗本願寺派の新体制移行(2012年4月1日付)に伴い、
正式名が従前の「本願寺築地別院」 から
「築地本願寺」 になりました。
著名な人物の葬儀が宗派を問わず多く執り行われています。
本堂。

本尊を安置する中央部と北翼部(向かって左)、

南翼部(同右)からなります。


左右には、狛犬ではなく、獅子像。

後ろから。

大階段を上がると「広間」と称する横長の前室を経て外陣があり、
その奥が本尊を安置する内陣。



本尊は聖徳太子手彫と伝承される阿弥陀如来立像。

右側の間。


左側の間。

内側から外を見ると。

北翼部は1階に説教所と小会議室(現・聞法ホールと控室)、
2 階に議場(現・講堂)などが。

説話会場。


南翼部は1 階に重役室、食堂等(現・寺務所等)があり、
2 階はおもに事務室(現・礼拝堂等)にあてられています。


南の伝道会館。




インド、西洋、イスラム、日本などの
異なるモチーフを融合させた独自の様式を示すとともに、
礼拝、説教、会議、事務など、
仏教寺院のさまざまな機能を1棟で果たせるような
合理的な設計になっており、
伊東忠太の代表作の一つです。

これは、

合同墓所。



南門からの光景。











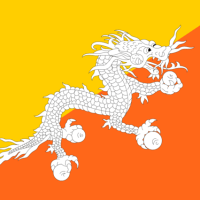









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます