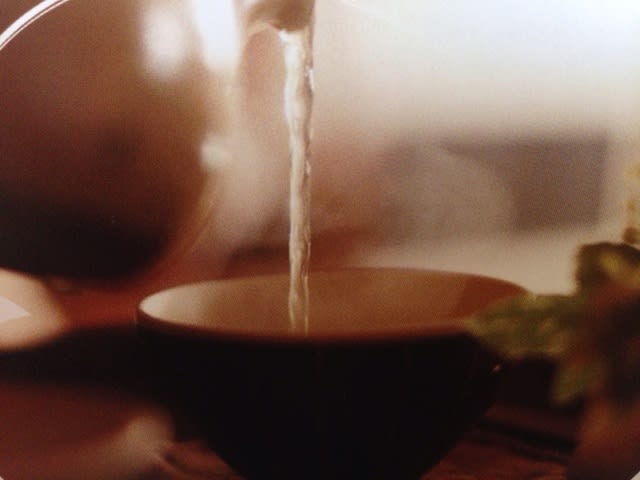杭州西湖 曲院風荷の茶館にて(2014.4月写真)
杭州(こうしゅう)と並び、昔から茶館文化が盛んだ街は、四川省(しせん)の成都(せいと)。

歴史上、西漢の時代(世紀前206年-9年)に、巴蜀(はしょく)茶業は、すでに盛んでいた。巴蜀とは、四川省の旧称。
その時代に残された面白い文献がある。
地主の王氏と男性の召使いの間に、結ばれた契約書『僮約(どうやく)』の記載が残されていた。
召使いは、契約書に書かれる以外のことは、一切やらないと言い出す。仕方なく、詩人でもある地主の王氏は、召使いのなすべき家事を細かく文書にした。
中に、このような項目が書かれている。
烹茶尽具
武陽買茶
この八文字から、当時豪族の家庭では、すでにお茶を調理する慣習があり、お茶を飲むための茶道具も、すでに存在したと言われている。
言葉にある武陽は、市場の名と推測され、その時代に、すでにビジネスとしてのお茶市場ができたことの証明になる。
茶聖と言われる陸羽の『茶経』は、それより800年後のことであるが、『僮約』は、お茶の飲用と購買を触れた、最古の文献資料として知られている。
茶杯の中の美味しさから始まるお茶の世界、気がつけば、古文献の面白さも教えてくれたきっかけになった。
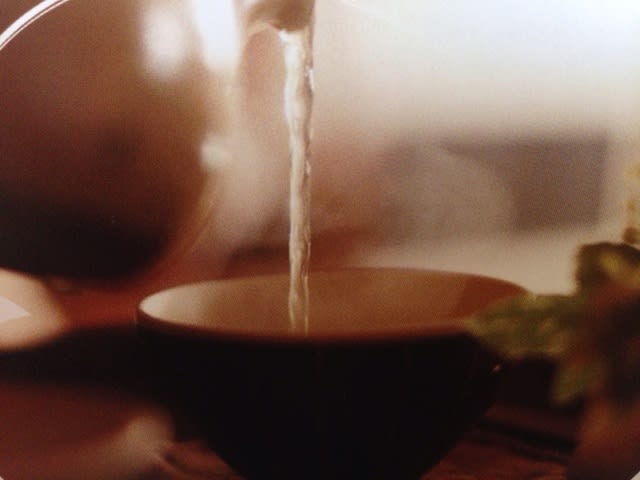
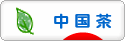 にほんブログ村
にほんブログ村
注)
巴蜀(ハショク)-「巴ba1」は現在の重慶を指す。「蜀shu3」は現在の成都を指す。四川省の二大都市を指すことで、「巴蜀」は四川省の代名詞になる。
僮約(ドウヤク)-「約yue1」は「契約」の略。「僮tong2」とは、未成年の召使いのこと。
未成年の若さであるゆえ、家主さんに向かって、契約書以外のことを一切やらないと言えたのではないでしょうか(笑)