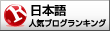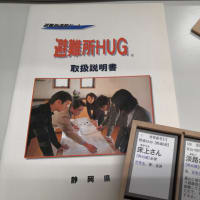非常勤でお世話になっている静岡文化芸術大学で、先日、「第13回多文化子ども教育フォーラム 日本で暮らすムスリムの子どもたち」が開催されました。
先約があって、残念なことに、うかがうことができませんでしたが、新聞記事や大学のHPで様子を知ることができました。
いい会だったんだなあと思っていたのもつかの間、
ネット上の匿名掲示板に、批判にあふれた投稿があり、読んでいて、なんといえばいいかな、悲しいというか、情けないというか、恥ずかしいというかそんな思いが錯そうしました。
基本的には、「郷に入らば郷に従え」という考え方です。
おそらく、そこには、自分がマジョリティであることにすら気づかない人たちが多いのではないかと思いました。
日本で暮らしている日本国籍の人間は、自分がマジョリティであることから得られている利益に気がついていないわけで、気がついていないから、マイノリティに対して当然のようにマジョリティと同じようにふるまうことを求めているだけだと思います。
私も、ちょっと人より体重が重いということで、体重的に見るとマイノリティに入っていて、
折り畳み自転車を買うとか、ちょっとデザインが凝っている椅子なんかを品定めするときに、耐荷重〇〇キログラムと書かれていると、
「ああ、買えないんだ」って思っちゃう。
服を買うときも、ウェストサイズを見て、セールになっているものには該当するものがなくて、お店の人に尋ねると、奥から定価の服が出てくるということもざら。
でも、だからといって、いわゆる標準体重の標準体型の人たちは、私を含む、ちょっと体の大きな人のために、何かをする可能性があるかというと、極めて低いわけですよ。
だから、時々、体の大きな人が起業して、自分のサイズに合う服を廉価に販売、なんてことが出てくるわけ。
体の重さや大きさは、自分の努力でなんとでもなるから、いわゆる「自己責任」という言葉も当てはまるかもしれません。
でも、ホルモンバランスが崩れて、とか、病気の治療の副作用で、私と同等の体格になる人もいます。
理由はどうあれ、マイノリティである人たちが普段どれだけ不便な思いをしているか、私たちは全く意識できていないような気がします。
私の勤めている大学の、私の研究室の入っている建物にはエレベーターがなく、スキーシーズンになると、友達に支えられて階段を上がる学生さんの姿を見ることがあります。
ほかの建物にはエレベーターがあるので、その学生さんは一人で移動できるわけですよ。
体にハンディを持つ人を含め、マイノリティの方々が暮らしやすい社会、生活しやすいシステムというのは、マジョリティにとっても快適な社会であり、システムであるはず。
だからこそ、若い時に、自分がマイノリティになるということを経験してほしいと思います。
留学もその一つの経験です。
ムスリムの方が学校生活の中で、給食であったり、お祈りであったり、そういったところに配慮を求めていることを、一方的に批判することなく、どうすればいいだろうか、と考えることが、豊かな社会につながることだと思います。
給食におけるアレルギー対応食だって、「個人のわがまま」という対応から「弁当持参」、そして、「アレルギー対応食の提供」へと進んできたのですから、今度はこの問題を社会全体で考えていけばいいだけのこと。
きっと乗り越えられると思いますよ。この国も社会も、それだけの能力も寛容性もあるんだから。
先約があって、残念なことに、うかがうことができませんでしたが、新聞記事や大学のHPで様子を知ることができました。
いい会だったんだなあと思っていたのもつかの間、
ネット上の匿名掲示板に、批判にあふれた投稿があり、読んでいて、なんといえばいいかな、悲しいというか、情けないというか、恥ずかしいというかそんな思いが錯そうしました。
基本的には、「郷に入らば郷に従え」という考え方です。
おそらく、そこには、自分がマジョリティであることにすら気づかない人たちが多いのではないかと思いました。
日本で暮らしている日本国籍の人間は、自分がマジョリティであることから得られている利益に気がついていないわけで、気がついていないから、マイノリティに対して当然のようにマジョリティと同じようにふるまうことを求めているだけだと思います。
私も、ちょっと人より体重が重いということで、体重的に見るとマイノリティに入っていて、
折り畳み自転車を買うとか、ちょっとデザインが凝っている椅子なんかを品定めするときに、耐荷重〇〇キログラムと書かれていると、
「ああ、買えないんだ」って思っちゃう。
服を買うときも、ウェストサイズを見て、セールになっているものには該当するものがなくて、お店の人に尋ねると、奥から定価の服が出てくるということもざら。
でも、だからといって、いわゆる標準体重の標準体型の人たちは、私を含む、ちょっと体の大きな人のために、何かをする可能性があるかというと、極めて低いわけですよ。
だから、時々、体の大きな人が起業して、自分のサイズに合う服を廉価に販売、なんてことが出てくるわけ。
体の重さや大きさは、自分の努力でなんとでもなるから、いわゆる「自己責任」という言葉も当てはまるかもしれません。
でも、ホルモンバランスが崩れて、とか、病気の治療の副作用で、私と同等の体格になる人もいます。
理由はどうあれ、マイノリティである人たちが普段どれだけ不便な思いをしているか、私たちは全く意識できていないような気がします。
私の勤めている大学の、私の研究室の入っている建物にはエレベーターがなく、スキーシーズンになると、友達に支えられて階段を上がる学生さんの姿を見ることがあります。
ほかの建物にはエレベーターがあるので、その学生さんは一人で移動できるわけですよ。
体にハンディを持つ人を含め、マイノリティの方々が暮らしやすい社会、生活しやすいシステムというのは、マジョリティにとっても快適な社会であり、システムであるはず。
だからこそ、若い時に、自分がマイノリティになるということを経験してほしいと思います。
留学もその一つの経験です。
ムスリムの方が学校生活の中で、給食であったり、お祈りであったり、そういったところに配慮を求めていることを、一方的に批判することなく、どうすればいいだろうか、と考えることが、豊かな社会につながることだと思います。
給食におけるアレルギー対応食だって、「個人のわがまま」という対応から「弁当持参」、そして、「アレルギー対応食の提供」へと進んできたのですから、今度はこの問題を社会全体で考えていけばいいだけのこと。
きっと乗り越えられると思いますよ。この国も社会も、それだけの能力も寛容性もあるんだから。