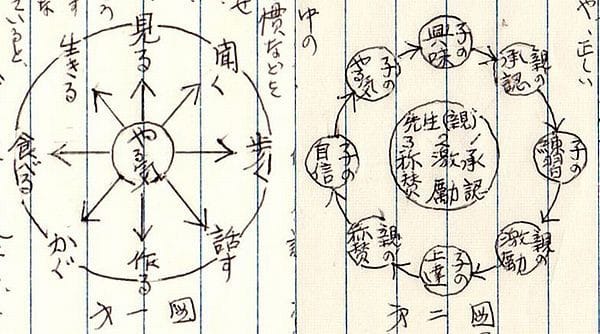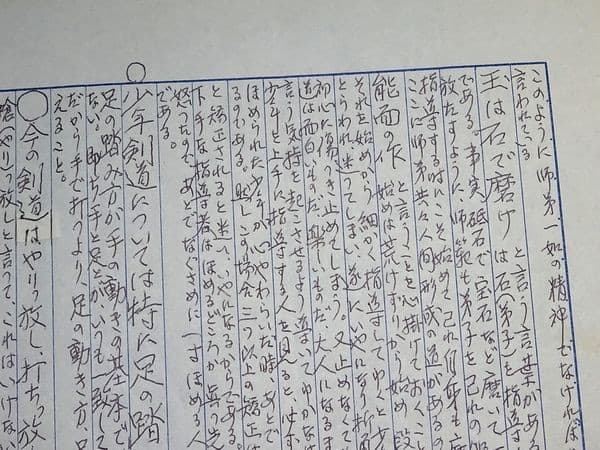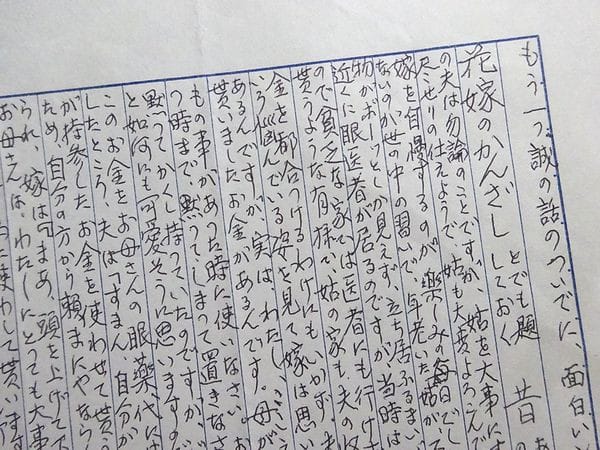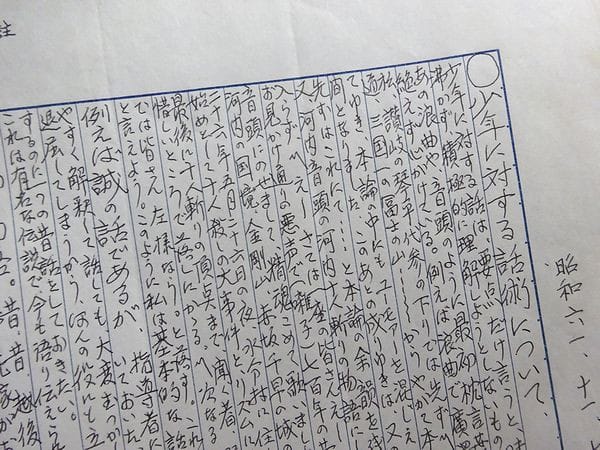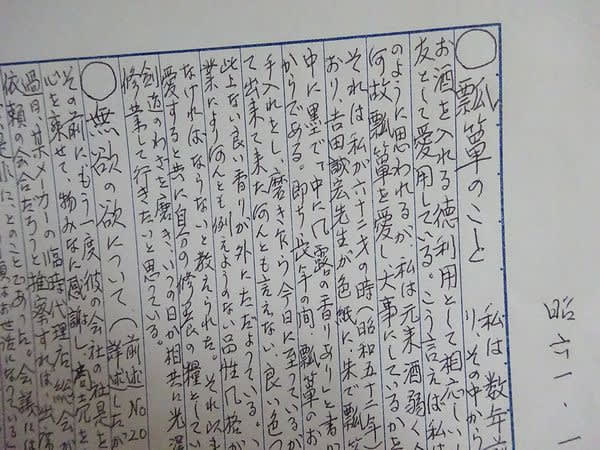この境地まで導いてくれた愛刀をとって、なで、さすり、ほほずりして、
三拝九拝している名人の姿が目に見えるように髣髴(ほうふつ)たるものがある。
一切が名刀のお力、名刀の導き、名刀のおかげで、
自分の力でこの境地が開けたのではないと、まことに謙虚な気持で涙を流してよろこび、
名刀と苦楽を共にして来た生涯をふりかえって楽しんでいる様を想像してみるとき、
私はこの所を涙なくしては書き得なかった。
斯様(かよう)に先生は極めて謙虚な気持ちで、名刀の力を得なかったならば
「剱の心」を証得することは出来なかったであろうと申しているのである。
誠に名刀こそ剱人の本心を直指して、本心の殿堂にご案内して下さって、
剣道至極の好境に入らしむる案内者である。
三、名刀製作の動機
法華経に「唯仏と仏とのみ能く究尽す」とあるように、
名人はよく名人を覚知し、名作は名人の手によって打成される。
曲木も名人の手になればたちまちその真価を発揮する。
吉田誠宏先生を今名人ということは尚早かも知れないが、
少なくとも名人位の境地とはこうしたものであるという事だけは既に三十代にして知り、
その境地を開拓しようと、あらゆる角度から研究に研究を重ね、或は一代の禅僧、
南天老に師事し、剣禅一如の妙所如何にと捨身の修行に徹する等、
或は京都武徳会本部の大会に於ける玉座問題では
剣道第一義諦(だいいちぎたい)のものを打成して、
剣道界に新生命の楔を打込み、飄然として剣を捨て、
拓生の道に入り、医師に見離されたる多くの肺病患者を癒やし、
活人剣の妙境を実際生活に於いて自得現成した。
或は又、一億玉砕のあの大戦の大詰となるや、全国の武道家に激をとばして、
中村半之助将軍を隊長として振武隊を組織し、橿原神宮の大広間に於いて
「我々日本の武道家は身命を大君に捧げ奉り護国の鬼と化することを
大神様の御魂にお誓い申す」と武徳の本領を発揮し、
以って護国の鬼たらん事を期して国難に当るなど・・・・・
或は又、敗戦直後のあの米穀の遅配欠配が続き将に餓死寸前の際に、
日下村農業倉庫に在った麦百二十五俵を非農家二千六百四人に対して
先生が身をもって配給し、村民の急場を救ったため、食糧統制違反によって告発せられ、
二年有余に渡って法廷で戦い、全く自己を捨てきって非農家を救う等、
事にのぞんで変に応じて道を行ずる剣の妙所を如実に生きぬいた人と言うべきであろう。
或は又、敗戦に逢い、国民騒然として国家を忘れ、民族を忘れ、
ただ自己一身の利害と安泰をはかる世情を見ては坐視するあたわずして
日本再建の道は剣道を復興せしめるにあり、
国民の生活の中に武道が入ってこなければ我が民族は亡ぶより外、仕方がない、
日本をして日本本来の日本に再興せしめるために私財を投げ出して武徳会の再興を企図し、
ほとんど成就するかに見えたが、時期尚早のためか、一部不明の人達の反対にあい、
まことに天、組みせず、雄国空しく失敗に終ったのである。
かくの如く先生の今日までの生涯は剣道第一義諦に、
こと志と違い成就し得なかったのである。
失敗に終ったとは言え、常人のよく企図しえざる事を企図し、
凡人のなし不得ところをなしきたったところのものはなんであろうか。
これは地位も、名誉も、財産も何もかもいらん。
ただ国家の安泰と民族の繁栄とを希求し、全自己をあげて、
一切を剣道のために打込んで、剣道の第一義諦より湧出せる透徹(とうてつ)した
心境と大義に生き抜かんとする情熱である。(以下続く)