近年の国際関係論における戦争の研究では、個人レベルの心理特性にその原因を求める分析が注目されています。その代表的な学者の1人が、ドミニク・ジョンソン氏(オックスフォード大学)です。かれは社会科学と自然科学の両方に精通している数少ない研究者の1人であり、オックスフォード大学で進化生物学の博士号を取得したのち、スイスのジュネーブ大学で政治学の博士号を授与されています。こうした学問的背景を持つジョンソン氏は、戦争原因を探求するにあたり、進化生物学や心理学の知見をふんだんに取り込んでいます。ここで取り上げる、かれの主著『自信過剰と戦争ー自己肯定の錯覚による混乱と栄光―』(ハーバード大学出版局、2004年)は、文字通り、学際的なものです。学問は他の学問体系から知識を「輸入」することにより、画期的な成果を生むといわれます。ジョンソン氏は、国際関係論に生物学(そして心理学)を導入することにより、戦争研究に新たな角度から光を当てただけでなく、斬新な仮説や理論を生み出しています。その1つが、政策決定者の「自信過剰(overconfidence)」と戦争に関する因果関係を立証しようとした上記の研究書です。
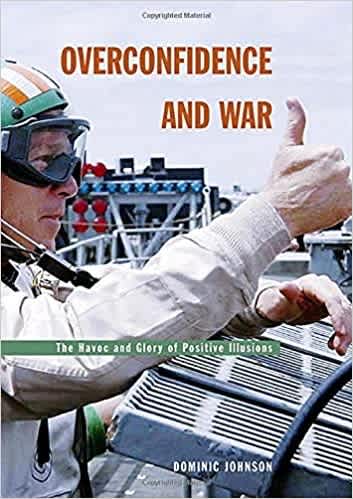
『自信過剰と戦争』は、今では国際関係論でなじみ深くなった「戦争のパズル」から議論を始めます。合理的選択のバーゲニング理論によれば、戦争は国家の指導者が、本当に「合理的」であれば起こらないはずです。なぜならば、双方の国家は相対的なパワーを反映した取引を成立させることにより、戦争のコストやリスクを避けられるからです。言い換えれば、当事国は戦争のコストを支払わずリスクも冒すことなく、戦争をした時と同じ結果をバーゲニングで得られるはずです。にもかかわらず、戦争が起こるのは、当事国のどちらか、もしくは両方が、自らの相対的パワーと戦勝の確率を実際より高く見積もっているからに他なりません。こうした「誤算」や「誤認」をもたらす最大の源泉の1つが、かれによれば、国家の指導者の自信過剰ということです。こうした自信過剰と戦争との因果理論は、ジェフリー・ブレイニー氏が戦争の原因を「楽観主義(optimism)」に求めた古典的なロジックをアップデートしたものだといえるでしょう(Geoffrey Blainey, The Causes of War, 3rd. ed., Free Press, 1988, pp. 35-56)。
ジョンソン氏によれば、人間の心理の基底には、自己肯定の錯覚(positive illusion)に導かれる自信過剰があります。こうした心理的バイアスは、人間が進化の過程で得たものであり、現在でも人々に広く認められるものだと、かれは主張しています。自然選択(natural selection)の長期的過程において、自己肯定の錯覚という心理的属性を持った人間が生き残り、繁殖して今日に至ったのです。この心理特性を持つ「楽観的な」人間は、自分の行動や将来展望を悲観視してあきらめてしまう人より、目標を達成できる見込みが高いと考えられます。自分に自信を持つ兵士や司令官、政治家が評価される所以です。
自信過剰は人間が環境に適応する際、有利に働いた一方で、残念なことに、人々の「合理的計算」をゆがめることになります。それが戦争の意思決定に働くと、時には破滅的な結末をもたらします。国家の政策決定者は、事態を楽観視する心理的バイアスに縛られてしまうと、戦争で勝利したり、戦争を簡単に終わらせられる蓋然性を過大評価してしまいます。その結果、交渉による紛争の解決より戦争がしばしば選好されることになります。すなわち、国家の指導者がもつ自己肯定の錯覚や自信過剰は、戦争の可能性を高めてしまうのです。
『自信過剰と戦争』が提供した行動論的な戦争原因の研究は、これまでややもすれば見過ごされがちだった、国際関係論における個人レベルの分析を再考することになりました。古典的な政治学では、戦争を引き起こす権力欲(animus dominandi)を備えた「人間本性」は固定化されたものだと論じられることがありました。人間本性は変わらないと。その一方で、戦争は起こったり起こらなかったりします。前者が一定で後者が変化するのであれば、両者に共変は認められないため、戦争は人間が引き起こすという直感に反して、それらは関係ないと結論づけらてしまいます。しかしながら、こうした通念は、ジョンソン氏によれば間違いであり、個人が抱く自己肯定の錯覚が高くなれば、人は自信過剰になるため、それだけ戦争を選択しやすくなるのです。人間の「本性」を「心理的バイアス」に置き換えるれば、個人レベルにおいて戦争の発生を説明できるようになるということです。そして、かれは、自信過剰と戦争の因果理論を構築します。その際、自己肯定の錯覚というバイアスが強まったり弱まったりする、理論の先行条件を特定しています。それらが「政治体制のタイプ」と「議論の開放性」です。一般的に、自由民主主義国では、政治指導者は政策を立案する過程で、さまざまな情報や批判的意見にさらされるために、自信過剰の心理バイアスが修正されやすくなります。ただし、民主体制下でも、政治的意思が閉ざされた環境で決定される場合、自信過剰な判断は是正されにくくなり、指導者は愚行に走りかねません。
ジョンソン氏は、上記の仮説を第一次世界大戦におけるドイツの戦争指導者の意思決定、ミュンヘン危機におけるヒトラーを取り巻く政治的状況、キューバ危機における米ソの対応、ヴェトナム戦争へのアメリカの軍事介入、さらには2003年のアメリカのイラク侵攻の事例により検証しています。その結果、戦争に至った全ての事例において、かれは、意思決定者が自己肯定の錯覚による自信過剰に陥っていたことを発見しました。第一次世界大戦では、ドイツの戦争指導者は「8月の危機」において、戦争の早期終結に過剰な自信を抱いていました。ミュンヘン危機において、ヒトラーが戦争を踏みとどまったのは、意外に思えるかもしれませんが、その当時のドイツの政策決定が「開放的」だったことが影響しています。「ヒトラーはチェコスロバキアへの軍事攻撃を望んだ…が、かれのアドバイザーたちは、ドイツが引き続き負けそうだったので、侵略に反対した…ヒトラーの計画は…将軍や助言者と共に実行され、主要なインテリジェンス情報は隠し立てせずに議論された」のです(上記書、95-96ページ)。この段階では「ヒトラーは合理的に行動した」(上記書、95ページ)ということです。
キューバ危機では、ケネディー大統領は国家安全保障会議のエクスコムにおいて、アメリカがとるべき複数の選択肢を側近たちと忌憚なく議論しました。こうした開放的な議論は、ケネディーが自己肯定の錯覚による自信過剰に陥るのを戒めて、キューバにおけるソ連の核ミサイルを空爆で叩く、核戦争を招きかねない危険な軍事オプションを退けたのです。ところが、ベトナムへの軍事介入の政策決定では、ジョンソン政権は閉ざされた議論を行ってしまった結果、戦争の行方に悲観的な情報を排除してしまい、楽観的な展望に惑わされて泥沼の戦争にはまってしまいました。2003年のアメリカのイラク侵攻も、同じように意思決定がブッシュ大統領の側近を中心に、閉ざされたメンバーで行われてしまったために、戦争と戦後のイラクの民主化を楽観的に見立てて、体制転換(regime change)のために軍事力を行使したということです。
こうした画期的な学術成果を図書として刊行した後、ジョンソン氏は、ドミニク・ティアニー氏(スワ―スモア大学)と共著で、今度は、「否定的バイアス(negativity bias)」に関する新しい研究を発表しました(Dominic D.P. Johnson and Dominic Tierney, "Bad World: The Negativity Bias in International Politics," International Security, Vol. 43, No. 3, Winter 2018/2019, pp. 96-140)。ここでいう否定的バイアスとは、望まない悪い結果が生じる潜在性を示す情報や出来事、信条を過大に評価することです。簡単にいえば、悪いニュースは良いニュースより人々に強く影響するということです。この否定的バイアスも、自己肯定の錯覚と同様に、人間の進化の長い歴史から生じました。日常生活における危険(否定的出来事)は、生死に直結しかねないため、人間は自然選択の過程で、外部環境の危難に敏感になったということです。
人間が持っている否定的バイアスは、上記の自信過剰の肯定的バイアスと矛盾するように思われますが、かれらは、これら2つのバイアスが、人間の心理において共存すると主張しています。すなわち、人は外部の環境を判断する時は否定的バイアスに支配されやすくなる一方で、自分自身の判断や選択、行動を評価する際には自信過剰になりやすいのです。その結果、こうしたバイアスがかかった国家の指導者は、二重に戦争を引き起こしやすくなります。
「否定的バイアスは人々を周囲の環境に存在する潜在的脅威に警戒するよう仕向ける一方で、肯定的バイアスは人々が生じた危険を頑張って克服する手助けをする」(同上論文、119ページ)。
要するに、国家の指導者は外部の脅威を過大評価して危機感を募らせる一方で、その危険を戦争によって乗り越えることに過度な自信を持ちがちになるのです。ジョンソン氏とティアニー氏は、この仮説を第一次世界大戦のドイツの意思決定の事例で例証しています。カイザーは、フランスやロシアのドイツに対する意図を攻撃的なものだとみなし警戒していました。その一方で、ドイツの政策決定者は、前述したように、自らの軍事力や戦争における早期の勝利に過剰な自信を抱いてしまったのです。
戦争原因研究の個人レベル分析への「回帰」は、生物学や心理学の研究成果を取り入れることにより、戦争のパズルの解明を前進させました。その結果、国際関係論における戦争原因研究は、より幅が広くなり、より奥行きが深くなりました。その一方で、人間の心理バイアスに焦点を当てた個人レベルでの戦争原因へのアプローチに、問題がないわけではありません。最大の疑問の1つは、パワーという物質的要因が政治指導者の心理にどのような影響を及ぼしているのかが、個人レベルの生物学的解析や心理学的分析のみでは分からないことです。たとえば、ミュンヘン危機において、ドイツは再軍備の途上にあり、相対的な軍事バランスが必ずしも優勢ではなく、戦争で勝てる見込みが薄かったことが、ヒトラーをはじめとする指導者に開戦を思いとどまらせたとされています(なお、ミュンヘン危機におけるドイツの政策決定については、いくつかの歴史解釈がありますが、ここでは、それに触れないことにします)。ジョンソン氏自身が著書で認めているように、この時、ヒトラーは「合理的に」行動したということです。そうだとすれば、このことはシンプルな合理的選択理論で説明できそうです。この事象が合理的選択の「逸脱事例」ではなく、このロジックで簡潔に説明できるのであれば、わざわざ追加の心理的属性の変数を理論に追加して、説明を複雑にする必要はないでしょう。第一次世界大戦の勃発も、当時の列強に配分されたパワー構造と無関係ではなさそうです。ドイツは、ロシアの軍事動員がなくても、あるいは独露間の予想されるパワー・バランスの変化がなくても、上記の心理的バイアスに影響されて、戦争を行っただろうと推論できるでしょうか。キューバ危機における米ソの指導者の慎慮ある行動は、はたして「核革命」と無縁なのでしょうか。戦争原因の説明において、心理的バイアスが独立変数(原因)として戦争という従属変数(結果)に及ぼす因果効果は無視できないでしょうが、パワーといった物質的要因と心理的バイアスという非物質的要因の関係を明らかにすることは、依然、重要な研究解題として残されているように思います。
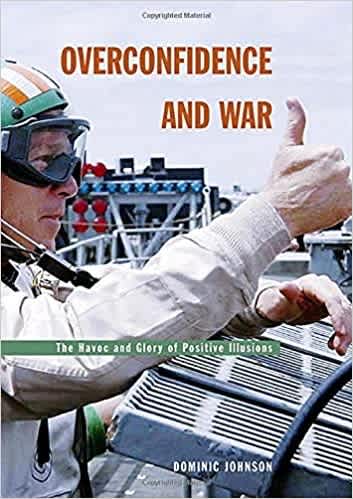
『自信過剰と戦争』は、今では国際関係論でなじみ深くなった「戦争のパズル」から議論を始めます。合理的選択のバーゲニング理論によれば、戦争は国家の指導者が、本当に「合理的」であれば起こらないはずです。なぜならば、双方の国家は相対的なパワーを反映した取引を成立させることにより、戦争のコストやリスクを避けられるからです。言い換えれば、当事国は戦争のコストを支払わずリスクも冒すことなく、戦争をした時と同じ結果をバーゲニングで得られるはずです。にもかかわらず、戦争が起こるのは、当事国のどちらか、もしくは両方が、自らの相対的パワーと戦勝の確率を実際より高く見積もっているからに他なりません。こうした「誤算」や「誤認」をもたらす最大の源泉の1つが、かれによれば、国家の指導者の自信過剰ということです。こうした自信過剰と戦争との因果理論は、ジェフリー・ブレイニー氏が戦争の原因を「楽観主義(optimism)」に求めた古典的なロジックをアップデートしたものだといえるでしょう(Geoffrey Blainey, The Causes of War, 3rd. ed., Free Press, 1988, pp. 35-56)。
ジョンソン氏によれば、人間の心理の基底には、自己肯定の錯覚(positive illusion)に導かれる自信過剰があります。こうした心理的バイアスは、人間が進化の過程で得たものであり、現在でも人々に広く認められるものだと、かれは主張しています。自然選択(natural selection)の長期的過程において、自己肯定の錯覚という心理的属性を持った人間が生き残り、繁殖して今日に至ったのです。この心理特性を持つ「楽観的な」人間は、自分の行動や将来展望を悲観視してあきらめてしまう人より、目標を達成できる見込みが高いと考えられます。自分に自信を持つ兵士や司令官、政治家が評価される所以です。
自信過剰は人間が環境に適応する際、有利に働いた一方で、残念なことに、人々の「合理的計算」をゆがめることになります。それが戦争の意思決定に働くと、時には破滅的な結末をもたらします。国家の政策決定者は、事態を楽観視する心理的バイアスに縛られてしまうと、戦争で勝利したり、戦争を簡単に終わらせられる蓋然性を過大評価してしまいます。その結果、交渉による紛争の解決より戦争がしばしば選好されることになります。すなわち、国家の指導者がもつ自己肯定の錯覚や自信過剰は、戦争の可能性を高めてしまうのです。
『自信過剰と戦争』が提供した行動論的な戦争原因の研究は、これまでややもすれば見過ごされがちだった、国際関係論における個人レベルの分析を再考することになりました。古典的な政治学では、戦争を引き起こす権力欲(animus dominandi)を備えた「人間本性」は固定化されたものだと論じられることがありました。人間本性は変わらないと。その一方で、戦争は起こったり起こらなかったりします。前者が一定で後者が変化するのであれば、両者に共変は認められないため、戦争は人間が引き起こすという直感に反して、それらは関係ないと結論づけらてしまいます。しかしながら、こうした通念は、ジョンソン氏によれば間違いであり、個人が抱く自己肯定の錯覚が高くなれば、人は自信過剰になるため、それだけ戦争を選択しやすくなるのです。人間の「本性」を「心理的バイアス」に置き換えるれば、個人レベルにおいて戦争の発生を説明できるようになるということです。そして、かれは、自信過剰と戦争の因果理論を構築します。その際、自己肯定の錯覚というバイアスが強まったり弱まったりする、理論の先行条件を特定しています。それらが「政治体制のタイプ」と「議論の開放性」です。一般的に、自由民主主義国では、政治指導者は政策を立案する過程で、さまざまな情報や批判的意見にさらされるために、自信過剰の心理バイアスが修正されやすくなります。ただし、民主体制下でも、政治的意思が閉ざされた環境で決定される場合、自信過剰な判断は是正されにくくなり、指導者は愚行に走りかねません。
ジョンソン氏は、上記の仮説を第一次世界大戦におけるドイツの戦争指導者の意思決定、ミュンヘン危機におけるヒトラーを取り巻く政治的状況、キューバ危機における米ソの対応、ヴェトナム戦争へのアメリカの軍事介入、さらには2003年のアメリカのイラク侵攻の事例により検証しています。その結果、戦争に至った全ての事例において、かれは、意思決定者が自己肯定の錯覚による自信過剰に陥っていたことを発見しました。第一次世界大戦では、ドイツの戦争指導者は「8月の危機」において、戦争の早期終結に過剰な自信を抱いていました。ミュンヘン危機において、ヒトラーが戦争を踏みとどまったのは、意外に思えるかもしれませんが、その当時のドイツの政策決定が「開放的」だったことが影響しています。「ヒトラーはチェコスロバキアへの軍事攻撃を望んだ…が、かれのアドバイザーたちは、ドイツが引き続き負けそうだったので、侵略に反対した…ヒトラーの計画は…将軍や助言者と共に実行され、主要なインテリジェンス情報は隠し立てせずに議論された」のです(上記書、95-96ページ)。この段階では「ヒトラーは合理的に行動した」(上記書、95ページ)ということです。
キューバ危機では、ケネディー大統領は国家安全保障会議のエクスコムにおいて、アメリカがとるべき複数の選択肢を側近たちと忌憚なく議論しました。こうした開放的な議論は、ケネディーが自己肯定の錯覚による自信過剰に陥るのを戒めて、キューバにおけるソ連の核ミサイルを空爆で叩く、核戦争を招きかねない危険な軍事オプションを退けたのです。ところが、ベトナムへの軍事介入の政策決定では、ジョンソン政権は閉ざされた議論を行ってしまった結果、戦争の行方に悲観的な情報を排除してしまい、楽観的な展望に惑わされて泥沼の戦争にはまってしまいました。2003年のアメリカのイラク侵攻も、同じように意思決定がブッシュ大統領の側近を中心に、閉ざされたメンバーで行われてしまったために、戦争と戦後のイラクの民主化を楽観的に見立てて、体制転換(regime change)のために軍事力を行使したということです。
こうした画期的な学術成果を図書として刊行した後、ジョンソン氏は、ドミニク・ティアニー氏(スワ―スモア大学)と共著で、今度は、「否定的バイアス(negativity bias)」に関する新しい研究を発表しました(Dominic D.P. Johnson and Dominic Tierney, "Bad World: The Negativity Bias in International Politics," International Security, Vol. 43, No. 3, Winter 2018/2019, pp. 96-140)。ここでいう否定的バイアスとは、望まない悪い結果が生じる潜在性を示す情報や出来事、信条を過大に評価することです。簡単にいえば、悪いニュースは良いニュースより人々に強く影響するということです。この否定的バイアスも、自己肯定の錯覚と同様に、人間の進化の長い歴史から生じました。日常生活における危険(否定的出来事)は、生死に直結しかねないため、人間は自然選択の過程で、外部環境の危難に敏感になったということです。
人間が持っている否定的バイアスは、上記の自信過剰の肯定的バイアスと矛盾するように思われますが、かれらは、これら2つのバイアスが、人間の心理において共存すると主張しています。すなわち、人は外部の環境を判断する時は否定的バイアスに支配されやすくなる一方で、自分自身の判断や選択、行動を評価する際には自信過剰になりやすいのです。その結果、こうしたバイアスがかかった国家の指導者は、二重に戦争を引き起こしやすくなります。
「否定的バイアスは人々を周囲の環境に存在する潜在的脅威に警戒するよう仕向ける一方で、肯定的バイアスは人々が生じた危険を頑張って克服する手助けをする」(同上論文、119ページ)。
要するに、国家の指導者は外部の脅威を過大評価して危機感を募らせる一方で、その危険を戦争によって乗り越えることに過度な自信を持ちがちになるのです。ジョンソン氏とティアニー氏は、この仮説を第一次世界大戦のドイツの意思決定の事例で例証しています。カイザーは、フランスやロシアのドイツに対する意図を攻撃的なものだとみなし警戒していました。その一方で、ドイツの政策決定者は、前述したように、自らの軍事力や戦争における早期の勝利に過剰な自信を抱いてしまったのです。
戦争原因研究の個人レベル分析への「回帰」は、生物学や心理学の研究成果を取り入れることにより、戦争のパズルの解明を前進させました。その結果、国際関係論における戦争原因研究は、より幅が広くなり、より奥行きが深くなりました。その一方で、人間の心理バイアスに焦点を当てた個人レベルでの戦争原因へのアプローチに、問題がないわけではありません。最大の疑問の1つは、パワーという物質的要因が政治指導者の心理にどのような影響を及ぼしているのかが、個人レベルの生物学的解析や心理学的分析のみでは分からないことです。たとえば、ミュンヘン危機において、ドイツは再軍備の途上にあり、相対的な軍事バランスが必ずしも優勢ではなく、戦争で勝てる見込みが薄かったことが、ヒトラーをはじめとする指導者に開戦を思いとどまらせたとされています(なお、ミュンヘン危機におけるドイツの政策決定については、いくつかの歴史解釈がありますが、ここでは、それに触れないことにします)。ジョンソン氏自身が著書で認めているように、この時、ヒトラーは「合理的に」行動したということです。そうだとすれば、このことはシンプルな合理的選択理論で説明できそうです。この事象が合理的選択の「逸脱事例」ではなく、このロジックで簡潔に説明できるのであれば、わざわざ追加の心理的属性の変数を理論に追加して、説明を複雑にする必要はないでしょう。第一次世界大戦の勃発も、当時の列強に配分されたパワー構造と無関係ではなさそうです。ドイツは、ロシアの軍事動員がなくても、あるいは独露間の予想されるパワー・バランスの変化がなくても、上記の心理的バイアスに影響されて、戦争を行っただろうと推論できるでしょうか。キューバ危機における米ソの指導者の慎慮ある行動は、はたして「核革命」と無縁なのでしょうか。戦争原因の説明において、心理的バイアスが独立変数(原因)として戦争という従属変数(結果)に及ぼす因果効果は無視できないでしょうが、パワーといった物質的要因と心理的バイアスという非物質的要因の関係を明らかにすることは、依然、重要な研究解題として残されているように思います。















