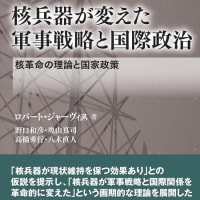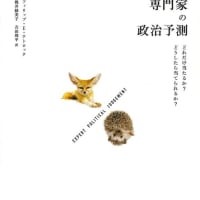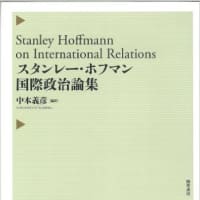私の所属先の看板「国際学」を構成する1つのアプローチが、「地域研究」(中国研究、アメリカ研究、中東研究など)です。私は最近、地域研究のある大家が、「中国研究」と社会科学について、次のように述べているのを目にしました。
「科学的分析とは予測能力を高めることにつながる。しかし、残念ながら社会科学は『科学』であるにもかかわらず『科学』でない部分が大きい。なぜなら人間やその集合体である社会の行動は非合理性に満ち溢れているからである。…中国の予測分析は…完全に外れた部分も多い」(国分良成編『中国は、いま』岩波書店、2011年、225ページ)。
この短い主張には、いろいろと興味深い問題が凝縮されています。今日は、そのことを少し考えてみましょう。
第1に、社会科学における合理性についてです。これまで社会科学の多くの分野が依拠してきた「合理性」概念には、確かに疑問が生じています。たとえば、戦争原因研究の分野では、ジェームズ・フィアロン氏(スタンフォード大学)の画期的な研究(James D. Fearon, "Rationalist Explanations for War," International Organization, Vol. 49, No. 3, June 1995)以来、戦争は国家が合理的であれば起こらないはずなのに、なぜ起こるのか、という疑問(パズル)から、国家の「非合理性」に戦争の原因を求めるアプローチが、盛んになってきました。経済学の分野でも、合理的選択理論から距離を起き、心理学から経済現象に迫る「行動経済学」が興隆しています。その背景には、河野勝氏(早稲田大学)が指摘するように、社会科学の多くの分野が「母体とした合理的選択がさまざまな方面で行き詰まった」ことがあります(河野勝・西條辰義編『社会科学の実験アプローチ』勁草書房、2007年、7ページ)。

ただし、ここで注意しなければならないことは、これらの研究アプローチは、科学としての社会科学を否定しているわけでもなければ、合理的アプローチを葬り去ろうとしているわけでもないということです。パズルへの接近ルートが変わってきたということです。たとえば、戦争はなぜ起こるのかというパズルについて言えば、合理的国家は、コストのかかる戦争をしないで、弱い方が強い方に、パワーの格差分の妥協をすれば、平和的解決に行く着くはずです。にもかかわらず、戦争が起こるということは、合理的な平和的解決を阻害する要因が、国家の政策決定に働いているからだ、ということになるでしょう。
要するに、国家の合理的行動を妨げる要因は何か、その候補となる要因は、どのように国家の合理的意思決定を歪めるのか、といった研究課題を科学的な手続きにしたがい解いていくということです。その際、「想像力」や「発想」力、「着想」力は、仮説を導出する初期の段階で重要な役割を果たすことでしょう。しかし、それは、社会科学の一連の気の遠くなるような研究プロセスを構成する、はじめの方の作業であり、全体のほんの一部分にしか過ぎません。このことについては、最後に説明します。
くわえて、非合理的に見える行動は、確かに「最適(optimal)」行動ではないのでしょうが、それは単に「最適以下(suboptimal)」の行動にすぎないかもしれません。さまざまな理由により、国家が最適行動をとれなくても、不思議ではありません。そうだとすれば、合理的理論を破棄するには時期尚早です。チャールズ・グレーザー氏(ジョージ・ワシントン大学)がいうように、「理論と国家行動がガッチリと合わなくても、それは、合理的理論の欠陥のせいではなく、(国家の)最適以下の決定を反映しているのかもしれません」(Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics, Princeton University Press, 2010, p. 19)。
第2に、社会科学における「科学」とは何か、ということです。この点は、ある程度、ハッキリさせたほうがよいでしょう。社会科学の方法を解説した、最も信頼のおける学術書として、Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton: Princeton University Press, 1994. (邦訳『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論』勁草書房、2004年) がありますので(略称KKV)、同書の定義を以下に引用します(原著、7-9ページ・邦訳、6-9ページ)。
1.目的は推論である。事実を集積しただけでは不十分である。科学研究の特徴は、事実を超えた推論を行う目的にある。
2.手続きが公開されている。これにより研究プロジェクト成果は追試され、研究者は学ぶことができる。
3.結論は不確実である。推論とは、不完全な過程である。
4.科学とは方法である。科学的研究とは、一連の推論のルールを厳守した研究である。
つまり、社会科学は、推論を目的としており、しかも推論には不確実性を伴うということなのです。このことは、以下の警告につながっていきます。
「研究者あるいは研究チームは、知識にも洞察にも限界があるなかで努力しており、間違いは避けられない。しかし、間違いは他の研究者によって指摘される。科学は社会的なものであることを理解すれば、批判されないような研究をしなければならないという拘束から研究者は解放される…批判されることのないような研究をする必要はない」(原著、9ページ・邦訳、9ページ)。
ですから、「予測」が外れたとしても、科学の手続きの厳守している限り、それは決して恥ずべきことではないということでしょう。ただし、ここで大切なことは、適切な推論の手続きを行っているかどうか、です。このことについて、再度、KKVから引いて、このブログを終わりにしたいと思います。
「仮説は着想のなかから生まれることを認めないとすれば…それは馬鹿げている。しかし、ひとたび仮説が立てられたら、その仮説の正しさを検証するためには、適切な科学的推論が必要である。…厳密さを欠いた解釈によって得られた結論は、未検証の仮説の状態を超えることはないし、そのような解釈は科学的推論というよりは個人的解釈にすぎなくなってしまう」(原著、38ページ・邦訳、46ページ、下線強調は引用者)。

このことは、社会科学における「科学」とそうでないものを分ける、1つの重要なメルクマール(目印)ではないでしょうか。もっとも、科学は「万能」ではありませんので、「社会科学」の看板さえ外してしまえば、このような、ややこしい議論に拘泥される必要はないでしょう。
「科学的分析とは予測能力を高めることにつながる。しかし、残念ながら社会科学は『科学』であるにもかかわらず『科学』でない部分が大きい。なぜなら人間やその集合体である社会の行動は非合理性に満ち溢れているからである。…中国の予測分析は…完全に外れた部分も多い」(国分良成編『中国は、いま』岩波書店、2011年、225ページ)。
この短い主張には、いろいろと興味深い問題が凝縮されています。今日は、そのことを少し考えてみましょう。
第1に、社会科学における合理性についてです。これまで社会科学の多くの分野が依拠してきた「合理性」概念には、確かに疑問が生じています。たとえば、戦争原因研究の分野では、ジェームズ・フィアロン氏(スタンフォード大学)の画期的な研究(James D. Fearon, "Rationalist Explanations for War," International Organization, Vol. 49, No. 3, June 1995)以来、戦争は国家が合理的であれば起こらないはずなのに、なぜ起こるのか、という疑問(パズル)から、国家の「非合理性」に戦争の原因を求めるアプローチが、盛んになってきました。経済学の分野でも、合理的選択理論から距離を起き、心理学から経済現象に迫る「行動経済学」が興隆しています。その背景には、河野勝氏(早稲田大学)が指摘するように、社会科学の多くの分野が「母体とした合理的選択がさまざまな方面で行き詰まった」ことがあります(河野勝・西條辰義編『社会科学の実験アプローチ』勁草書房、2007年、7ページ)。

ただし、ここで注意しなければならないことは、これらの研究アプローチは、科学としての社会科学を否定しているわけでもなければ、合理的アプローチを葬り去ろうとしているわけでもないということです。パズルへの接近ルートが変わってきたということです。たとえば、戦争はなぜ起こるのかというパズルについて言えば、合理的国家は、コストのかかる戦争をしないで、弱い方が強い方に、パワーの格差分の妥協をすれば、平和的解決に行く着くはずです。にもかかわらず、戦争が起こるということは、合理的な平和的解決を阻害する要因が、国家の政策決定に働いているからだ、ということになるでしょう。
要するに、国家の合理的行動を妨げる要因は何か、その候補となる要因は、どのように国家の合理的意思決定を歪めるのか、といった研究課題を科学的な手続きにしたがい解いていくということです。その際、「想像力」や「発想」力、「着想」力は、仮説を導出する初期の段階で重要な役割を果たすことでしょう。しかし、それは、社会科学の一連の気の遠くなるような研究プロセスを構成する、はじめの方の作業であり、全体のほんの一部分にしか過ぎません。このことについては、最後に説明します。
くわえて、非合理的に見える行動は、確かに「最適(optimal)」行動ではないのでしょうが、それは単に「最適以下(suboptimal)」の行動にすぎないかもしれません。さまざまな理由により、国家が最適行動をとれなくても、不思議ではありません。そうだとすれば、合理的理論を破棄するには時期尚早です。チャールズ・グレーザー氏(ジョージ・ワシントン大学)がいうように、「理論と国家行動がガッチリと合わなくても、それは、合理的理論の欠陥のせいではなく、(国家の)最適以下の決定を反映しているのかもしれません」(Charles L. Glaser, Rational Theory of International Politics, Princeton University Press, 2010, p. 19)。
第2に、社会科学における「科学」とは何か、ということです。この点は、ある程度、ハッキリさせたほうがよいでしょう。社会科学の方法を解説した、最も信頼のおける学術書として、Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton: Princeton University Press, 1994. (邦訳『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論』勁草書房、2004年) がありますので(略称KKV)、同書の定義を以下に引用します(原著、7-9ページ・邦訳、6-9ページ)。
1.目的は推論である。事実を集積しただけでは不十分である。科学研究の特徴は、事実を超えた推論を行う目的にある。
2.手続きが公開されている。これにより研究プロジェクト成果は追試され、研究者は学ぶことができる。
3.結論は不確実である。推論とは、不完全な過程である。
4.科学とは方法である。科学的研究とは、一連の推論のルールを厳守した研究である。
つまり、社会科学は、推論を目的としており、しかも推論には不確実性を伴うということなのです。このことは、以下の警告につながっていきます。
「研究者あるいは研究チームは、知識にも洞察にも限界があるなかで努力しており、間違いは避けられない。しかし、間違いは他の研究者によって指摘される。科学は社会的なものであることを理解すれば、批判されないような研究をしなければならないという拘束から研究者は解放される…批判されることのないような研究をする必要はない」(原著、9ページ・邦訳、9ページ)。
ですから、「予測」が外れたとしても、科学の手続きの厳守している限り、それは決して恥ずべきことではないということでしょう。ただし、ここで大切なことは、適切な推論の手続きを行っているかどうか、です。このことについて、再度、KKVから引いて、このブログを終わりにしたいと思います。
「仮説は着想のなかから生まれることを認めないとすれば…それは馬鹿げている。しかし、ひとたび仮説が立てられたら、その仮説の正しさを検証するためには、適切な科学的推論が必要である。…厳密さを欠いた解釈によって得られた結論は、未検証の仮説の状態を超えることはないし、そのような解釈は科学的推論というよりは個人的解釈にすぎなくなってしまう」(原著、38ページ・邦訳、46ページ、下線強調は引用者)。

このことは、社会科学における「科学」とそうでないものを分ける、1つの重要なメルクマール(目印)ではないでしょうか。もっとも、科学は「万能」ではありませんので、「社会科学」の看板さえ外してしまえば、このような、ややこしい議論に拘泥される必要はないでしょう。