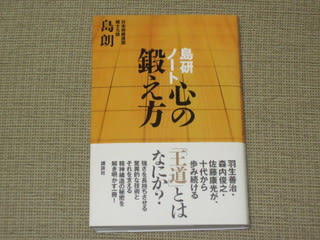島朗 2013年3月 講談社
島研というのは、島九段がやってた研究会であって、発足したのは昭和60年ころではないかと言われている。
メンバーがすごくて、佐藤康光、森内俊之、あとから加わったのが羽生善治、研究会始めたころ彼らはまだ十代だった。
んで、この本は、彼らがなんで強くなって、いまでも強いのかを書いたもの。
でも、よくあるハウツー本みたいな安易なつくりしてないから、簡単に答えが書いてあんぢゃなくて、読み応えはあるよ。
島九段は、A級に当然のごとく昇り、タイトルを獲ったこともあるんだけど、自分が強いだけでやっていけるトップ集団にいつまでもいるとは思ってなかったらしく、それは研究会のメンバーみたいな恐るべき後輩を目の当たりにしたこととも関連してるんだろうが、本書では、そのような心情も吐露している。
たとえば、「話せること・表現することが強さと同じくらい大切だという価値観を自然と自分の中に根付かせた」なんて言って、プロの世界を伝えることを自分の仕事だとしている。
「研究会のメンバーに会うことがなかったら、私は六段で終わっていた棋士だったと思う」とまで言ってる。
で、三人の強さの理由については、いろいろあるんだけど、集まって研究会をしたからぢゃなく、一人ずつの努力のほうが大きいと明かしている。
「羽生さん・佐藤さん・森内さんの話を長年聞いていると、予習より復習に時間をかけていることもわかった」とか、「群れることが中心の勉強法で、一人で鍛え上げてきた世代にこれから勝てるとは、私には考えにくい」とか、やっぱ集まったとき以外に、いかに自分ひとりで徹底的に検証・鍛錬するかが重要だってことだろう。
そのへんに関連して、負けたあとに、敗北の理由をどう振り返るか、自分の技術や当時の心理を洗い直すことの難しさについても、くわしく自身の考えを書いてくれてるけど、一対一の勝負で言い訳ができないのは、やっぱそうとうツライみたい。
また、羽生・佐藤・森内の強さについて、これは他のひともよく言ってることかもしれないが、真実を追究することへの純粋な情熱をもっていることも、大きな要素だとしている。
「成功するために努力する、というのは結果を前提とした思想なのかもしれない(略)見返りを求めての勉強はそれがかなわなければいとも簡単に挫折する」なんてのは、厳しいけど事実だろうと思う。
それはそうと、この本についても、昔のネタばらしを何でもしようってわけぢゃない。勝負の世界のことだから、今後に影響するようなことはむやみに書かない。
そのへんを「私がソーシャルメディアから距離を置いているのは、今の社会風潮が含羞の精神に欠ける気がするからだ」と言って、なんでもあけすけに語ればいいってもんぢゃないというスタンスを表明している。
「羽生さん・佐藤さん・森内さんの美しさは「群れない強さと、含羞と恥じらいの美」だと思っている」って一節、著者の語りたいことのメインのひとつなんぢゃないかと思う。
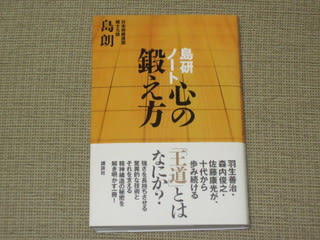
島研というのは、島九段がやってた研究会であって、発足したのは昭和60年ころではないかと言われている。
メンバーがすごくて、佐藤康光、森内俊之、あとから加わったのが羽生善治、研究会始めたころ彼らはまだ十代だった。
んで、この本は、彼らがなんで強くなって、いまでも強いのかを書いたもの。
でも、よくあるハウツー本みたいな安易なつくりしてないから、簡単に答えが書いてあんぢゃなくて、読み応えはあるよ。
島九段は、A級に当然のごとく昇り、タイトルを獲ったこともあるんだけど、自分が強いだけでやっていけるトップ集団にいつまでもいるとは思ってなかったらしく、それは研究会のメンバーみたいな恐るべき後輩を目の当たりにしたこととも関連してるんだろうが、本書では、そのような心情も吐露している。
たとえば、「話せること・表現することが強さと同じくらい大切だという価値観を自然と自分の中に根付かせた」なんて言って、プロの世界を伝えることを自分の仕事だとしている。
「研究会のメンバーに会うことがなかったら、私は六段で終わっていた棋士だったと思う」とまで言ってる。
で、三人の強さの理由については、いろいろあるんだけど、集まって研究会をしたからぢゃなく、一人ずつの努力のほうが大きいと明かしている。
「羽生さん・佐藤さん・森内さんの話を長年聞いていると、予習より復習に時間をかけていることもわかった」とか、「群れることが中心の勉強法で、一人で鍛え上げてきた世代にこれから勝てるとは、私には考えにくい」とか、やっぱ集まったとき以外に、いかに自分ひとりで徹底的に検証・鍛錬するかが重要だってことだろう。
そのへんに関連して、負けたあとに、敗北の理由をどう振り返るか、自分の技術や当時の心理を洗い直すことの難しさについても、くわしく自身の考えを書いてくれてるけど、一対一の勝負で言い訳ができないのは、やっぱそうとうツライみたい。
また、羽生・佐藤・森内の強さについて、これは他のひともよく言ってることかもしれないが、真実を追究することへの純粋な情熱をもっていることも、大きな要素だとしている。
「成功するために努力する、というのは結果を前提とした思想なのかもしれない(略)見返りを求めての勉強はそれがかなわなければいとも簡単に挫折する」なんてのは、厳しいけど事実だろうと思う。
それはそうと、この本についても、昔のネタばらしを何でもしようってわけぢゃない。勝負の世界のことだから、今後に影響するようなことはむやみに書かない。
そのへんを「私がソーシャルメディアから距離を置いているのは、今の社会風潮が含羞の精神に欠ける気がするからだ」と言って、なんでもあけすけに語ればいいってもんぢゃないというスタンスを表明している。
「羽生さん・佐藤さん・森内さんの美しさは「群れない強さと、含羞と恥じらいの美」だと思っている」って一節、著者の語りたいことのメインのひとつなんぢゃないかと思う。