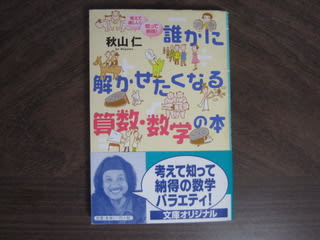秋山仁 平成11年 幻冬舎文庫
バラエティ系数学(?)つながりで。
一時期、有り余るヒマがあった若いころに比べて、ちゃんと時間をとっての読書とかができなくなっちゃった時期があったんだけど、そういうときでも活字は好きなので、わりと一章が短くて、どっからでも読める雑学本なんかを多く読んでたんで、そのころのものだと思う。
全21題の数学・算数的な問題が詰まってますが。
私としては、図形とかよりも、確率の問題がわりと好きだったりします。
たとえば、大相撲の優勝決定戦でつかう巴戦。3人が決勝進出したとき、AとBが戦って、勝ったほうが次Cとやる。最初に勝ったのがCに勝てば優勝だけど、Cが勝ったら、最初の負けたほうがまた出てきてCと戦って、って誰かが2連勝するまでやるシステム。
これは、最初に空き番のCが損だという。自分が登場したとき、相手はどちらにしろ既に1勝あげてるから、自分は優勝するには絶対負けられない。それに比べて、最初にぶつかるAとBは最初に負けても、次の結果次第でもう一回チャンスまわってくるから、初戦は絶対に負けられないわけではないと。なるほど。で、その確率はどんくらい、ってのが書いてあったりします。
あと「最適停止の理論」の問題。
>20人の相手とお見合いをするとき、可能な限り望ましい相手と結婚する方法を次の条件によって求めよ。 1、相手からは断られない。2、結婚を申し込むのは1度だけ。3、断った相手には2度と会えない。
で、ある理論と戦略をとれば、「平均で」20人中3位までの相手と結婚できる、という話。
どうでもいいけど、私があれこれと、あんまり役に立ちそうにないことを勉強するようになったのは、中学3年のときの数学が発端だと、いま思い出した。
4月の最初の授業のときか、小テストのときかな、「数学について思うことを書け」って項目があって。
私は「方程式使わなくても買い物はできる」とか「実生活で図形の面積求めたことなんかない」みたいなこと、延々と書いて、「だから、こんなもん必要ない、だから、数学嫌い」みたいなことをたくさん書きました。(そんな嫌いぢゃなかったんだけどね、まあナマイキ言いたがる悪いガキだったのよ。)
それが返ってきたときの、先生の赤ペンでの答えは、ひとこと。
「ただ生きるだけなら誰でもできる」でした。
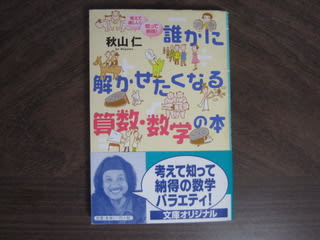
バラエティ系数学(?)つながりで。
一時期、有り余るヒマがあった若いころに比べて、ちゃんと時間をとっての読書とかができなくなっちゃった時期があったんだけど、そういうときでも活字は好きなので、わりと一章が短くて、どっからでも読める雑学本なんかを多く読んでたんで、そのころのものだと思う。
全21題の数学・算数的な問題が詰まってますが。
私としては、図形とかよりも、確率の問題がわりと好きだったりします。
たとえば、大相撲の優勝決定戦でつかう巴戦。3人が決勝進出したとき、AとBが戦って、勝ったほうが次Cとやる。最初に勝ったのがCに勝てば優勝だけど、Cが勝ったら、最初の負けたほうがまた出てきてCと戦って、って誰かが2連勝するまでやるシステム。
これは、最初に空き番のCが損だという。自分が登場したとき、相手はどちらにしろ既に1勝あげてるから、自分は優勝するには絶対負けられない。それに比べて、最初にぶつかるAとBは最初に負けても、次の結果次第でもう一回チャンスまわってくるから、初戦は絶対に負けられないわけではないと。なるほど。で、その確率はどんくらい、ってのが書いてあったりします。
あと「最適停止の理論」の問題。
>20人の相手とお見合いをするとき、可能な限り望ましい相手と結婚する方法を次の条件によって求めよ。 1、相手からは断られない。2、結婚を申し込むのは1度だけ。3、断った相手には2度と会えない。
で、ある理論と戦略をとれば、「平均で」20人中3位までの相手と結婚できる、という話。
どうでもいいけど、私があれこれと、あんまり役に立ちそうにないことを勉強するようになったのは、中学3年のときの数学が発端だと、いま思い出した。
4月の最初の授業のときか、小テストのときかな、「数学について思うことを書け」って項目があって。
私は「方程式使わなくても買い物はできる」とか「実生活で図形の面積求めたことなんかない」みたいなこと、延々と書いて、「だから、こんなもん必要ない、だから、数学嫌い」みたいなことをたくさん書きました。(そんな嫌いぢゃなかったんだけどね、まあナマイキ言いたがる悪いガキだったのよ。)
それが返ってきたときの、先生の赤ペンでの答えは、ひとこと。
「ただ生きるだけなら誰でもできる」でした。