『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(1985)
監督:黒沢清
脚本:黒沢清、万田邦敏
出演者:洞口依子、伊丹十三
撮影:瓜生敏彦
編集:菊池純一
【作品概要】
心理学の教授が、田舎から上京してきた女子大生を自らの妙な理論の実験材料にする異色コメディ。もともと成人映画として撮影されたままオクラになっていたものを商業用に再編集した作品。黒沢清監督の出世作。

【感想レビュー】
 ドミソファラソシ、ドシラソファラソシラソファミレドド、ドラソファミレミドソ
ドミソファラソシ、ドシラソファラソシラソファミレドド、ドラソファミレミドソ
冒頭、機会的な音色の単旋律に不可思議な世界へと導かれる…
とにかく洞口依子さんが可愛いのだ
黒沢清作品を観る旅、で観ております。
あぁ、こっちのテイストかと思ったのは、同監督の特集上映で観た『神田川淫乱戦争』の記憶から。
岸野萌圓さんが、どちらにも出ていたのもあります。
この淡々としたテンションで、シュールなシーンが連続していく感じ、嫌いじゃないです
なんだろう。この癖になる感じは…
Yahoo!映画などのレビューを読むと、ゴダールの影響に言及されている方が多いのですが、こういうコアな映画観賞歴の浅い私は、残念ながらまだゴダールを観たことがありません。。なので、感じたことを…。
大学という、やたらだだっ広くて遊んでいる敷地の多い場所が舞台で、がらんどうとした建物内の異様な美しさは、思わず息を呑みます
忘れ去られたような廃墟のような建物。
それは60年代、70年代の大学闘争の熱狂とその衰退を映像だけで表していると思うし、なんか80年代はそういう空虚な時代だったのだなとちょっと切なくなってみたり…
ノンポリの学生達に、妙な“恥じらい理論”を講義する心理学の教授。
これがまたじわじわくる面白さです
劇中にも、学生達と教授のやりとりに下記のような台詞が出てきますが、一貫して、音楽だけが絶対的な存在に描かれています。
学生『でも本当にどうしてでしょうね、音楽というものだけが必ず僕たちを感動させるでしょ、必ずなんですよね、あれが不思議で。』
教授『それ絶対音ってのがあるだろ』
(ちょっと台詞の細部が違うかもですが…)
それで、色んな音楽が使われます。
音楽とシュールなシーンが不思議と融合しています
黒沢作品をもう少し観てから読もうと思っていたのですが、先日、“黒沢清、21世紀の映画を語る”という監督の著書を我慢できず買って読んでしまいました
大島渚監督の『日本春歌考』についての記述が興味深かったです。音楽と映画と政治、世相?などなど。
『ドレミファ娘〜』とも何か繋がるところがあるのかしら、と『日本春歌考』を観るのも楽しみです
こうやってどんどん観たい作品が拡がっていきます… でも、嬉しいことです
でも、嬉しいことです

また、裸婦画のように動かない女性達が動き出し、リアルな性が表出するところも印象的でした。
近作『クリーピ』にも換気扇や扇風機の描写がありますが、この作品にもあって、なんだか嬉しくなりました
ブラームスのポスターの目元をくり抜くシーン、面白かったな
まだまだ黒沢清監督作品の旅は続きそうです

監督:黒沢清
脚本:黒沢清、万田邦敏
出演者:洞口依子、伊丹十三
撮影:瓜生敏彦
編集:菊池純一
【作品概要】
心理学の教授が、田舎から上京してきた女子大生を自らの妙な理論の実験材料にする異色コメディ。もともと成人映画として撮影されたままオクラになっていたものを商業用に再編集した作品。黒沢清監督の出世作。

【感想レビュー】
 ドミソファラソシ、ドシラソファラソシラソファミレドド、ドラソファミレミドソ
ドミソファラソシ、ドシラソファラソシラソファミレドド、ドラソファミレミドソ
冒頭、機会的な音色の単旋律に不可思議な世界へと導かれる…

とにかく洞口依子さんが可愛いのだ

黒沢清作品を観る旅、で観ております。
あぁ、こっちのテイストかと思ったのは、同監督の特集上映で観た『神田川淫乱戦争』の記憶から。
岸野萌圓さんが、どちらにも出ていたのもあります。
この淡々としたテンションで、シュールなシーンが連続していく感じ、嫌いじゃないです

なんだろう。この癖になる感じは…

Yahoo!映画などのレビューを読むと、ゴダールの影響に言及されている方が多いのですが、こういうコアな映画観賞歴の浅い私は、残念ながらまだゴダールを観たことがありません。。なので、感じたことを…。
大学という、やたらだだっ広くて遊んでいる敷地の多い場所が舞台で、がらんどうとした建物内の異様な美しさは、思わず息を呑みます

忘れ去られたような廃墟のような建物。
それは60年代、70年代の大学闘争の熱狂とその衰退を映像だけで表していると思うし、なんか80年代はそういう空虚な時代だったのだなとちょっと切なくなってみたり…

ノンポリの学生達に、妙な“恥じらい理論”を講義する心理学の教授。
これがまたじわじわくる面白さです

劇中にも、学生達と教授のやりとりに下記のような台詞が出てきますが、一貫して、音楽だけが絶対的な存在に描かれています。
学生『でも本当にどうしてでしょうね、音楽というものだけが必ず僕たちを感動させるでしょ、必ずなんですよね、あれが不思議で。』
教授『それ絶対音ってのがあるだろ』
(ちょっと台詞の細部が違うかもですが…)
それで、色んな音楽が使われます。
音楽とシュールなシーンが不思議と融合しています

黒沢作品をもう少し観てから読もうと思っていたのですが、先日、“黒沢清、21世紀の映画を語る”という監督の著書を我慢できず買って読んでしまいました

大島渚監督の『日本春歌考』についての記述が興味深かったです。音楽と映画と政治、世相?などなど。
『ドレミファ娘〜』とも何か繋がるところがあるのかしら、と『日本春歌考』を観るのも楽しみです

こうやってどんどん観たい作品が拡がっていきます…
 でも、嬉しいことです
でも、嬉しいことです

また、裸婦画のように動かない女性達が動き出し、リアルな性が表出するところも印象的でした。
近作『クリーピ』にも換気扇や扇風機の描写がありますが、この作品にもあって、なんだか嬉しくなりました

ブラームスのポスターの目元をくり抜くシーン、面白かったな

まだまだ黒沢清監督作品の旅は続きそうです




















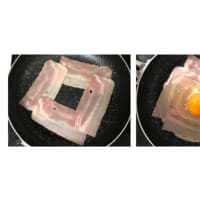

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます