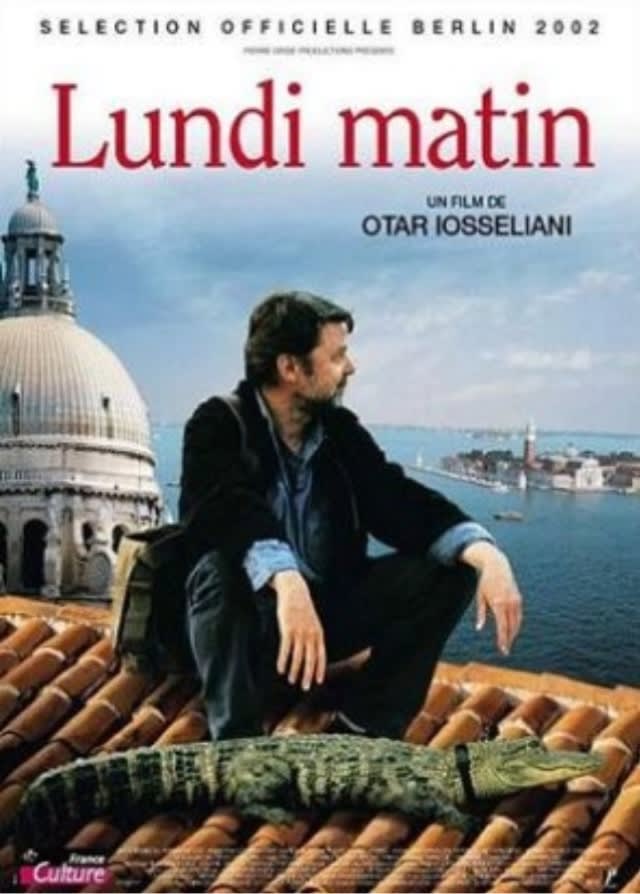『西遊』(2014)
【作品概要】
フランス、台湾 / 2014 / 56分
監督:ツァイ・ミンリャン (TSAI Ming Liang)
【作品解説】
2012年以降、ツァイ・ミンリャンは僧に扮したリー・カンションが超スローモーションで歩く姿をとらえた短編を連作している。『無色』(12)、『行者』(12)、『金剛経』(12)、『行在水上』(13)といった作品群がこれにあたる。中でも香港映画祭からの委嘱でオムニバス映画『美好2012』の1篇として製作された『行者』はカンヌ映画祭批評家週間のクロージングを飾るなど大きな反響を巻き起こした。この作品群に連なる最新作である『西遊』は、舞台を南仏のマルセイユに移し、レオス・カラックス作品の常連ドゥニ・ラヴァンが共演しているという点で、このシリーズの一つの頂点を成す作品と言える。映画の極北とも言うべき異形の傑作である。ベルリン映画祭パノラマ部門で上映。 (フィルメックス公式サイトより)

【感想レビュー】@東京フィルメックス
昨年のフィルメックスで観た『ピクニック』に続いてツァイ・ミンリャン2作品目。
初っ端から、あぁ…!(覚悟して観始めたものの )この世界観…!蘇ってきました。
)この世界観…!蘇ってきました。
生きてきた時間を刻印してきたかのようなドゥニ・ラヴァンの皺が、だんだんと愛おしく感じられてくる。
生きてきた証となるその皺やその息遣い。揺るぎない、その存在感。
圧倒されます。
しかし、長い!
…果てしなく、長い!
(どこまで睨めっこが続くのかとだんだん笑えてきます )
)
そして、スローモーションで歩く僧侶。その動きは、まるでコンテンポラリー・ダンスを観ているかのようだ。
そして、観ているこちらの時間が支配される感覚が、ダンスや音楽に近いように思う…のに、そのスタイルは、時間の経過と共に変化していく絵画を眺めているようで、なんとも不思議な体験だ。
人それぞれに、それぞれの“生きてきた時間”、“生きている時間”、“生きていく時間”が存在する。人生は“時間”そのもの。
やがてスクリーンというキャンバスに、いくつもの“時間”が映し出される。
まさにアート映画‼

観て数日経ちました。じわじわ噛み締めながら、ほっこりときています
【作品概要】
フランス、台湾 / 2014 / 56分
監督:ツァイ・ミンリャン (TSAI Ming Liang)
【作品解説】
2012年以降、ツァイ・ミンリャンは僧に扮したリー・カンションが超スローモーションで歩く姿をとらえた短編を連作している。『無色』(12)、『行者』(12)、『金剛経』(12)、『行在水上』(13)といった作品群がこれにあたる。中でも香港映画祭からの委嘱でオムニバス映画『美好2012』の1篇として製作された『行者』はカンヌ映画祭批評家週間のクロージングを飾るなど大きな反響を巻き起こした。この作品群に連なる最新作である『西遊』は、舞台を南仏のマルセイユに移し、レオス・カラックス作品の常連ドゥニ・ラヴァンが共演しているという点で、このシリーズの一つの頂点を成す作品と言える。映画の極北とも言うべき異形の傑作である。ベルリン映画祭パノラマ部門で上映。 (フィルメックス公式サイトより)

【感想レビュー】@東京フィルメックス
昨年のフィルメックスで観た『ピクニック』に続いてツァイ・ミンリャン2作品目。
初っ端から、あぁ…!(覚悟して観始めたものの
 )この世界観…!蘇ってきました。
)この世界観…!蘇ってきました。生きてきた時間を刻印してきたかのようなドゥニ・ラヴァンの皺が、だんだんと愛おしく感じられてくる。
生きてきた証となるその皺やその息遣い。揺るぎない、その存在感。
圧倒されます。
しかし、長い!
…果てしなく、長い!
(どこまで睨めっこが続くのかとだんだん笑えてきます
 )
)そして、スローモーションで歩く僧侶。その動きは、まるでコンテンポラリー・ダンスを観ているかのようだ。
そして、観ているこちらの時間が支配される感覚が、ダンスや音楽に近いように思う…のに、そのスタイルは、時間の経過と共に変化していく絵画を眺めているようで、なんとも不思議な体験だ。
人それぞれに、それぞれの“生きてきた時間”、“生きている時間”、“生きていく時間”が存在する。人生は“時間”そのもの。
やがてスクリーンというキャンバスに、いくつもの“時間”が映し出される。
まさにアート映画‼


観て数日経ちました。じわじわ噛み締めながら、ほっこりときています