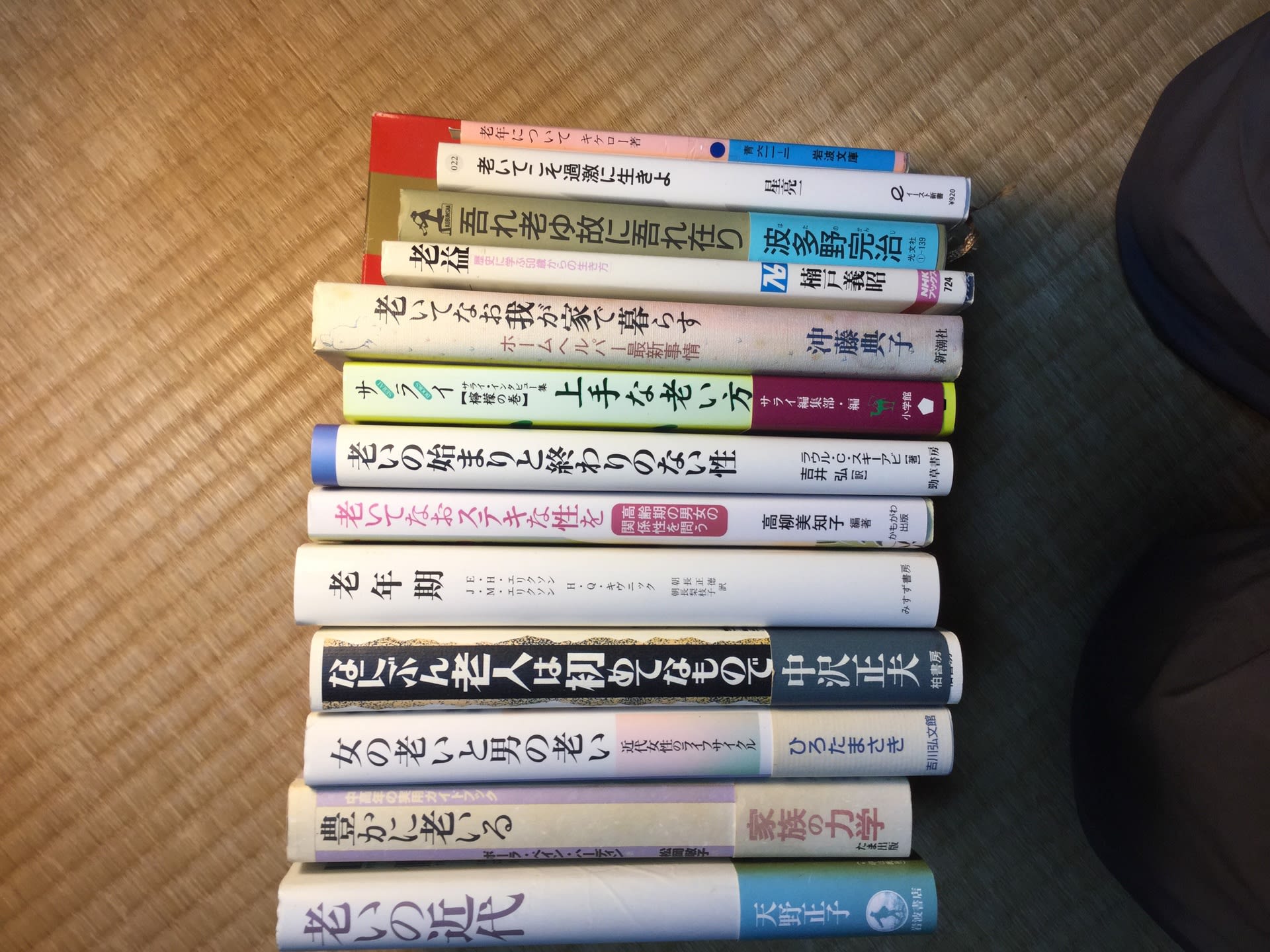午前中は健康診査、手元にある「検診結果のお知らせ」を見ると、75歳と77歳78歳と受けているので、今回が70歳代最終の健康状態がわかることになる。前回の健診がきっかけになって昨年秋の心臓に関しての検査入院になったのだから、さて今回はどういう結果が出ることか、来月20日に分かる。
終わってみて、この検診で認知症については? と思った。「結果表」の記載にはそれに該当するものはないし、事前に「認知症の検査希望」という記入欄もなかったので、この種の健診には対象になっていないのでしょう。
昨日の「てんがらもんラジオ」の話のこともあって、気になったことです、高齢者の運転免許更新には認知症検査があると聞いたことがありました。自動車運転という自他とともに死傷事故につながること恐れもあることですから、必要な検査なのでしょうが、日常生活にも多大な影響をもつ病気だけに健診項目に入って然るべきことでしょう。
健診が終わって昨夜の食事から18時間後の昼飯を腹に入れて、雨も上がったのでkaeru夫人の願事を祈願しようと神武寺に向かいました。33年のご開帳は明後日まで、次は33年後ですからその時は二人で天上から参ることになるでしょうと、雨上がりの山道を二本足で登りました。葉山で育った者にとってこの山道は小学校の遠足の道だったそうですが、何十年ぶりかでしょう。
kaeru夫人はかなり長く手を合わせていました、沢山沢山願い事があったのでしょう。私は先日お参りしていましたので、短くこれだけはということを、お互いの健康こそが何よりということは言わずもがな、ですが。
願いかなって健診結果は、良好!となれば、神様仏様ならぬ神さんの神通力の威力です、さて……。