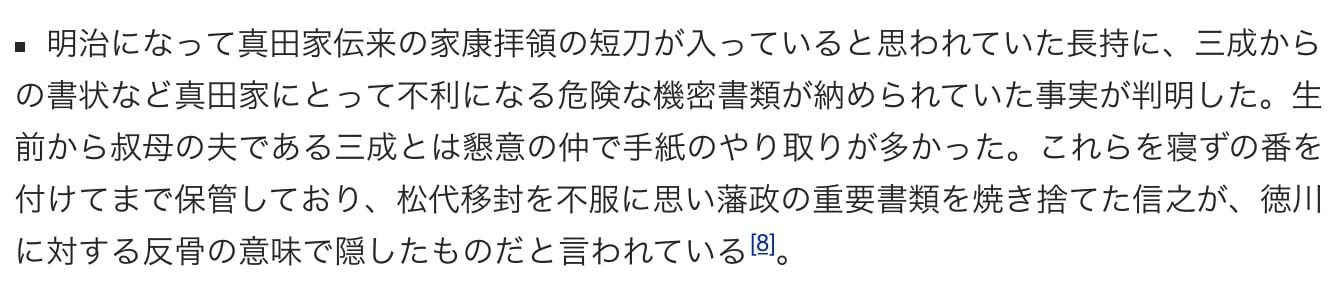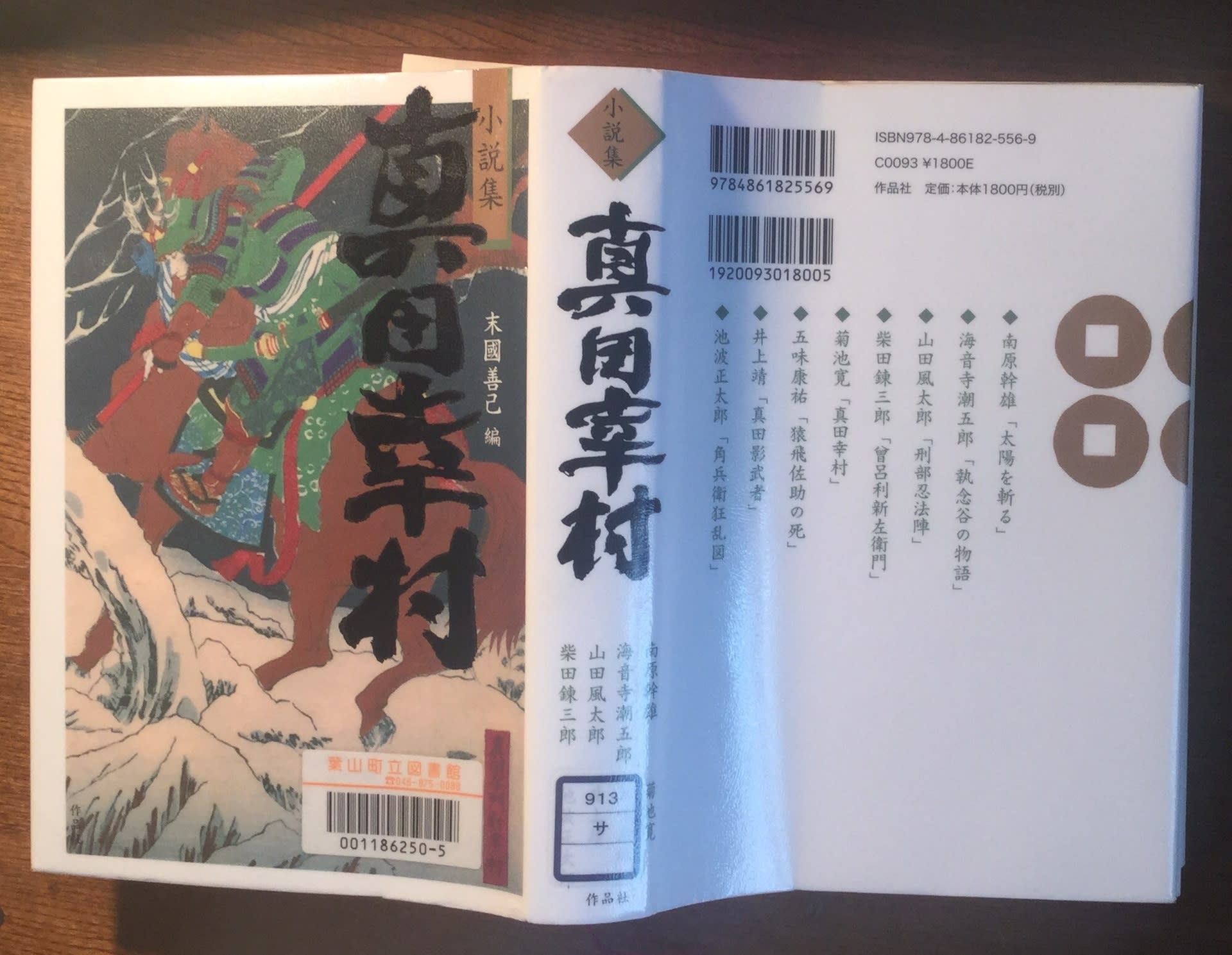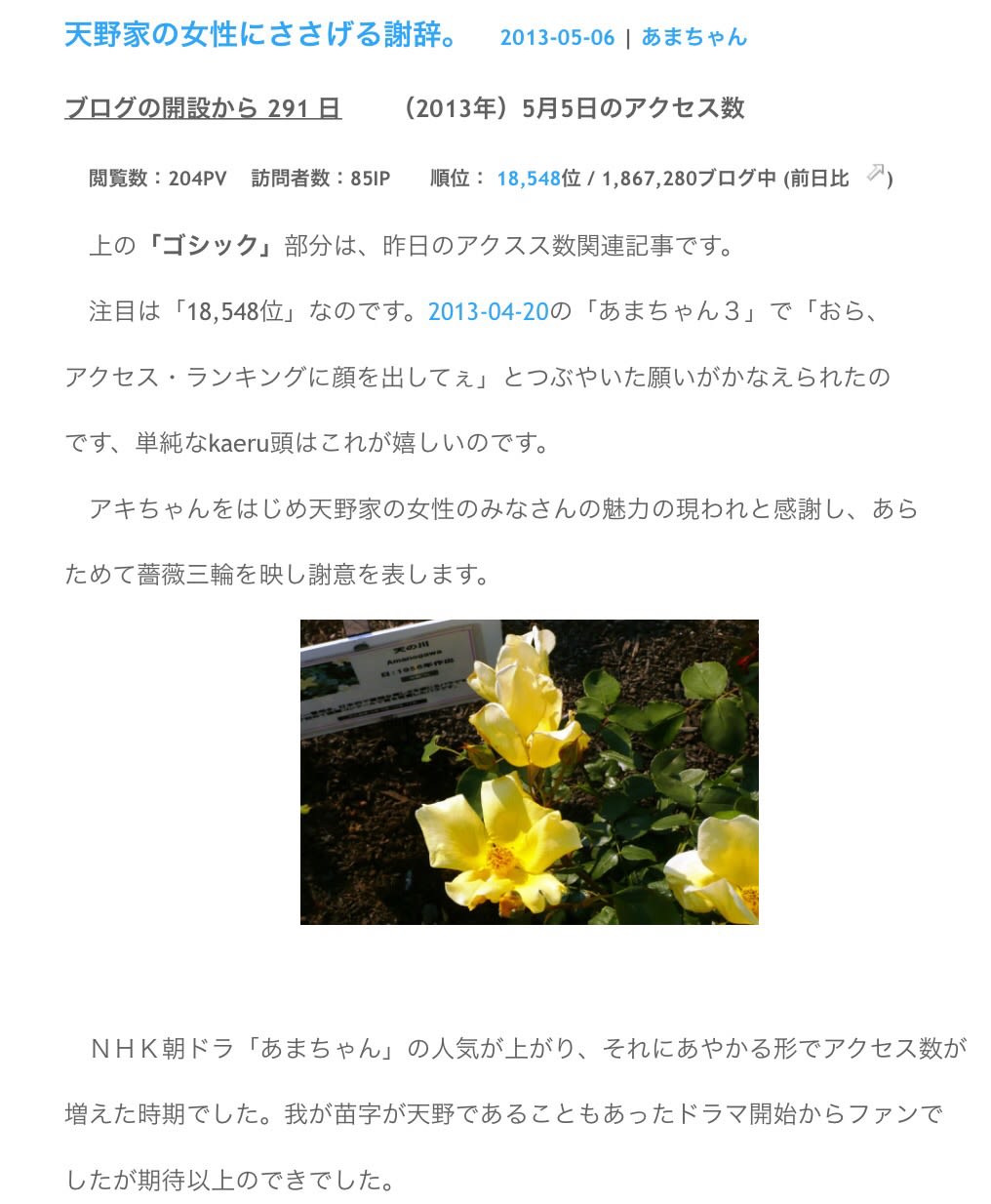先週第41話は「入城」今夜が「味方」来週が「軍議」そのあと7回で終了。歴史は「大坂の陣」の勝敗の結果を知っている事になっています。それにそって私たちも知ったことになってます。
しかし、慶長十九年十月・1614年12月大坂城に集まって行った人々は歴史を作って行った人ではありますが、その結果を知るのはかなりあとでしょう。今このドラマを作っている人々も歴史の結果のなかには立っていません。それも真田信繁に身を託している人々ですから、今夜の最終場面で「この戦は勝てる」と言った幸村の言葉に本気になっている人々でしょう。
しかし、というふうに言葉を継いではならないのです。しかし、と言いはじめれば「歴史の真実は」などとつながり「冷酷にも信繁はあと一歩のところまで家康を追い込み」みたいなことにつながってしまします。
そこで、暫くドラマや信繁から離れてやはり平山さんの『真田信繁』の紙面をお借りします、大坂城をめぐる人、米、武器です。
「大坂城の総兵力については、諸説あって定まっていない。総人数が侍八万七百余人、雑兵十万の合計十九万余という説、十三万人という説、七万^_^三千五百人の着到を数えたという説、雑兵含めて三万余人など様々です。おおよそ十万にだったのではないでしょうか(と平山さんの言葉)。
こういう人数ですから兵糧の確保が大変です。《大坂城の太閤遺金を鋳潰し、その金で大坂城下町はもとより大坂の集まってくる米を買い漁った。》このため米価は暴騰し、他では十八匁くらいが大坂では百三十目になったと書かれています。
火薬の調達で外国商人が色めき立ちます。イギリス商人《イートンは、十月八日(慶長十九年九月五日)には鉛の購入を堺商人に依頼され、提示された値段が百斤=五十五匁であったため返答しなかったといい》ます。《 鉛は、遂には十二月五日(慶長十九年十一月五日)には百斤=金六両に高騰した。これは大坂に流れる物資の動きを徳川方に切り替える役割を果たしたと考えられる。
豊臣、徳川双方の物資確保をめぐる経済戦争は、結果的に諸大名や民衆の生活を逼迫させ、死の商人たちを肥え太らせる結果となった。》というわけです。
こうして大坂城内から目を外へ、それも人数とかお金、米、武器などなど、それに民衆の暮らしの変化まで見ていくことが「歴史の真実」をみる上では欠かせないようです。