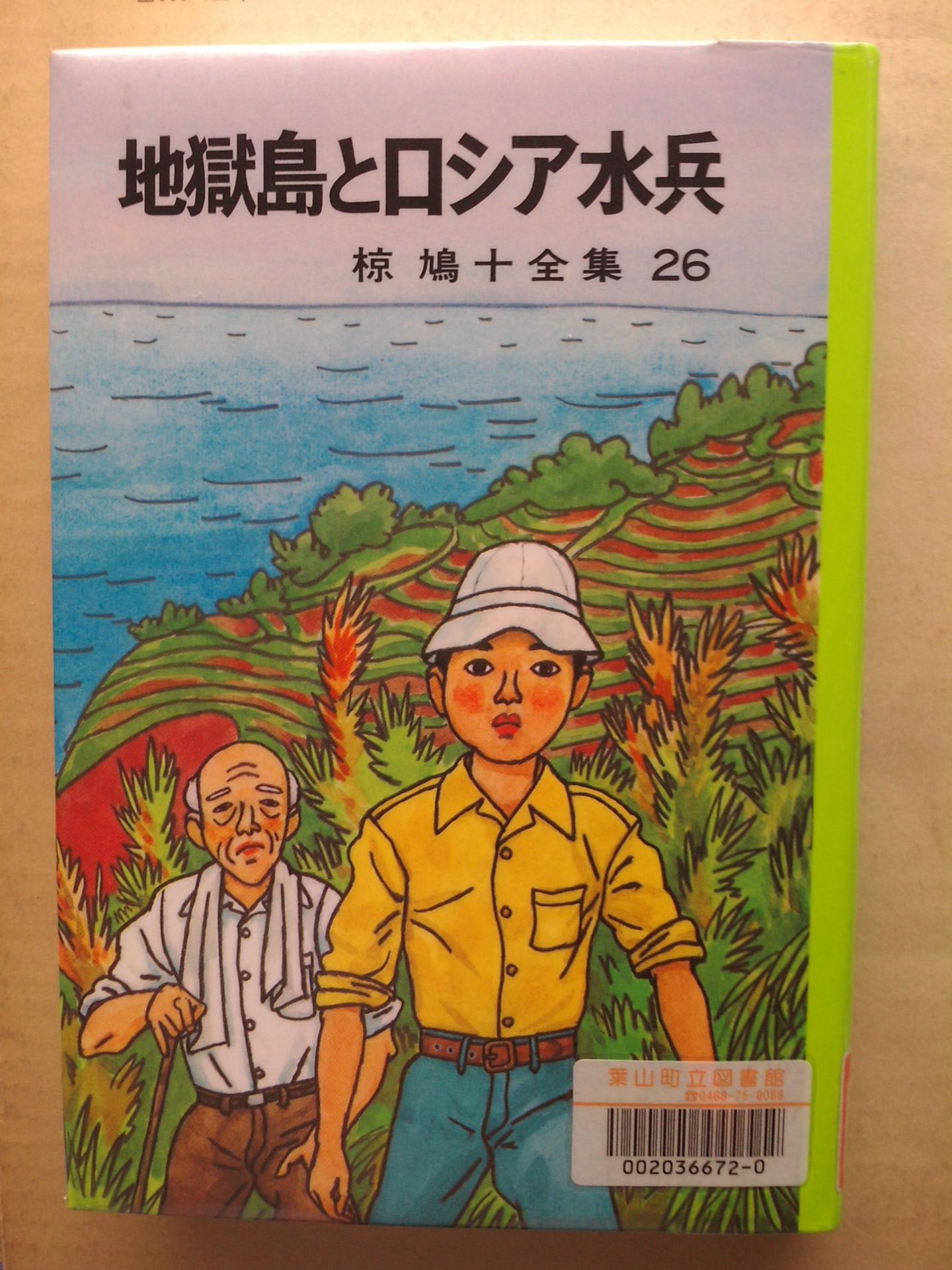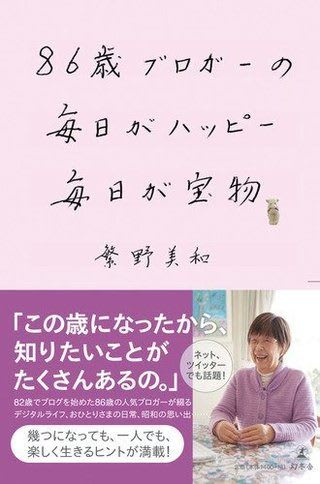この本の出版社大月書店のこの本の 「紹介」 です。
http://www.otsukishoten.co.jp/book/b185350.html

今、拾い読みをしています、読みやすい本ですから最初から読み出したの
ですが、バラバラめくっていてこんな所に目が止りました。
それは「認知症介護研究 ・ 研修東京センター」 の永田久美子さんの 「解
説」 の部分です。
≪ I T機器を自身の分身として
佐藤さんは、発症のかなり早い時期から文字を手書きすることに苦労するよ
うになりました。 書けなくなっていくなかで、発症前からなじんでいたパソコン
に加えて、発症後に携帯電話のメールやタブレット端末の操作に新たに挑戦し
ました。(略)
I T機器を利用して日々の 「暮らしの記憶」 を記録し、保存することが佐藤さ
んの新しい暮らしの習慣となり、I T 機器が佐藤さんの外付けの頭脳として威
力を発揮しています。
佐藤さんは、パソコン等にとにかく保存することで、当初つきまと って離れな
かった 「忘れる不安」 から解放され、ずいぶんと安定し、のびのび暮らす自信
を得たように思います。
そして、それらに保存された記録を見ることで、佐藤さんはその時々(人生
の大切な場面 ) 何が起こっていたのか、その詳細を確認し、時系列の変化を
いまでも追うことが可能になっています。≫
この 「I T機器を自身の分身として」 の部分だけでも3頁ほどですから極一
部の引用ですが、I T 機器と認知症患者との有機的関係を示していると思いま
す。
そしてこうしてブログで 「つぶやき」 コメントをいただき、昨日と今日を結び、明
日への己の存在を受け止めることが出来るのも、この有機的関係のすそ野の一
部ではないかと思うのです。
ブログの縁も他生の縁、ひとりの認知症患者 ・ 佐藤雅彦さんへの縁でもあり
ますので、書店での立ち読みの際お役にたちますように「I T機器を自身の分
身として」 の頁を記しておきます、P191。