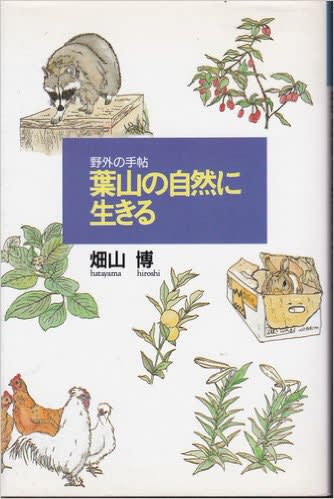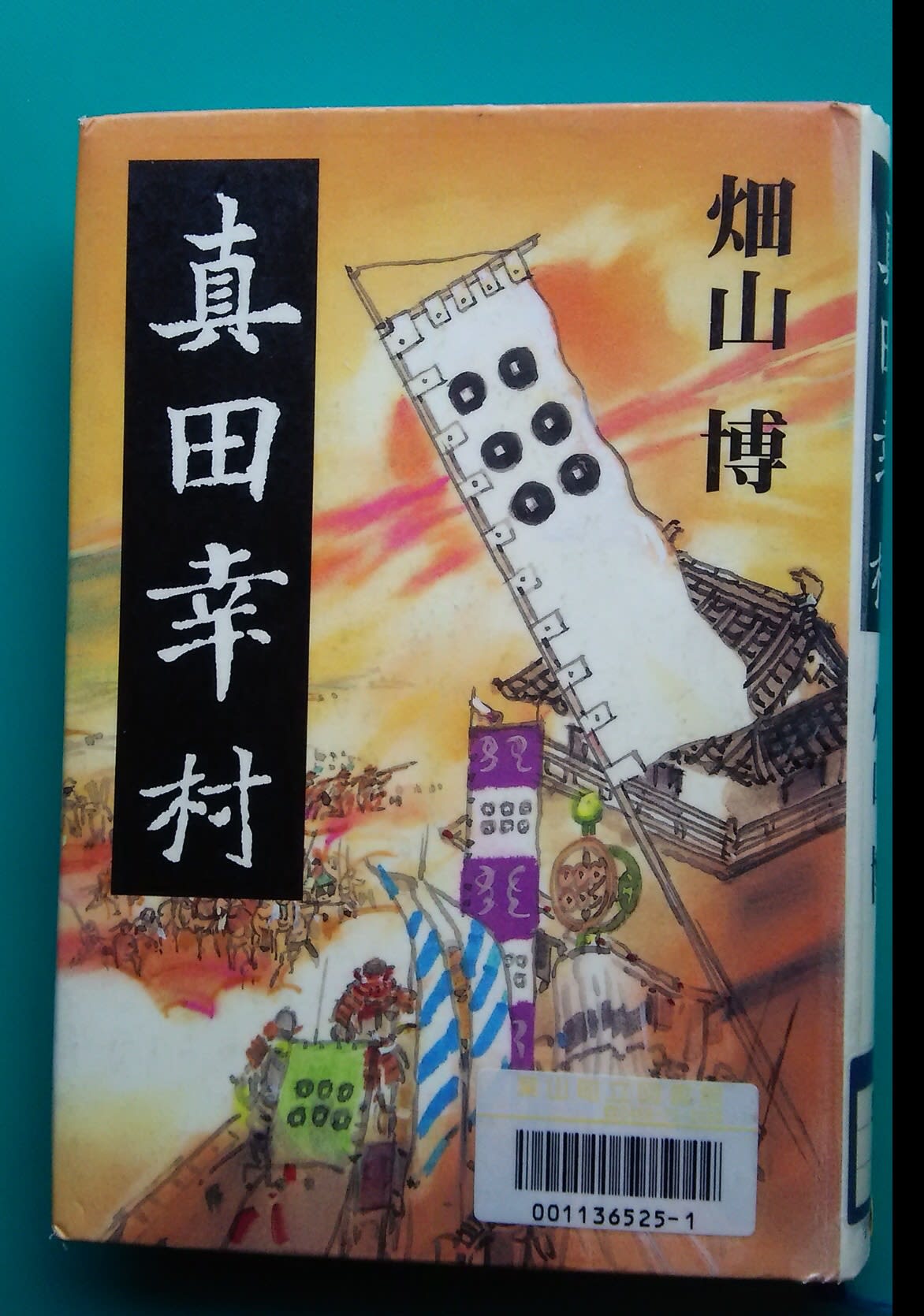上田城築城との関係で「天正十一年八月二十四日」が気になっています。
まずはこれです、昨日一昨日と「つぶやき」に記しました「真田丸」の時代考証担当の一人平山優さんの「天正十一年八月二十四日」です。
「天正十一年(一五八三)八月二十四日、家康は上田城を昌幸に与えた」と見えます。

次はこれです、

『地形で読み解く「真田三代」最強の秘密』(著者・橋場日月 朝日新書)の上田城築城に関わる頁です。中ほどに「工事が八月二十四日からはじまって~」と書かれています。ここでは天正十一年と年は記されていないのですが、文の前後からみて「天正十一年」といえます。
この二つの「天正十一年八月二十四日」の元の出どころは同じなのでしょうか。橋場さんの本には『真武内伝』という史料が見え、この日付はその史料によると読めます。平山さんの日付については史料は書かれていません。
上田城を「家康が昌幸に与えた」日と「工事をはじめた」日が同じ日だとすると、「家康が昌幸に工事開始の許可を与えた」とも読めます、がすると『真武内伝』に見えます「(家康から)上田城を給ふ」というのと合いません、なかなか面白いです。
さて、もうひとつの「天正十一年八月二十四日」です、その時家康は何処にいたか? 甲府です。
「家康の軌跡」というサイトに「8月24日、再び甲府に入り」とありました。

こうしてみると遥か昔のある一日も色々な色彩を帯びて見えます。
2916年3月15日という一日がどんな色彩を示しているのか、これから小父さんの所へ奥さんの月命日ですのでお線香をあげに向かいます、夕食を共にしイッパイ機嫌になってきます、いい色彩です、夕焼けです。