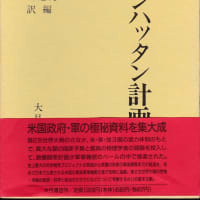三国志 魏書東夷伝中に倭人名は多く記されていながら、卑弥呼の墓の記述があるほかは、魏から官爵を与えられた倭人が、卑弥呼の墓とともに、(初期)古墳に埋葬されているという発想はなかなか、直接的に結びついてきたわけではなかった。その点、東潮は『邪馬台国の考古学』で大胆かつ魅力的な世界を描きだしたように思える。 考古学の成果を語るのに安易に文献に寄りかかってはいけないということ。また一方文献的な探求は、自説に有利な部分の補強のためだけに考古学の成果を使用してはならないということを理解した上で、歴史叙述する可能性を探るのは、意味のないことではあり得ない。 その点、東潮は中国・朝鮮考古学・古代文献史にも、日本考古学にも通じている。 「難升米は黒塚古墳の被葬者であった」のではないかと、この著で披露している。これが考古学的・文献史的な共通理解として研究者間に納得得られれれば3世紀後半の一定点として、古墳時代の開始問題や、初期国家像のフォーカスが合ってくるはずである。 まずは、魏から難升米が受け取った黄幢は、どのように考えればよいのだろうか。
難升米のもらった官爵について
三品彰英 編著の『邪馬台国研究総覧』1970年 創元社 の注解がよくまとまっており、参考になると思われるので引用する。
率善中郎将
中郎将とは交代で宿直して宮城を護衛する武官の長である。この職は、秦代に、始まり、宋代以後には廃止された。秩は比二千石。中郎将は郎中令に属し、五官・左・右の三中郎将が常置であるが、必要に応じて種種の「雑中郎将」(例えば匈奴中郎将・建義中郎将等々)が任命された。率善中郎将も、この「雑中郎将」の類に属する。
率善の意味について、志田(不動麿)は中国の勢力を承認した蛮人の勢力者に対して帰義候の官名を与えた例が見られるから、率善の場合も、この帰義とほとんど同一であろうとしている。なお中郎将に任ぜられるのは原則として内臣に限られており、難升米の場合はむしろ例外と考えてよい。『邪馬台国研究総覧』139頁
栗原は、難升米への賜幢を 下記のように考えている。
まず、幢を、『後漢書』の班超伝にみえる李賢の注には「鼓吹・幢麾、皆大将所有」とあることを確認、諸橋『大漢和辞典』の、軍の指揮に用いる「はた」(はたぼこ)であるとしている。
「幢が軍旗の一種であり、少なくとも唐代には、将軍・刺使の威儀を示した儀飾の一つであったと理解されていたことがわかるが、これは正しい解釈のようである」としている。
これには、そんなに異論はないのではないだろうか。
一番古い軍旗としての幢の記録は、栗原の探したものでは、『漢書』の韓延寿伝 という。
漢の宣帝のとき、延寿が東郡太守として在任中、都試の際に幟を立ててこれに臨んだころが記述されている。ところが、自分が考案した各種の儀飾りが、反対派によって劾奏されて、「棄市」という極刑に処せられてしまったという。問われた罪が、幟を立てて都試に臨んだことだというのである。
したがって 幢 は、王権の権力行使や軍事権に関わる重要なシンボルとしての意味をもっていることが考えられるのである。
内臣以外の賜幢の例としては、泄帰泥 に与えられたものが一つだけあるようである。 部族をひきいて、魏に帰属した泄帰泥にあたえたものである。
「曲蓋・鼓吹を与えて、元通り住まわせ、鮮卑族に対抗させた」という記録である。
日本語訳 は『三国志』 魏書 烏丸鮮卑東夷伝『世界古典文学全集24B三国志Ⅱ』筑摩書房 (現在は筑摩文庫にも収録されている)291頁にある。
武田幸男 の黄幢の見解
さて、武田幸男は黄幢拝受の頃を以下のように記している。
中央公論社版『世界の歴史6 隋唐帝国と古代朝鮮 第2部朝鮮の古代から新羅・渤海へ』1997年 (中公文庫版は2008年刊 332頁~336頁)
「魏は倭の難升米に黄幢授与することにした。「幢」というのは、袋状の軍旗であり、「黄」色陰陽五行説にいう五行の一つ、魏の土徳を意味していて、黄幢は魏の軍事力を象徴した。黄幢の授与を通じて、魏は軍事的連携をはかったのであろう。おりしも、魏の高句麗攻撃が最高潮にたっし、母丘倹が東方世界を制圧しかかっていたころである。帯方郡が黄幢を届けるまで三年かかったのも郡自体が作戦の展開中だったからである。
難升米は魏が注目し、高く評価した人物であった。卑弥呼が男弟一人を頼りに神聖統治の宗教的な統括者として振る舞う中で、大夫の難升米は行政実績があり、すでに外交手腕も認められて、世俗面を代表する重鎮であった。魏は外交辞令だけで、率善中郎将に任じたのではなかった。今度は、外臣としてのかれに、軍事的な指導性が期待された。女王国は、魏の東方戦略に組み込まれていたのである。
さて第四回め、卑弥呼最後の遣魏使は247年、帯方郡にむけて、急使が派遣された。これまでも不和だった隣の狗奴国の男王、卑弥弓呼との間で、戦争が始まったというのである。帯方郡は敏感に反応した。前々年までの高句麗遠征、前年の諸韓国の反乱、辰王の討滅作戦が終了したばかりである。すぐ、張政らが派遣された。張政は郡庁に留めおかれていた例の黄幢をもちだして、ようやく難升米まで届けられた。
張政はまた、檄文(軍事司令書)を与えて叱咤激励したという。
卑弥呼の軍団に外国人の軍事顧問がついたのである。黄幢の軍事的意味あいは、当面、卑弥弓呼の打倒に向けられていたはずである。結局、張政が翌248年に還ったところをみると、それが少しでも効いたのかも知れない。」
さすが、武田幸男、うまいなあ
それにしてもこの時代の三国(魏・呉・蜀)燕・韓・倭などの外交交流術あるいは権謀術策というか、正史の行間などを読みこんでいると、現代の東アジア情勢や、世界政治は、とても民主主義の世界とは思えず、古代のパワー・ポリテックスの無理難題と少しも変わらぬ姿であることに改めて驚愕する。
これまで、卑弥呼の倭国を考えるとき、どうしても魏との関係史が中心であるが、この頃、蜀は234年に諸葛亮を陣中で失い、衰えをみせはじめる。魏は西方への軍隊配置の軽減を考えられるようになり、公孫淵政権の打倒や、韓半島への勢力拡大に振り向けるようになる。
先の栗原の黄幢についての見解の紹介で脱落していた重要な指摘に、呉が、公孫淵に与えた詔書の件があった。
三国志 呉志の 注で、裴松之は「江表伝」を引用しているところの記述である。呉王の孫権が公孫淵に送った詔書のことである。公孫淵を「燕王」とするとともに、「戎事あれば兵馬の「典蓋・麾幢」を与える」記されていることである。
呉にとっても、周辺国に対して与えられる幢は王権の軍事政策にとって、詔書中の 策書 とともに重要なものであることが知られる。
さて、
「赤烏七年は、244年で、公孫淵政権は滅びて存在していない。この紀年銘年号の鏡はなぜ、どこで作られたのだろう。
山梨県鳥居原古墳出土 画文帯神獣鏡は238年の呉の赤烏元年。
兵庫県安倉古墳の画文帯神獣鏡の年号は赤烏七年、244年である。
これらの年号鏡の年代は卑弥呼の晩年の時代に重なり、また呉が背後から魏を攻略するため支援しようとした公孫淵の滅亡があり、呉が新たな軍事・外交の見直し・模索が開始された時期でもある。
日本の中小の古墳の主体部から、今後、赤烏年号や呉の年号鏡ももう少し発見される可能性もあるのではないか。また、政治的な目的以外に交易・商業という交流も呉との間にあった可能性も考える必要性もある。
263年(蜀の滅亡(魏の景元4年)
265年、晋の建国
266年、倭人が晋に朝貢280年、呉の滅亡。晋の中国統一
邪馬台国から倭国・初期国家への探求において、銅鏡の考古学的探索も重要であるが、『三国志』を、「魏志倭人伝」の項目だけを参照するのではなく、呉・蜀の関係や戦況の動向も読み解く必要があるようだ。
魏の倭国への特別な待遇は、魏・呉・蜀 三国の壮絶な戦いのゆくえに深く関連しているのではないかと考えるに至った。
東潮の『邪馬台国の考古学』は さあこれで、解決だ!
難升米は黒塚の被葬者だ とだけ言っているわけではない
東潮の「『三国志』の夷狄思想から脱却してはじめて、里程論の呪縛からときはなたれるはずなのだ。」というのは正しい。と考える。
前提の前提を深く疑え!
東潮の『邪馬台国の考古学』あとがきによれば、牽牛子塚の見学の帰り、森浩一先生のひとことに「魏志東夷伝の考古学」の執筆を期した。とある。
森浩一さんは読んでどんな感想をも持っているのだろうか。ぜひ読んでみたいものだ。
そういえば
森浩一編の著で、『倭人伝を読む』 1982年 中公新書665 があった。出版されてすぐに面白く読んだ記憶がある。もう30年前に発行したものだ。時のたつのははやいが、わたしの 知 がいっこうにそのころから深まっていないことに気がつく。
開発がらみの発掘調査で忙殺されるのを理由に、メモもとらず、読みっぱなしだったのだろう。
この本の中で 執筆者となっている森博達が「三世紀倭人語の音韻」を書いている。このときは、古代史をやるのに、音韻論もやっておくといつか、役にたつかもしれないと思っていたのだが、同じ森博達の『日本書紀の謎を解く』1999年中公新書 を読むに至って、おもわずうなってしまった。これはすごい!これは日本史研究上の世紀の大発見だ。「ユリイカ」だ。「われ発見せり」だ。森博達は自分でこう叫んだはずだ。
稲荷山鉄剣銘文も、言語学的・音韻論的にも森博達のように解釈できるわけで、古代史は、さらに精緻で・科学的に理解可能となるはずだ。
もう一度、学生時代に読んだソシュールや、ヤコブソンを手がかりに、中国の古代音韻の基本を学び直す必要があるようだ。とにかく時間の変化を識別できる「弁別可能な音素」のようなものにまでたどりつかないと、考古学の遺物においても説明可能な説得力のある編年基準の変化の要素を抽出できないわけだから。
言語学的手法を通して、宋書の中の倭王名と、日本書紀における天皇名を相関させる方法はないか。大王とされる古墳の比定もまだままならないが、天皇の実在の真偽もあるのだが。
この項続く