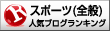漱石山房記念館(新宿区早稲田南町)
夏目漱石が晩年の九年間を過ごした早稲田南町の旧居は「漱石山房」と呼ばれ、今は「新宿区立・漱石山房記念館」として、漱石に関する詳細な資料を展示してあります。館内の展示順路標識は「吾輩は猫である」から猫が案内しております。
展示物の資料の中には、執筆原稿の実物や出版本などの他、幅広い交流人物についての説明があります。漱石の実寸大の模型のところは撮影ができます。
漱石山房記念館は、新宿区が建設したものです。建物の前の道はきれいに整備されており、周りは珍しい植物が植えられております。裏手には漱石公園となっており落ち着いた雰囲気が醸し出されていました。
夏目漱石生誕地(新宿区喜久井町)
夏目漱石は、慶應3年(1867年)新宿区喜久井町で生まれました。
裕福な家庭で父親は前を通る坂道を夏目坂と付けました。
17歳のときに正岡子規と出会い文学的影響を受け、23歳で東京帝国大学英文科へ進み、卒業後は英語教師となり、英国留学後、同大学の講師となっております。
執筆作品には「吾輩は猫である」が評判となり、作家としての道を歩みはじめ「坊ちゃん」「三四郎」「それから」などがあります。
その漱石の生誕地は、今は定食食堂となっていて、店の前に生誕碑と漱石の句碑があり、脇には説明書が建っていました。
その生誕地から10分ほどのところに夏目漱石がその生涯を閉じた場所には、漱石山房記念館があります。
酒粕・味淋粕にこだわり、漬ける素材にこだわり、納得のいくものだけを提供する鈴波の味。
イケバスを活用して豊島区内の4ヶ所(池袋駅西口えんちゃん広場、目白駅前広場、サンシャインシティ南入口、大塚駅南口トランパル広場)を巡回しました。
司会はお馴染みの城所信英さんです。音楽をはじめ幅広く知識を持っている方なので説明がとても分かりやすいです。
出演者は、ケン・カタヤマ(テノールアーティスト)、知久晴美(ソプラノ・ハモローザ)、下澤明夜(ソプラノ・ハモローザ)、シェーンパトウ(サックス)、宇津木あい(ヴァイオリン)、高梨雄太郎(シャンソン)の皆さんです。
演目は、フニクラフニクリ、未来、パリの空の下で、オーソレミオ、銀河鉄道999、オーシャンゼリゼです。素晴らしい歌唱を堪能しました。
電気仕様のイケバスを活用して、マイク、音楽スピーカー等の電源を接続しています。災害時でも活躍するイケバスはとても機能的な電気バスとなっております。


庭園に流れる瀧の源流となっている湧水は、古くから「延命の水」として親しまれ、昨今はパワースポットとして注目されている。新緑、紅葉の時期はひときわ見事な景観が見られる。
歌人・与謝野晶子もこの瀧の風情にふれ、「山荘へ 玉簾の瀧流れ入り 客房の灯をもてあそぶかな」と歌に残している。
山本亭の庭園
柴又にある山本亭(東京都選定歴史的建造物・葛飾区登録文化財)の特徴は、近代和風建築と純和風庭園が見事に調和しているところです。
庭は、面積こそ著名な庭園に比べ小さいものの、その狭さを、奥に滝を配して奥行きを持たせ、池の岸にアクセントをつけて広がりを持たせルなど、日本の伝統的な庭造りの工夫が見られます。米国の日本庭園ランキングでは、3年連続第3位に選ばれています。
和室の花の間から見る庭園が一番美しく、抹茶やコーヒーを飲みながら懇談しているグループがおりました。この日は、庭園では雪つりの準備をしているところでした。雪の積もった庭園もまた趣があることでしょう。
井の頭公園の七井橋
井の頭公園の井の頭池はY字型になっていて中央部分を「七井橋」が通っています。
三鷹市牟礼に住んでいる人たちが歩いて吉祥寺に来るときに利用する人も多くおります。
この七井橋はなかなか池との調和があって風情があります。
子供の頃は木橋であり、その頃は名称は付いていなかった。コンクリート橋にリニューアルした時に「橋の名称」を公募していました。小学時代の時ではがきに書いてで応募したことを思い出します。今の橋はさらにリニューアルした最新の橋であります。
七井橋の由来は、井の頭池は湧水で池の水が満たされています。池に湧き出す場所が七つあるところから七井橋と命名されました。
池の水面すれすれのところに渡してあるので、水鳥や池の中の鯉や魚が近くで見ることが出来ます。
七井橋から見る公園の景色は昔とあまり変わっていないところがとても良いです。そして懐かしく昔の思い出を蘇らせてくれます。
男滝(名主の滝公園)
「名主の滝公園」は、王子駅から徒歩5分のところにとても静かな場所にあります。
江戸時代、王子村の名主、畑野孫八が屋敷内に滝を開き、茶を栽培して避暑のために一般に開放したのが始まりで、名前の「名主」はそこに由来します。昭和50年からは北区に移管され管理されています。
園内は回遊式の庭園となっており、男滝(おだき)、女滝(めだき)、独鈷の滝(どっこのたき)、湧玉の滝(ゆうぎょくのたき)の4つの滝があります。
男滝は豪快に流れ落ちいつまでも見飽きないです。滝から流れた水は小川となって園内を巡り大小の池に注いでいます。入場料は無料。
近くには王子稲荷神社もあり、入口のところは王子稲荷の坂という急な坂道の途中にありました。この界隈は散歩をするにはいい場所です。
始めに10月27日に開催されたTAMC「マジック発表会」を観覧した人から感想が述べられました。大きなステージで演ずるマジックの醍醐味に感心をした。クロースアップのプログラムがスクリーンで投影されていたことは素晴らしかった。大トリの和の世界の演技がダイナミックで見事でした。
12月のマジック教室は特別ゲストを招聘していることの案内がありました。
研修は「ロープとシルク」でした。シルクのほどけ結び、ネクタイ結びシルクの離脱、シルクの偽結び(フォールスノット)、ロビンスの結び目、シルクとロープのペネトレーション。最初は難しいようでしたが慣れてくるとスムーズにできるようになりました。いろいろの種類があるので楽しんでいました。
トランプカードでは、4枚のカードを半分に切って組み合わせる方法、同じくカードによる恋占いの方法、そしてごちゃまぜ予言、嘘の切り方などを研修しました。


ロープのネクタイ結び離脱 ロープとシルクの研修
三定の「天ぷら料理」
浅草の雷門の横には、天ぷら料理の老舗「三定」があります。「一に浅草、二に観音様、三に三定」のキャッチフレーズで馴染みのお店です。
お店に入り「天ぷらご飯」を注文。魚の白身のキス、大きな海老、小エビと貝柱のかき揚げなどが盛られております。天ぷらは軽く揚げられているので美味しさが増します。
霞会散策会で「三定」を訪問した時に、真田優七代目会長(TIU同窓生)から天ぷらの歴史と知識について聞いたことがありました。とても参考になりました。また、天ぷら料理では油を使用するので、絶対に火事を起こしてはならないと、いつも緊張感をもってお店のビル上階に家族とともに生活をしているとのことです。
老舗の理念とこだわりが、料理の天ぷらにも伝わっておりとても美味しく味わいました。
川越の菓子屋横丁
色とりどりのガラスが散りばめられた石畳の道に、20軒程の菓子屋などがひしめく川越の有名なスポット「菓子屋横丁」。 素朴で昔懐かしい味を今に伝える菓子作りの店が立ち並び、一歩足を踏み入れると、誰もが子供に返ったような気分になってしまう。
醤油の焼ける香ばしい香り、ニッキやハッカ飴、駄菓子やだんごなど、昔ながらの手法で作られる飴菓子・カルメ焼きなど、思わず「あっこれ!」と言ってしまう駄菓子の数々…。誰もがワクワクしてしまうような場所であります。
「菓子屋横丁」は明治の始め頃、鈴木藤左衛門が養寿院の門前町として栄えるこの町で江戸っ子好みの 気取らない菓子を製造したことが始まりといわれている。
その後の大正12年、関東大震災によって被害を受けた東京に代わって製造供給を賄い、昭和初期には70軒以上の店があったといわれている。人情味あふれる横丁の情緒、威勢の良い呼び込みの声、素朴で懐かしく温かい街角は、時代が変わっても人々に安らぎを与えてくれる。
「菓子屋横丁」に漂う素朴で懐かしい香りは、平成13年環境省の“かおり風景100選”に選定されました。