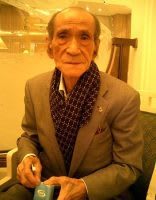武道館の入り口では検温と手の消毒を行います。大会会場には競技種目に出場する選手のみが入り、出場待ちの選手たちは第二武道場で練習をしながら待機していて出場種目の開始を待っています。会場にはいたるところに消毒液が配置されており、また競技が終了するたびに試合場の畳の上を消毒して清掃しています。このような中で競技進行を行うのは初めての試みです。
競技中も選手はマスクを着用しているのでとてもやりにくそうです。その中で中堅組の選手の活躍が目立ち優勝メダルを獲得していました。金子智一選手(男子実戦競技)。名倉崇広選手(男子法形競技)。山際真穂選手(女子実戦競技)。稲見安希子選手(女子法形競技)。表彰式ではメダルを受け取り自分で首に掛ける方式となります。今大会の出場選手はコロナ禍のために遠方からの参加が少なく例年のような社会人優勝大会の盛り上がりに欠けていました。
全国社会人躰道優勝大会のみに贈呈される「最高師範杯」は、金子智一選手に贈呈されました。その他の三賞は、殊勲賞に山際真穂選手。敢闘賞に稲見安希子選手、技能賞に名倉崇広選手が受賞しました。
コロナが早く収束して、多くの選手が出場出来て通常の全国社会人躰道優勝大会が出来ることを願っております。
(9月21日記)
(2007年5月3日)
今年の全日本選手権大会に出場した愛知県選手は、実戦競技では油井陽選手は2位、団体戦は3位、女子の部では平山愛子選手が3位に入賞と立派な成績を挙げております。法形競技出場の佐々木秀彰選手、壮年法形競技に出場の浅岡宏選手も毎回出場をして頑張っています。
山本清隆師範は、大学で教職課程を取得して小牧市の中学校の英語教諭として赴任をした時に、街に掲示してあった躰道の会員募集のポスターを見て藤丸英雄師範の小牧道場へ入門をしました。その時のポスターは祝嶺正献最高師範が撮影してくれた私の飛燕突きの術技の写真であったと話してくれました。
山本清隆師範は「躰道創始者・祝嶺正献最高師範を通して思い出すこと」と綴った資料を書いて持参して渡してくれました。祝嶺正献最高師範が愛知県の演武会や審査会に来てくれたことの模様が詳しく記述されておりました。また、厳しさについては今でも参加した人の語り草となっている静岡県清水で開催された「指導者合宿研修会」の模様や「躰道概論」の挿絵は山本師範の門弟である美術学校の先生が描いて祝嶺正献最高師範にはとても満足をしてもらったエピソードなどが掲載されていました。
その後、小牧市で話題のお店「めりけん堂」の具だくさんのジャーマンスパゲッテイをご馳走になりました。子宝の恵まれるご利益のあるとテレビで報道される奇祭の行われる田縣神社、そして国宝犬山城を案内してもらいました。(2017年12月13日)
全国少年少女躰道優勝大会で小松優選手の健闘ぶりが注目を浴びていました。小松優選手は宮城県気仙沼市の大島小学校で躰道を修練しております。父親の小松 武さんと母親の小松万里子さんとも躰道の指導者であり、子どもの頃から環境に恵まれたところで稽古を重ねてきました。躰道の宮城県大会や東北地区大会での優勝実績もあり、全国大会でも有望選手としてシードされていました。
法形競技ではシード選手として2回戦から登場し、3対0で勝ち上がり、3回戦、4回戦も完勝して決勝戦でも3対0で文句なく優勝しました。実戦競技ではポイントは先取して勝ち上がり、決勝戦でも完勝して見事に優勝を勝ち取りました。
褒章授与では全出場選手の中から「優秀選手賞」の栄誉を獲得しておりました。小松優選手は今後も活躍が大いに期待される選手です。(2019年8月6日)
中学校の英語教諭として生徒の指導に尽力してきたが、定年勇退後も躰道の指導は継続している。躰道は、創始者である祝嶺正献最高師範及び藤丸英雄先生から指導を受けて、精進を重ねてきた。今は愛知県小牧市の篠岡中学校(月曜日)、味岡中学校(水曜日)の各武道場で2カ所、そして愛知県江南市武道館(金曜日)で指導している。躰道を稽古すると、護身術、健康法も身につく。いい汗を流すことができる。
山本清隆さんは、今年4月から中日新聞主催の躰道講座を名古屋の中心・栄の中日ビルで、第2.4の日曜日(10:00~12:00)に開催している。このことは中日新聞より取材を受けて、写真入りの大きな記事が掲載された。「旋技は、半身に構えた状態から素早く前後の足を交えて体をこまのように回す。捻技は両脚で相手の胴や脚を挟み、ひねり倒す。いずれも相手のくり出す技をかわしながら懐に入り攻撃する動きです。『我動く故に我あり』いろいろと組み合わせを考えるのがとても楽しい」と話す。(2010年4月22日)
祝嶺正献最高師範のお墓参り
祝嶺正献最高師範の命日に今年もお墓参りに行ってきました。伊東駅には長女である齋藤育代さんが出迎えてくれました。いつもの花屋でお花と線香を購入してから、高台にあるお墓へ行きました。そこからは伊東の港と市街が眼下に広がります。遠方には初島が見えます。
お墓を清掃してから、花を手向けて線香をあげ、近況を報告しました。今年は新型コロナの影響で、全日本躰道選手権大会をはじめ、全国学生大会、全国社会人大会、全国少年少女大会などのすべての大会が中止となったこと。最高師範から直接指導を受けた高弟の優秀な指導者たちが亡くなったことなどを報告しました。
その後、齋藤育代さんの案内で和食海鮮処「花季(はなごのみ)」で鮪の漬け丼を食しながらの懇談のひとときを過ごしました。話の内容は、玄制流空手道、躰道を創始した祝嶺正献最高師範について、その精神と理念を現在修練している人たちにどのように繋いでいくことができるかが主題となり、資料をお渡ししました。
帰途に乗車した特急「サフィール踊り子号」は全車両グリーン席の特別仕様の列車であり、快適な乗りこごちでありました。
(11月28日記)
板山徳子審判員
躰道の優勝大会では審判員は重要なポジションを司る。審判員は、全ての法形を理解していることは勿論のこと、実戦競技での直視判断と所作を選手や観客から見られている。
審判員の中で特に光り輝く審判をするのが板山徳子審判員であります。板山徳子さんは、秩父女子高校で躰道部を創部させた一期生であり、板山昌司先生の指導を受けて躰道の稽古を重ねてきました。その後、縁があって板山昌司先生と結婚をして、妻として躰道普及の補佐をしてきました。山梨県北杜市長坂町で板山昌司先生が建設した山梨正統館道場では、女子部と少年部の指導を担当しています。板山昌司先生の勤務先である帝京第三高校躰道部の生徒たちの面倒もよくみています。息子の板山宜弘さんも立派な躰道マンとして育成しました。
板山徳子審判員は、実戦競技において、ポイントが入ると素早く的確に所作を施します。判定の場合でも、選手はもとより観客にもはっきりと分かる内容で説明を行います。審判員は、正統なる実技を習得してこそ、選手の競技を導いていくことができます。板山徳子審判員の判定は、誰もが納得する分かりやすい説明が特徴であります。そして、妻として、母として、指導者として躰道の普及に尽力している人です。
(10月31日記)