今日は水戸の藩校「弘道館」の名前のところ
衛霊公十五ー29

子曰く
人能く道を弘む
道人を弘むるに非ず
安岡定子先生
よき人物が道を切り拓いていくものなのです。
道が人を弘めてくれるものではありません。
実は昨日から考えていた~
まず「弘」
漢和辞典を引くと「肘を大きく弓をひく」そのときの
人の状態とある
「ピューンと大空に向かって矢を放つ瞬間」
そんな感じかな

だから「ひろい・ひろし・ひろむ」と読む
私の友人・先輩にも「道弘」「弘」という名前の人がいる
この名前の由来はここにあるのでしょうね
さて、「道」ですよ
これを昨日から考えていました

老子の世界では「タオ」
日本では武士道、茶道、華道、剣道、柔道
どの世界でも「道」がつく
それほど日本人が大切にしている「道」
白川静先生の「常用字解」を引くと
首とシンニュウ(パソコンでは出ません~~)
シンニュウは歩く・行くの意
首を手に持って行くという意味で
邪霊を祓い清めて進む、その祓い清めたところを
進むことを「導く」といい、祓い清められたところを
「道」という解説である
清め祓めたるところが「道」
では具体的にこの道に至るのは・・・
それを考えていたら安岡正篤先生の「思考の三原則」を
思いついた
「思考の三原則」
一、目先にとらわれず、できるだけ「長い目」で見る
二、一面ではなく多面的に、できれば全面的に観察する
三、枝葉末節に捉われないで「根本」を見る
「道」に至るのはやはり具体的にならねばならないが
こりゃあ~なかなか、私には高いハードルじゃね

定子先生の道を「切り拓く」という言葉は
ここら辺にあるのかもしれない
道に至るのは「自分であり」「切り拓く」
そんな声が定子さんから聞こえてくるような気がする
「切り拓く」
さあ~わたしもボチボチ道々ゆっくりと
道「切り拓いて」みようかあ~~












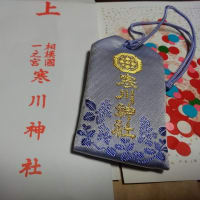







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます