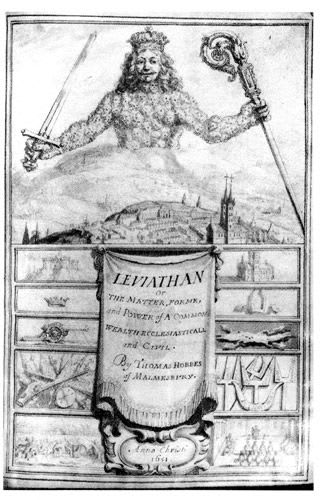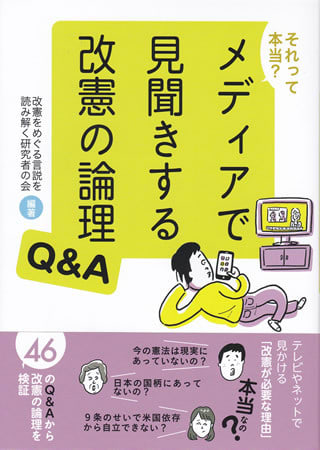
正直に言えば(そして私の記憶が確かであればだが)、Q&A本を隅から隅まできちんと読んだのはこの本が初めてである。Q&A本というのは知識の穴を埋めるために、必要な項目を拾い読みすればこと足りると思っていたし、私の本棚にもそのような種類の本は見当たらない(そんなにたくさんの本を持っているわけではないが)。
この本を隅々まで読んだことには、もちろん理由がある。一つは私自身の問題である。私は1945年8月15日を母親の胎内で迎えたので、まるまる太平洋戦争後の時間を生きてきた。子どものころから憲法の話は聞いたし、それなりに本も読んだ。そして、憲法を改めたいという反動的な動きに反対してきたつもりである。つまり、日本国憲法についてそこそこ知っていると思っていた。それが最近怪しくなってきた。自公政権が国会で3分の2以上を占め、改憲の動きが急になってきたことばかりではなく、憲法成立時の過程についても新しい事実が明らかにされてきたこともある。もう一度くらいは、憲法をめぐる私の認識の点検をしておく必要があると考えている時期でもあった。
もう一つの理由はこの本自体にある。本書はQ&A本には違いないが、メディア・リテラシーについての本でもあって、とても興味深い構成になっている。まず、憲法に関するメディアの言説(談話)が取り上げられ、それを見聞きした一般の国民(私のように憲法やメディア・リテラシーに関して専門的な知識を持たない)が抱くであろう疑問や反応を設定し、それに答えるという形になっている。特徴的なことは、一つのメディア言説に1~3の質問(疑問)が誘起され、さらにそれぞれのQに必ず異なった論者による二つの回答(A)が与えられていることである。
一つのメディアの言説への人々の反応、受け止め方は多様であるだろうし、そこから生まれた疑問への回答もまた単一ということはないだろう。この本書の工夫は、読者に親切なちょっとしたアイデアのように見えるが、私には知に関するたいせつな見識が盛り込まれているように思える。
真実は唯一つという信憑が一個だけの正解が求められる試験制度へ強く依存する学歴格差社会、競争主義社会で培われてきたということはしばしば耳にする指摘である。そのような受験システムを持つ日本や韓国にありがちな考え方だとする説もあるが、ことはそれほど簡単ではない。
世界(社会、自然)のもろもろの物象(事象)にはそれに照応するイデーが存在するというプラトン流の考え方は、デカルトに始まる近代的自我の時代にも連綿と受け継がれてきた。しかも、その真実または真理は、ヒューマニズム(人文主義、人間主義、正しくは人間中心主義)によって偏光された視線によって形作られてきた。
ポストモダンの思想家たちは、いわゆる〈脱構築〉的思考法によって絶対的価値、絶対的真理の相対化を図った。それは、判断停止や思考停止をもたらす俗流相対主義を生み出す元ともなったが、真実の多義性や歴史的・社会的構造性を指摘する豊かな思想の始まりだったと私は考えている。ヒューマニズム(人間中心主義)批判もポストモダン以降の思想の主要な課題であることは、ジョルジョ・アガンベンやジャック・デリダの仕事などからも窺える。
そのようなポストモダン以降の思想の展開は、ウォーラーステインが語る〈1968年世界革命〉と照応する。世界同時的に発生した〈1968年世界革命〉は、少なくても「大きな物語」の終焉としての「革命論の革命」であったことは間違いない。正統派マルクス主義が標榜していた「一国社会主義革命」は乗り越えられ、複雑な資本主義世界システムのなかの位置取りに応じた多様な民主主義革命、つまりは古典的な発展段階論ではない各国家の世界システムにおける位置、地域社会の歴史・経済の固有性に依存する多様な革命論が追求されるようになった。
こうした事柄は、けっして真実は曖昧であるとか多様性によって真実が失われたということではなく、真実は構造的多様性を持つものだという考えなのだと私は受け止めている。真実は多面体であって、真実を求める複数の主体が向ける眼差しには複数の面が顕われ、それぞれの面は構造的に切り離しえないものだ。「真実は一つ」というより「真実は多様な一体」とでも例えればよいのではなかろうか。
本書のような一つのQに複数のAという思考の進め方を教育の現場(それは学校であり家庭でもあるが、柳田国男の言う〈世間〉そのものと言った方がよいかもしれない)でごくごく普通に行うことができたら、私たちの「知」の展開はもう少し異なるものになるだろう。ガチガチに練られた方法論ではなく、本書のようにさりげなく普段着のように取り入れられるのが理想だろう。大げさだが、それこそがポストモダン以降の思想的営みの現実的な効用と言えるのではないか。本書を読みながら、そんなふうなことを考えた。
メディア・リテラシーと憲法論の融合した本書の執筆陣は、当然のことながら石川裕一郎、稲正樹、木部尚志、中村安菜の憲法学、政治学を専門とする4氏と、神田靖子、名嶋義直、野呂香代子の言語学の3氏である。構成は、「憲法改正ということについて」、「自民党改憲草案(2005、2012)をめぐって」、「改憲勢力各党の提案」の3章から成っている。
例えば、「自民党改憲草案(2005、2012)をめぐって」のなかに次のような言説が示されている。
【言説11】
憲法9条の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という規定は自衛隊を軍として明確に位置づけていない。これに関連して、自衛権についても抑制的に解釈され、防衛政策や防衛力の充実は制限されてきた。しかし、自衛隊の存在をあいまいにしておいては自衛隊員が気の毒だし、防衛費は「国民の生命を守るための予算」である。自衛隊の存在を憲法に明記し、隊員の名誉を保証する必要がある。 (p. 58)
この言説を基にして、二つの疑問(質問)が挙げられている。
Q1 日本の防衛費はかなり高いと聞いたことがありますし、年に何回もハワイやタイなど外国に行ってアメリカ•韓国をはじめ諸外国と一緒に大規模な軍事演習にも参加しているとニュ—スで報じていました。「防衛政策や防衛力の充実は制限されてきた」というのは本当ですか。 (p. 58)
Q2 自衛隊員は「自衛隊は軍隊ではない」ということを知って自ら志願して自衛隊に入るのですから、何が「気の毒」なのかよくわかりません。軍隊でないと「名誉」ではないのですか。 (p. 60)
ここでは、後者のQ2に対する二つの回答を例示しておく。
A1 名誉・不名誉という感情を根拠にして改憲を主張することは危険
ここでいう「名誉」には2つの意味があると思います。1つは自衛隊が軍隊でないという「不名誉」です。新聞記事の中で、「海外の軍隊と共同訓練をしているときに自衛隊が軍ではないことに引け目を感じる」という自衛官の発言を読んだことがあります。自衛隊関係者の中には、軍隊ではないことを誇りに思うのではなく、中途半端で不じゅうぶんであるという劣等感のような感情があるようです。
もう1つはいわゆる「名誉の戦死」的なものです。これも数年前に聞いた国会中継の中で元自衛隊員の議員が、自衛官が海外でPKO活動という重要な任務に就くのだから死んだときにはそれ相応の処遇が必要であると述べ、弔慰金の増加を求めていました。2016年11月6日の新聞報道によると南スーダンのPKO派遣に関して政府は弔慰金の引き上げは行わないものの、新たな手当を付与するようです。
自衛隊が軍隊でないことを不名誉と感じたり、その職務上の負傷や死を名誉と感じるかどうかは個人的にさまざまな受け取り方があってよいと思います。しかし、個人的に差がある情緒的な想いを根拠にして改憲が必要だと主張することは非常に危ういことです。気の毒とか名誉とかいつた情緒面ではなく、しっかりとした根拠をもとに議論すべきです。 (pp. 60-1)
A2 自衛隊員の名誉と命が天秤にかけられ、憲法改正に利用されそう
広辞苑によると、名誉とは「よい評判をえること」や「人格の高さに対する自覚、道徳的尊厳が、他人に承認・尊敬・賞賛せられること」です。自衛隊で働くことに関する自衛隊員の方たちの考えはわかりません。しかし、自衛隊を憲法で明記することが彼らの名誉とどのようにつながるのでしようか。憲法は、議会制民主主義を前提としつつも、政党について規定していませんが、政党に属する国会議員は名誉を守られていないのでしょうか。東日本大震災などに際し、自衛隊は災害援助活動にも携わってきました。つまり、自衛隊は、災害援助活動を通して名誉を得ていると考えられます。
外国の軍隊に対して自衛官が劣等感を覚えるということもあるでしょう(A1参照)。しかし湾岸戦争のように、9条の存在によって自衛隊が戦闘地域への派遣を免れた事例もあります。また、安保法制や周辺事態法成立に際し、多くの人が自衛隊員の生命が危険に晒されることを危惧して反対しました。
自衛隊が国防軍となり、軍事活動を活発化させることが可能になれば、自衛隊員の生命が危険に晒される可能性も増えるでしよう。生命と名誉は引き換えにできるものではありません。9条改正の理由として自衛隊員の名誉の問題をもち出してくることは、自衛隊員の生命を軽視することにもつながる危険性を有しています。 (pp. 61-2)
A1もA2もその要諦は、文末に記されている。A1では「個人的に差がある情緒的な想いを根拠にして改憲が必要だと主張することは非常に危ういことです。気の毒とか名誉とかいつた情緒面ではなく、しっかりとした根拠をもとに議論すべき」とあって、言説11が持つポピュリズム的な語りを批判している。
大衆の情緒、感情に訴える政治的主張は、とくに保守的(または右翼)政治家に重用されてきた。ヒットラーのナチスを例に出すまでもなく、現代日本においても片言隻句(つまり論を尽くさない)で票を大量に集めた小泉純一郎はそれほど古い話ではないし、なによりも「民主主義は感情統治」と断言して憚らなかった政治家がいる。橋下徹である。想田和弘は、橋下の手法を次のように述べている。
橋下氏は、人々の「感情を統治」するためにこそ、言葉を発しているのではないか。そして、橋下氏を支持する人々は、彼の言葉を自ら進んで輪唱することによって、「感情を統治」されているのではないか。
そう考えると、橋下氏がしばしば論理的にめちゃくちゃなことを述べたり、発言内容がコロコ口変わったりしても、ほとんど政治的なダメージを受けない(支持者が離れない)ことにも納得がいきます。そうした論理的ほころびは、彼を支持しない者(感情を統治されていない者)にとっては重大な瑕疵に見えますが、感情を支配された人々にとっては、大して問題になりません。なぜなら、いくら論理的には矛盾しても、感情的な流れにおいては完璧につじつまが合っているからです。 [1]
もちろん、感情統治は民主主義ではない。おそらく、橋下は感情統治によって多数派を形成し、多数決で政治的決定を行うことは民主主義だと言いたいのだろう。しかし、多数決が民主主義だという理解も、小学校に入学したばかりの6歳児が初めてクラスで挙手の多数決採決を行ったとき「これが民主主義です」と言う教師の言をもって民主主義を理解した程度のレベルでしかない。私が小学校に入学した60年も前の民主主義理解である。
橋下流のポピュリズム、「感情統治」が一定の成功をおさめた結果として現在の極右政権の誕生につながっている。「感情統治」という政治の流れの中で、情緒から憲法を語ること、改憲を主張することがどれほどの過誤をもたらすかは言うをまたない。
A2も文末の「9条改正の理由として自衛隊員の名誉の問題をもち出してくることは、自衛隊員の生命を軽視することにもつながる危険性を有して」いるという文言にその要諦がある。つまり、生命を軽視することになりかねない憲法改正の言説を倫理的立場から批判している。つまり、A1は政治的手法の視点から、A2は倫理上の問題から言説11を批判している。独立した観点からの批判であるが、すぐれて補完的である。
もう一例、興味深いQ&Aを引用しておこう。
【言説19】
改憲草案92条1項は、「地方自治は…住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う」と規定。同93条3項では「国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力」するとしました。しかし、地方自治が果たす役割を「身近な行政」と割り切ることは、立憲・民主・平和・社会保障という地方自治の広範な理念を著しく切り縮めるものです。
Q1 ここでは地方自治の役割を「身近な行政」と言っていますが、そもそも「地方自治」(地方政府)は中央政府に対して、どのような関係にあるべきものでしょうか。
A1 憲法の理念が形骸化し国と地方自治体との対等協力関係が脅かされている
現行憲法は国と地方自治体とを平等な関係で捉えています。その関係を保障するため95条は「ある地方公共団体にのみ適用される特別法を定める手続きにおいては、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意が必要で、それがなければ国会で制定できない」と述べ地方自治体の意向を重視しています。しかし実際には国の事務を地方自治体に委任するという機関委任事務制度が導入されており、国予知法との関係は上下支配関係となっていました。
この機関委任事務制度は1999年の地方分権改革で廃止され、国と地方との関係は対等協力関係になりました。今その対等協力関係が脅かされています。1つは国が沖縄県を訴えた裁判です。これは国が沖縄県の行った地方行政行為を違法だと訴えたもので、7月に裁判所は国の言い分を認め、国が地方自治体よりも上に立ち支配するという以前の形を認めるかのような判決を出しました。2つ目は自民党改憲草案です。草案は「国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない」と書いています。その分担を決め割り振るのは国でしよう。国が地方自治体を支配する形です。憲法の理念が再び形骸化する危機にあります。
A2 「充実した地方自治」の体制のもとでの、地方政府と中央政府の闋係は?
ある有力な憲法学説によれば、人権保障を目的とし、「人民主権」を原理とする国家における、以下のような原則に立つ地方自治のありかたを、「充実した地方自治」の体制と位置づけ、あるべき地方政府と中央政府の関係を指摘しています。
第1は、充実した住民自治の原則です。地方公共団体の自治事務の処理(政治)は、住民の意思に基づき、住民の利益のために行われなければなりません。
第2は、充実した団体自治の原則です。地方公共団体が法人格をもち、その自治事務をその地方公共団体の利益のために中央政府から独立して処理する権利を求めるものです。
第3は、地方公共団体優先の事務配分の原則(市町村最優先、都道府県優先の事務配分の原則)です。「補完性または近接性の原則」とも言われます。国民の生活に一番近い地方公共団体が公的事務を優先的に分担し、国民生活から距離をもつより包括的な地方公共団体はより近接的な地方公共団体が効果的に処理できない公的事項を補完的に分担し、中央政府は地方公共団体では効果的に処理できない全国民的な性質.性格の事務と中央政府の存立に関する事務のみを分担するという事務配分の原則です。
第4は、上記の事務配分の原則にみあった自主財源配分の原則です。
第5は、「地方政府」としての地方公共団体です。以上のような地方自治の体制では、地方公共団体は、たんなる行政団体ではなく、統治団体・地方政府となります。
(杉原泰雄『地方自治の憲法論〔補訂版〕』(勁草書房、2008年)51-54頁) (pp. 92-94)
A1は、国と地方自治体が対等な関係であるとする地方分権の趣旨を踏みにじる政府・行政のありようをそのまま是認してしまおうとする改憲の意図を、事実経過を明らかにすることで批判している。一方、A2は、地方自治についての理念的な考察から憲法改悪の意図を批判している。「現実の政治的流れ」と「立法理念」はまったく異なった視点だが、一つのQに対する回答としての補完関係は理想形に近いだろう(私個人としては、いつも一方の手中に憲法理念、理念的な立法意思をおさめておくことを好もしいと思っている)。
本書の中で、読み過ごしてしばらく後で「あれっ」と思って立ち戻った一文があった。
しかし終戦後、GHQは日本の国民感情を考えて天皇を断罪せず、「象徴」という形で天皇制を存続させる「日本国憲法」を作りました。 (p. 25)
この文の主語である「GHQは」の述語は「断罪せず」と「作りました」の二つである。つまり、私は「GHQは「日本国憲法」を作りました」という構文として読み過ぎたのである。しかし、この文が含まれるQ&Aより前に「GHQ草案に多くの日本人の手が加わり、普遍的理念を持つ憲法に」と題する次のような回答文が記述されている。
現行憲法が日本がGHQの支配下にあった時代に作られたのは確かです。GHQから新憲法を作るように指示された当時の日本政府は、国民主権の草案を構想できず、戦前の明治憲法とあまり変わらない案しか作れなかったため、GHQが作った草案を「押し付け」られたわけです。しかし、そのGHQ草案自体、フランス人権宣言やアメリカ独立宣言などに現れた近代憲法原理に影響され、それを参照して研究した日本人の鈴木安蔵らの「憲法研究会」が作った案を参考にしたのです。ですから、GHQ草案には国境を超えて自由と平等を求める普遍的な理念が流れているうえ、日本の実情に合うよう日本政府によって何度も改訂が加えられており、ほぼ原形を留めていないといっても過言ではありません。こうして作られた「日本国憲法」は当時の国民に歓迎され、戦後長い間守られてきました。時代の変化には、憲法解釈の発展と最高法規である憲法を具体化する諸法令によって対応してきました。翻訳調でおかしいと言われますが、法律とはほぼすベて独特の法律用語で書かれています。文体自体は法律の内容の問題点ではないので、それを改憲の根拠にするのはおかしいでしょう。 (pp. 12-3)
この文章ばかりではなく、最近はいろいろな文献が発見されて、憲法創設に多くの日本人が関わっていたことが知られるようになっていた。にもかかわらず、私は、「GHQは「日本国憲法」を作りました」に違和を感じないまま読み進んでしまったのである。
それは、私自身が長い間「GHQが日本国憲法を作った」と思っていたからである。戦勝国であるアメリカが全権を持つGHQを通じて敗戦国日本をいわば強権的に統治していたのであるから、たとえ日本の国会の圧倒的賛同のもとで成立したといっても「GHQが作った」という表現に私はまったく違和感を持たずに生きてきたということだ。1946年生まれの私が育つころ、周囲の大人たちは新しい憲法を喜んでおり、民主主義を自分たちの生きている場所でどう生かしていくのかに夢中になっていた。誰が憲法を作ったかなどということを問題にしている雰囲気なんてまったく感じられなかったのである。
「アメリカに押し付けられた憲法」と主張する人間たちがいても、だれが作ったかは問題ではない、優れた憲法はそれ自体として大切であると考えていた。戦後民主主義の盛り上がりの時期に成長した世代として私はそう考えていた。だから、「GHQが日本国憲法を作った」という文章にほとんど違和を感じなかったのである。本書を読み終えた今は、次のように読み替えておくことにする。
立憲主体である日本国国民の一般意思が日本国憲法を作りました。
この読み替え文に「GHQの承認のもとで」とか「GHQの草案をベースにして」という条件を付けくわえても何の問題もないが、どんな干渉もなく純粋に「立憲主体である日本国国民の一般意思」が現在の日本国憲法を作ったのなら、私は今よりもずっと日本人を誇らしく思っていただろう。
[1] 想田和弘『日本人は民主主義を捨てたがっているのか?』(岩波書店、2013年) pp. 19-20。
街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ
山行・水行・書筺(小野寺秀也)
日々のささやかなことのブログ
ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)
小野寺秀也のホームページ
ブリコラージュ@川内川前叢茅辺