無伴奏「シャコンヌ」とは、映画のタイトルです。
1994年、フランス・ベルギー・ドイツ合作の作品です。
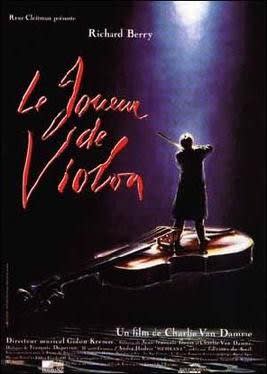
バッハ大先生の作品について話をしていたとき、
偶然この映画の話題になりました。
あまりメジャーとはいえない作品なので
お互いかなり驚きました。
いい作品です。 いえ、素晴らしい作品です。
このエントリーをご覧になって、万に一人でも
観ようと思う方がいらっしゃるかもしれませんので、
内容については一切触れないでおきます。
(レビューや解説を読まずに観ることをお勧めします)
残念ながら、現時点でDVDになっていませんので、
レンタルビデオで探さないと観られませんが・・・。
(私はレーザーディスクが出たときに買っていて、
後にDVDにダビングしたものを観ています)
作曲家が主人公の映画や、
音楽作品がテーマとなった映画は色々ありますが、
この作品は「特別」です。
唯一にして究極の作品だと思います。
映画館で観たときは涙が止まりませんでした。
1994年、フランス・ベルギー・ドイツ合作の作品です。
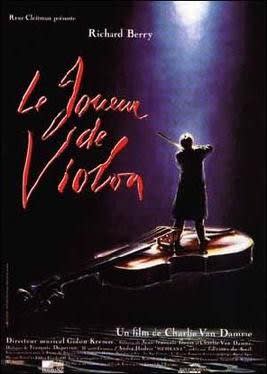
バッハ大先生の作品について話をしていたとき、
偶然この映画の話題になりました。
あまりメジャーとはいえない作品なので
お互いかなり驚きました。
いい作品です。 いえ、素晴らしい作品です。
このエントリーをご覧になって、万に一人でも
観ようと思う方がいらっしゃるかもしれませんので、
内容については一切触れないでおきます。
(レビューや解説を読まずに観ることをお勧めします)
残念ながら、現時点でDVDになっていませんので、
レンタルビデオで探さないと観られませんが・・・。
(私はレーザーディスクが出たときに買っていて、
後にDVDにダビングしたものを観ています)
作曲家が主人公の映画や、
音楽作品がテーマとなった映画は色々ありますが、
この作品は「特別」です。
唯一にして究極の作品だと思います。
映画館で観たときは涙が止まりませんでした。










