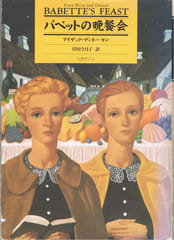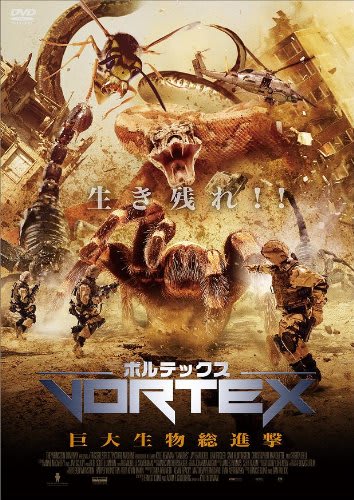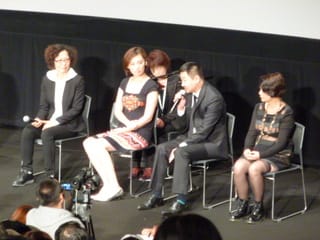M・ナイト・シャマラン監督の『レディ・イン・ザ・ウォーター』を観ました。
素晴らしい作品でした。
シャマラン監督といえば「シックス・センス」や「サイン」などが有名ですが、
恥ずかしながらシャマラン作品は今まで一本も観たことがなく
今回の『レディ・イン・ザ・ウォーター』が初でした。
色々な批評を見ると、
前出の過去作品にあるようなどんでん返しもなくて期待外れ、
と評判も悪く、興業的にも失敗作とのこと。
他の作品を知らなかったのが逆によかったのかもしれません。
加えて以前に、ライムスター宇多丸さんのラジオ番組
「ウィークエンド・シャッフル」内の映画時評コーナーで、
シャマラン監督の作品の"本質"について聴いていたのもよかったです。
宇多丸さん曰く、
シャマラン映画は実はテーマが一貫している
それは、主人公、登場人物が
「世界の本当の仕組みを知り、その中で自分が果たすべき真の役割に気付く」
という話である
ということです。
そしてそれに続けてこうも語っていました。
「嘘みたいな物語を語ることこそが自分の使命だ」と本気で信じている
『レディ・イン・ザ・ウォーター』をご覧になった方ならわかると思いますが、
まさにその通りの話でした。
なにせ、主人公のもとに現れる謎の女性の名前が「ストーリー」ですから。
アパートの管理人(主人公)と、かなり個性的な住人達。
主要登場人物は皆(まさか!と思う人まで)「物語」の中での真の役割を果たし、
その「物語」を完結へと導いていく・・・
主人公に、謎を解くヒントを与える人物が(結果的にそれがミスリードになってしまう)
唯一、残念な結果になってしまうのですが、
彼の仕事が映画や本の「批評家」だというのも示唆に富んでいます。
決して悪い人ではないんですけどね。
ところで、この『レディ・イン・ザ・ウォーター』を観て、
ケビン・コスナー主演の「フィールド・オブ・ドリームス」(Field of Dreams)
という映画を思い出しました。
映画全体の印象はまるで違いますが、どちらの作品も
なにか(天の声?あるいは内なる自分自身の声?)を信じ、
行動することでおきる「奇跡」。
そして、過去のトラウマから解放され、罪の意識が癒される・・・
という物語だと思います。
『レディ・イン・ザ・ウォーター』 素晴らしい「物語」でした。

『Lady in the Water』

こちらは MAN in the Field ではなく「Field of Dreams」
素晴らしい作品でした。
シャマラン監督といえば「シックス・センス」や「サイン」などが有名ですが、
恥ずかしながらシャマラン作品は今まで一本も観たことがなく
今回の『レディ・イン・ザ・ウォーター』が初でした。
色々な批評を見ると、
前出の過去作品にあるようなどんでん返しもなくて期待外れ、
と評判も悪く、興業的にも失敗作とのこと。
他の作品を知らなかったのが逆によかったのかもしれません。
加えて以前に、ライムスター宇多丸さんのラジオ番組
「ウィークエンド・シャッフル」内の映画時評コーナーで、
シャマラン監督の作品の"本質"について聴いていたのもよかったです。
宇多丸さん曰く、
シャマラン映画は実はテーマが一貫している
それは、主人公、登場人物が
「世界の本当の仕組みを知り、その中で自分が果たすべき真の役割に気付く」
という話である
ということです。
そしてそれに続けてこうも語っていました。
「嘘みたいな物語を語ることこそが自分の使命だ」と本気で信じている
『レディ・イン・ザ・ウォーター』をご覧になった方ならわかると思いますが、
まさにその通りの話でした。
なにせ、主人公のもとに現れる謎の女性の名前が「ストーリー」ですから。
アパートの管理人(主人公)と、かなり個性的な住人達。
主要登場人物は皆(まさか!と思う人まで)「物語」の中での真の役割を果たし、
その「物語」を完結へと導いていく・・・
主人公に、謎を解くヒントを与える人物が(結果的にそれがミスリードになってしまう)
唯一、残念な結果になってしまうのですが、
彼の仕事が映画や本の「批評家」だというのも示唆に富んでいます。
決して悪い人ではないんですけどね。
ところで、この『レディ・イン・ザ・ウォーター』を観て、
ケビン・コスナー主演の「フィールド・オブ・ドリームス」(Field of Dreams)
という映画を思い出しました。
映画全体の印象はまるで違いますが、どちらの作品も
なにか(天の声?あるいは内なる自分自身の声?)を信じ、
行動することでおきる「奇跡」。
そして、過去のトラウマから解放され、罪の意識が癒される・・・
という物語だと思います。
『レディ・イン・ザ・ウォーター』 素晴らしい「物語」でした。

『Lady in the Water』

こちらは MAN in the Field ではなく「Field of Dreams」