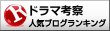2016年、『シン・ゴジラ』と共に史上空前のメガヒットを記録した、新海 誠 監督によるアニメーション映画。WOWOWでようやく観ました。声の出演は神木隆之介、上白石萌音、長澤まさみ、市原悦子etc……
観てない方でも大まかな内容はご存じでしょうから、此処では個人的な感想だけ書かせて頂きます。
男女の心が入れ替わっちゃう『転校生』バリエーションの話だとは知ってましたが、実際に観ると同じ尾道三部作でも『時をかける少女』の方に近いと私は感じました。
ただ入れ替わっちゃうだけじゃなくて、両者の間には3年という時間の隔たりがあるんですね。しかも、その3年の間に片方がこの世からいなくなっちゃってる。
だから現実には会えない相手なのに、どうしても会いたい想いが奇跡を起こす。お互いの存在が記憶に残ってないのに、想いだけはずっと残ってる。いつか出逢えることを信じて、相手を探し続ける終盤の二人は『時をかける少女』の芳山和子そのまんまでした。
もちろん元祖『君の名は』へのオマージュもあるでしょうが、それよりも新海監督は大林宣彦監督から、私が思ってた以上に影響を受けておられるようです。
それにしても、あの異常な大ヒット。たかが純愛ストーリーのアニメ映画を、なぜ日本人があれほど群れをなして観に行ったのか、とにかく私はその理由が知りたくて観ました。で、自分なりに答えを見つけましたよ。
あれだけ沢山の人が観てるんだから、同じ答えを出した方も沢山おられるかも知れないけど、これは決して受け売りではありません。(一応アマゾンのレビューは覗いてみたけど、盲目的な絶賛ばかりで何の参考にもなりませんでした)
私の答えは、たぶん大ヒットの理由は『シン・ゴジラ』と全く同じだろう、という解釈。どちらも、物凄く上手に創られた「アトラクション映画」なんですよね。
考えてみれば、現在の日本で(世界でも?)映画をヒットさせるにはアトラクションの要素が不可欠です。本作のクライマックスである彗星落下のくだりなんか、完全に災害パニック物ですから、それこそ『シン・ゴジラ』と変わんない。
で、祭りの夜にやって来て分裂し、花火みたいに降り注ぐ彗星の欠片群という、映像の美しさとロマンチックさ! そんなシチュエーションの下で繰り広げる一大メロドラマですから、そりゃ女性客は酔いしれますよ!
『シン・ゴジラ』よりも『君の名は。』の方がヒットしたのは、前者が男の子向けのアトラクションで、後者が女の子向けのアトラクションだったから。ホントそれだけの違い。
彗星のくだり以外でも、主役二人や村の人々の運命を左右するアイテムが、山奥のパワースポットに隠されてるなんて『インディ・ジョーンズ』そのまんまだし、この映画でテーマパークが造れるくらいアトラクション要素が満載なんですよね。だからこそ、皆わざわざ劇場に足を運ぶワケです。ストーリーじゃなく、シチュエーションを楽しむために。リピーターが多い所以です。
もちろん良いストーリーだし、語り口も憎らしいくらい巧いんだけど、この「アトラクション」の要素が無ければ大ヒットにはならなかっただろうと私は思います。
それは新海監督の計算だったのか、あるいは監督ご自身が好きな映画の要素を盛り込んで行った結果、たまたまそうなったのか?
いずれにせよ、これは大ヒットすべくして大ヒットした、いま最も売れる映画の典型モデルです。とにかく女性客が酔いしれるシチュエーション、それも劇場の大画面でこそ堪能できる大スケールのシチュエーションを設定し、その下で等身大のキャラクターによる甘~いメロドラマを展開させる。今後のシネコンは、そんなアニメしか上映しなくなるかも知れませんw
……と、いうような分析を抜きにして、素直な感想を書けば、とても面白かったです。特に『転校生』だと思ってた話が実は『時かけ』だった!ってことが分かって来る、序盤から中盤にかけて。後半はやっぱメロドラマですから、女性客みたいに酔いしれることは出来ませんでした。
それに、やっぱアトラクションだけに観てる間は楽しいけど、余韻は残らないですね。冷静に振り返ると、ちょっと話が甘すぎたんじゃないかと思います。
尾道三部作は、ただ甘いだけじゃなく「青春の痛さ」「残酷さ」がちゃんと描かれてました。だから心に突き刺さって忘れられないワケです。
『君の名は。』は、たぶん明日には忘れちゃいます。そりゃアトラクションだから当たり前のこと。いま大ヒットする映画は、おしなべてそういうもんだと思っておけば、まず間違いありません。
PS. 『シン・ゴジラ』もあらためて観直しましたが、全く新しい手法とクラシックな手法を見事に融合させてる点も『君の名は。』と共通しており、庵野秀明監督と新海誠監督はやっぱ資質が似てると思いました。庵野さんも本職はアニメですもんね。