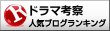久々となる日本映画レビューですが、これは積極的にオススメできる作品じゃありません。特に、観てスッキリしないどころか憂鬱な気分にさせられたり、救いがないようなストーリーは敬遠したいと仰る方には「絶対観ない方がいい」と断言しておきます。
私自身も暗いのは得意じゃないんだけど、なんとなく「日本のレズビアン映画」をまたレビューしたくなって(詳しい内容はあえて調べずに)DVDを借りて観たら「うわっ、なんだこれは!?」と。ただでさえネガティブなものは避けたい時期に「しまった、うっかりした!」と、大いに後悔するほど本作の憂鬱さ、救いの無さは群を抜いてます。
けど、2回に分けて観るつもりが一気にラストまで観ちゃった(それだけ引き込まれた)のは事実だし、万人受け=当たり障りない“商品”で溢れてるメジャー界隈よりよっぽど刺激的で、ボケ防止には持って来いかも知れません。
少なくとも私は、そのストーリーが憂鬱であればあるほど、救いが無ければ無いほど、作者が一体どういうつもりで創作したのかを凄く知りたくなる。
もちろん、その作品に“魂”とか“熱量”を感じなければ冒頭数分で鑑賞をやめた筈だから、きっと何かメッセージが込められてると思うワケです。
それを読み解くにはストーリーを(サラッとだけど)結末まで書く必要があるので、憂鬱なレズビアン映画が大好きでネタバレを避けたい方や、救いが無いなら粗筋も知りたくないと仰る方は、ここから先は読まないで下さい。亀井亨監督による2016年公開の作品です。
 小さな配管工会社に勤める技師の屋島(不二子)は自分が女性であることに違和感を抱えており、恋愛に縁が無いまま生理も止まってる今日この頃。
小さな配管工会社に勤める技師の屋島(不二子)は自分が女性であることに違和感を抱えており、恋愛に縁が無いまま生理も止まってる今日この頃。
そんなある日、屋島は水道管修理の依頼を受けて訪ねた古い家で、若い女性の九(真上さつき)と出逢い、お礼に「I」というアルファベットを象った飴を貰います。
どうやら九は屋島に自分と相通じるものを感じたらしく、数日も経たない内にわざと水道管を詰まらせ、再び修理にやって来た屋島に黙ってキスし、屋島も黙ってそれを受け入れるのでした。


 二人に相通じるのは同性愛者ということに限らず、両者とも片親で、屋島はしょっちゅうカネの無心に来るアル中の母親になけなしの給料を分け与え、九は同居する父親に支配されて性のオモチャにされている!
二人に相通じるのは同性愛者ということに限らず、両者とも片親で、屋島はしょっちゅうカネの無心に来るアル中の母親になけなしの給料を分け与え、九は同居する父親に支配されて性のオモチャにされている!
(学校の制服は変態オヤジの趣味=コスプレであり、演じてる俳優さんは成人女性ですからね、goo事務局さん!)
つまり屋島も九もそれぞれ親と共依存の関係にあり、屋島は先天的に、九は後天的に自分が“女性”として生まれた運命に苦しんでる。



 そんな二人も身体を重ねる内に共依存の関係となっていき、屋島は九に「一緒にどこかへ逃げよう」と説得するんだけど、九は「どうせすぐに見つかるから」と頑なに拒みます。
そんな二人も身体を重ねる内に共依存の関係となっていき、屋島は九に「一緒にどこかへ逃げよう」と説得するんだけど、九は「どうせすぐに見つかるから」と頑なに拒みます。
せっかく大切に思えるパートナーと出逢えたのに、鳥籠みたいに小さな世界から飛び出せない二人。
そればかりか、九とのチョメチョメによってフェロモンが出て来ちゃった屋島は、同僚の最低チンポコ野郎にレイプされてしまう!

 絶望の淵に立たされた屋島がふと、九と会うたびに渡されてたアルファベットの飴を並べてみたら驚いた!
絶望の淵に立たされた屋島がふと、九と会うたびに渡されてたアルファベットの飴を並べてみたら驚いた!
 「H」「E」「L」「P」
「H」「E」「L」「P」
頑なに脱出を拒んでた筈の九が、実は屋島に助けを求めてた!?
すぐさま九の家に駆けつけた屋島は、今まさに彼女を犯してる真っ最中の最低ちんぽこ豚ファーザーの後頭部に、配管工事用の特大ハンマーを振り下ろすのでした。

 工場のトラックで豚ファーザーの死体を森まで運び、車内で激しく絡み合う二人。ところがそのあと九は、なぜか豚ファーザーの死体にすがって泣きじゃくる。せっかく地獄の檻から救ってあげたのにと、屋島は混乱します。そして……
工場のトラックで豚ファーザーの死体を森まで運び、車内で激しく絡み合う二人。ところがそのあと九は、なぜか豚ファーザーの死体にすがって泣きじゃくる。せっかく地獄の檻から救ってあげたのにと、屋島は混乱します。そして……
ちょっと仮眠したスキにトラックから消えた九を、必死に探し回った屋島が見たものは……!
 荷台にあったロープで首を吊り、息絶えた九の右手には、3つのアルファベットの飴が握られてました。
荷台にあったロープで首を吊り、息絶えた九の右手には、3つのアルファベットの飴が握られてました。
 「Y」「O」「U」
「Y」「O」「U」
つまり九が飴に託した想いは「I HELP YOU」であり、豚ファーザーとの共依存を絶ち切りたいワケじゃなかった! ……と私は解釈したけど説明は一切されぬまま、突き放すように映画は幕を下ろします。

 どうですか? これ以上は考えられないほどのバッドエンドで、「作者はこの2人を一体どうやって救済するんだろう?」なんて期待しながら観た私はエラい目に遭いました。
どうですか? これ以上は考えられないほどのバッドエンドで、「作者はこの2人を一体どうやって救済するんだろう?」なんて期待しながら観た私はエラい目に遭いました。
けれど、伝わってくる熱量がとにかく凄い。見過ごせない。何かしら必ずメッセージがある筈で、そうでなきゃスタッフ&キャスト(ことに主演の不二子さんと真上さつきさん)が浮かばれない。
まず私が感じたのは、彼女らに比べりゃ自分の置かれた境遇がいかに恵まれてるか!っていう、逆説的な励まし。
その次に、男という生きものが如何に愚かで、どれだけの女性たちがその犠牲になってるかっていう、まさに2025年現在でも変わらない社会問題に対する糾弾。
 そしてもう1つ。親との共依存関係をやめられない心理は解らなくもないけど、同僚にレイプされながらその会社を辞めることも訴えることもせず、また九が父親に性的虐待を受けてるのを知りながら警察に通報しない屋島の、愚かさというか無知さ。
そしてもう1つ。親との共依存関係をやめられない心理は解らなくもないけど、同僚にレイプされながらその会社を辞めることも訴えることもせず、また九が父親に性的虐待を受けてるのを知りながら警察に通報しない屋島の、愚かさというか無知さ。
男性しかいない小さな工務店で働き、友達も恋人もつくらず、アパートにはテレビも無い。世の中には救済の場も存在することを、たぶん屋島は知らないんでしょう。九の場合は父親によって情報を遮断されてるのに対し、彼女は自らアンテナを外してる。
つまり、これは私自身も凄く耳の痛いテーマになるけど、“孤立”の成れの果てを描くことで“他者との繋がり”を促してる?と解釈出来なくもない。
実際、職場で同僚たちと一定の距離を保ってる私は、皆の間じゃ常識になってる些末なこと(例えば先日書いたMさん2号の正体とか)を後から知って驚くようなことが、ままあったりします。
友達も少ないし、そのこと自体は苦痛じゃないにせよ、無知であることの弊害は時おり感じてます。
作者が一番伝えたかったのは、そういうことじゃないかと私は解釈しました。そうでなきゃ観てしまった私自身も浮かばれません。
 PS. ラストのどんでん返しで悲惨さが倍増する映画と言えば、フランク・ダラボン監督のアメリカ映画『ミスト』(’07) を思い出します。
PS. ラストのどんでん返しで悲惨さが倍増する映画と言えば、フランク・ダラボン監督のアメリカ映画『ミスト』(’07) を思い出します。
正体不明のモンスターに追い詰められ、政府にも見放されたと思い込んだ主人公が一家心中を敢行し、さあ自分も死のうとしたところで救援軍が駆けつけるという究極のバッドエンド。
全てはそのための前フリだったと考えればエンタメ性を感じなくもないけど、この『アルビノ』がそうだったとすれば相当な悪趣味で、やっぱりオススメは出来ません。