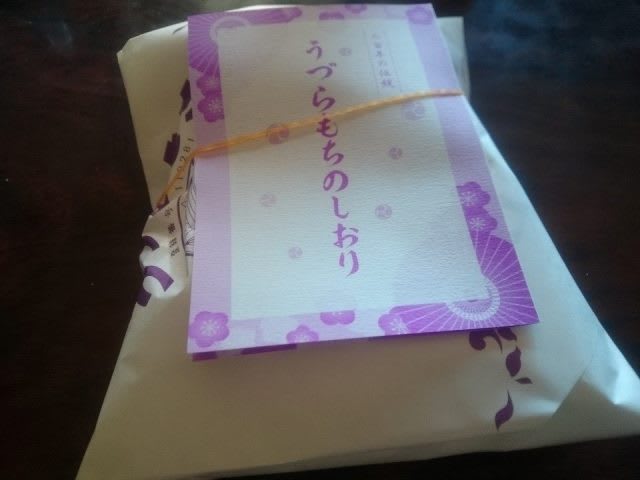先日、山梨をふらついたときに、北杜市白州町を通りかかった。ふっとカヤの大木が目に入り、たまたま寄ったのが白州町花水の曹洞宗霊長山清泰寺に寄った。
有名なのは参道入り口にあるカヤの大木。

何も、予備知識のないまま、境内を散策した。すると、何ともきれいな馬頭観音の石像が目に入った。

これは、石造としては秀逸だ。看板によると町の文化財なのだそうだ。
何ともいい表情だ。地方の石像は素朴なものが多いが、これは何ともいい表情だ。解説は特になかったが、非常に緻密な掘りのような気がする。あまりのきれいさに、ふと高遠の石工・守屋貞次を思い出す。貞次といえば、須玉町の海岸寺の石仏が有名だが、この馬頭観音もいい。
今回は何も知らずに立ち寄ったお寺で、何だか感動した石仏との出会いだった。
有名なのは参道入り口にあるカヤの大木。

何も、予備知識のないまま、境内を散策した。すると、何ともきれいな馬頭観音の石像が目に入った。

これは、石造としては秀逸だ。看板によると町の文化財なのだそうだ。
何ともいい表情だ。地方の石像は素朴なものが多いが、これは何ともいい表情だ。解説は特になかったが、非常に緻密な掘りのような気がする。あまりのきれいさに、ふと高遠の石工・守屋貞次を思い出す。貞次といえば、須玉町の海岸寺の石仏が有名だが、この馬頭観音もいい。
今回は何も知らずに立ち寄ったお寺で、何だか感動した石仏との出会いだった。