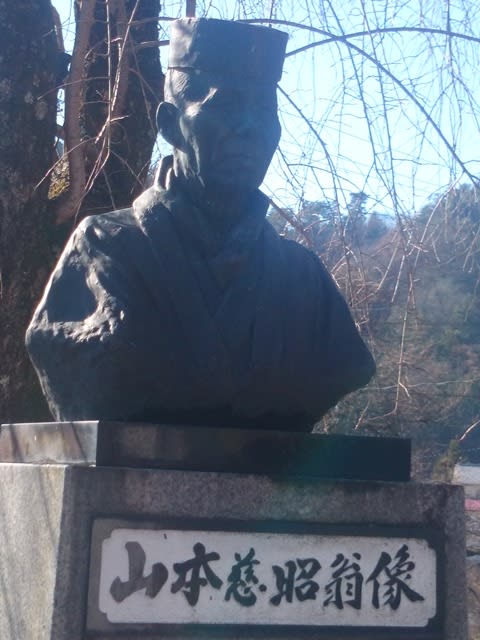長野県北部、信濃町に「石の鐘」があるいう。たまたま知った情報で、出かけてみることにした。それは信濃町市街地から山手に入って行く富濃集落にある。浄土真宗本願寺派の称名寺だ。

地域にある小さなお寺だ。

本堂脇にある鐘楼がこれだ。

確かに大きな石が吊り下げられている。これは昭和16年の「国家総動員法」によって金属回収令が出され、あらゆる金属類が取り上げられた。そして称名寺の鐘も大砲の弾丸になったのだそうだ。そして、信徒さんたちによって近くにあった石をに吊るしたという。

その石には「梵鐘記念 昭和十七年十月」と刻まれている。そして70年も経った現在でも、そのまま石が吊るされ続けている。
いまだに「石の鐘」が吊るされ続けているのは、当寺の女性僧侶のご意志なのだそうだ。いまだに続く戦争、まだ平和とは言えないこの世の中に対する厳しい見方をお持ちなのだ。そして、戦争がなくなったら、石の鐘は下げてとりかえるとのこと。
また、鐘楼下にはシダレザクラの古木がある。

これも、戦時中の食料増産のために、切られそうになったところを、激しくつめよって何とか阻止したのだそうだ。
この称名寺のある場所は、北信濃の静かな山村の風景をたたえたところだ。自分が訪ねたときは、ソバの花がきれいだった。

戦争と平和…。この石の鐘の意味を深く考えたい。撞木はあるが、鐘の音はするはずはない。本当に平和になったとき、この信濃町に本当にきれいな鐘の音が響き渡るはず。

地域にある小さなお寺だ。

本堂脇にある鐘楼がこれだ。

確かに大きな石が吊り下げられている。これは昭和16年の「国家総動員法」によって金属回収令が出され、あらゆる金属類が取り上げられた。そして称名寺の鐘も大砲の弾丸になったのだそうだ。そして、信徒さんたちによって近くにあった石をに吊るしたという。

その石には「梵鐘記念 昭和十七年十月」と刻まれている。そして70年も経った現在でも、そのまま石が吊るされ続けている。
いまだに「石の鐘」が吊るされ続けているのは、当寺の女性僧侶のご意志なのだそうだ。いまだに続く戦争、まだ平和とは言えないこの世の中に対する厳しい見方をお持ちなのだ。そして、戦争がなくなったら、石の鐘は下げてとりかえるとのこと。
また、鐘楼下にはシダレザクラの古木がある。

これも、戦時中の食料増産のために、切られそうになったところを、激しくつめよって何とか阻止したのだそうだ。
この称名寺のある場所は、北信濃の静かな山村の風景をたたえたところだ。自分が訪ねたときは、ソバの花がきれいだった。

戦争と平和…。この石の鐘の意味を深く考えたい。撞木はあるが、鐘の音はするはずはない。本当に平和になったとき、この信濃町に本当にきれいな鐘の音が響き渡るはず。