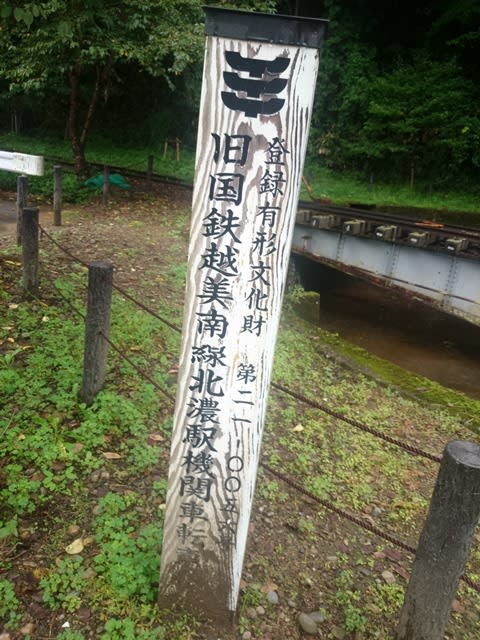今日、せっかく下伊那まで足を伸ばしたので、今年のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」に登場する井伊直親が幼少期を過ごした、高森町の臨済宗の古刹・松源寺に寄ってみた。幼名・亀之丞は、主人公の井伊家23代当主・直虎(直虎は22代当主直盛の一人娘)のいいなずけであった。
亀之丞の父を討った今川義元は、亀之丞の首も差し出すよう命じたが、亀之丞は遠州井伊谷から南信州、松源寺まで逃げ、20歳まで過ごしたという。
さて寺に着くと、大河ドラマで盛り上がっている風景が目に入る。

平日にも関わらず、駐車場にはマイクロバスが停まっていた。ゆかりの地を訪ねる方々のツァーの団体さんがおられた。さすが、大河効果だ。
さて、山門から入るために駐車場から正面に移動する。するとエドヒガンザクラの古木がいい感じに枝を広げている。

またキレイなお顔の地蔵尊も静かに出迎えてくれる。

絵になる風景だな!

さて山門から中へ入る。

静かな本堂。扉は閉められていたが、中から御住職と思しき方の説明されるお声が漏れ聞こえてくる。団体さんにお話をされているようだ。


本堂を始めとして境内はキレイに整えられ、清々しい空間であった。鐘楼もあり、時を告げてくれる鐘の音が聞こえてきそうであった。

ドラマはまだ始まったばかり。亀之丞が成人して再び、遠州へ戻るまでのお話の舞台に注目したい。
亀之丞の父を討った今川義元は、亀之丞の首も差し出すよう命じたが、亀之丞は遠州井伊谷から南信州、松源寺まで逃げ、20歳まで過ごしたという。
さて寺に着くと、大河ドラマで盛り上がっている風景が目に入る。

平日にも関わらず、駐車場にはマイクロバスが停まっていた。ゆかりの地を訪ねる方々のツァーの団体さんがおられた。さすが、大河効果だ。
さて、山門から入るために駐車場から正面に移動する。するとエドヒガンザクラの古木がいい感じに枝を広げている。

またキレイなお顔の地蔵尊も静かに出迎えてくれる。

絵になる風景だな!

さて山門から中へ入る。

静かな本堂。扉は閉められていたが、中から御住職と思しき方の説明されるお声が漏れ聞こえてくる。団体さんにお話をされているようだ。


本堂を始めとして境内はキレイに整えられ、清々しい空間であった。鐘楼もあり、時を告げてくれる鐘の音が聞こえてきそうであった。

ドラマはまだ始まったばかり。亀之丞が成人して再び、遠州へ戻るまでのお話の舞台に注目したい。