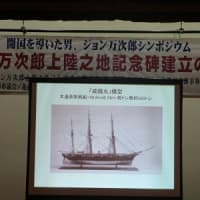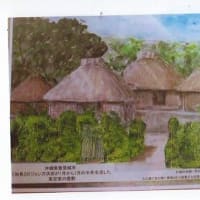「ぷらっとウオーク」 情報プラットフォーム、No.257, 2(2009)掲載
{巨樹・古木と古仏・名刹}

ご感想、ご意見、耳寄りな情報をお聞かせ下さい。
高知県香美郡土佐山田町植718 Tel 0887-52-5154 
鈴木朝夫の「ぷらっとウオーク」 目次
高知県緑サポーター会や緑と水の会にメンバー登録している。各種のイベントの中で最も興味を引かれ、数多く参加してきたのは「巨樹・古木に会いに行く旅」である。「土佐の名木・古木」(高知県森林局、2001,3)には600樹の写真とデータが記録されている。見てきたものに○印を付けているが進捗度は微々たるものである。
このデータ集によれば、一番多い樹種のスギが156樹、次いでクスノキ60樹、イチョウ41樹、ムク38樹、ヒノキ33樹、エノキ23樹と続く。樹齢の最高は、およそ2000年で、須崎市大谷のクスノキ、大豊町杉の大杉である。樹高は、杉の大杉と十和村地吉の夫婦杉がともに60m、次いで十和村地吉のクスノキ50m、越知町横畠のイチイガシ48m、大豊町新田神社のイチョウ45mが続く。
胸高直径は、大川村小北川のカツラ13.9m、杉の大杉13m、安田町唐浜のクスノキ11.3m、仁淀川町長者のイチョウ10.8mである。改めて「杉の大杉」のすごさが理解できる。巨木を見守っている集落の長老は「この木の樹齢は309年です」と言う。端数の9年の理由を問えば、偉い先生が300年と言ってから9年経っているとの答に感心したものである。樹齢は古文書や言伝えに頼ることが多い。
ところで、昨年末に地方仏研究会主催の見学会「”冬の嶺北”をたずねて」に参加して、土佐町田井中島観音堂、大豊町栗生定福寺、大豊町寺内豊楽寺(ぶらくじ)を訪ねてきた。事前に書棚にある2冊の本、「れいほくネイチャーハント ガイドブック”巨木を見に行こう”」(嶺北巨木伝説実行委員会、2002,3)、および「高知県文化財ハンドブック」((財)高知県文化財団、1998,7)を取り出した。「巨木」の本には、観音堂の金木犀、定福寺の紅葉と乳銀杏、豊楽寺の多羅葉と杉が紹介されている。
「文化財」の本には、観音堂の立像(木彫)、香美市美術館で対面した定福寺の微笑みの六体の地蔵菩薩立像(木彫)他、豊楽寺の薬師堂(国宝)とその仏像達(木彫)が紹介されている。巨樹・古木と古仏・名刹の一致に吃驚した。全国統計によれば、巨樹・古木の57%が社寺に属している。3つの古刹の名木は当然のことかも知れない。だからこそ長い年月を守られてきたとも言える。
「文化財」の仏像は全部で100体、その中で98体が木彫(一本造りと寄木造りは半々)、その中でヒノキが76体、次いでクスノキ9体、スギ8体と続いている。この数字は森林県の高知だから当然と思いがちである。平安京に遷都した頃から、貞観時代に入ると木造仏が多くなっている。日本全体が木の文化圏だったのである。
高知としては、地産地消の土佐材が使われていると信じたい。また、ヒノキやクスノキが多いのはその香りと耐腐食性による。木造仏は檀像(香木の仏像)の流れの延長上にいるとも考えられる。木造仏に対
面するとき、仏師は掘り込む前から、木に宿る仏様のお姿が見えていたように思えて来る。