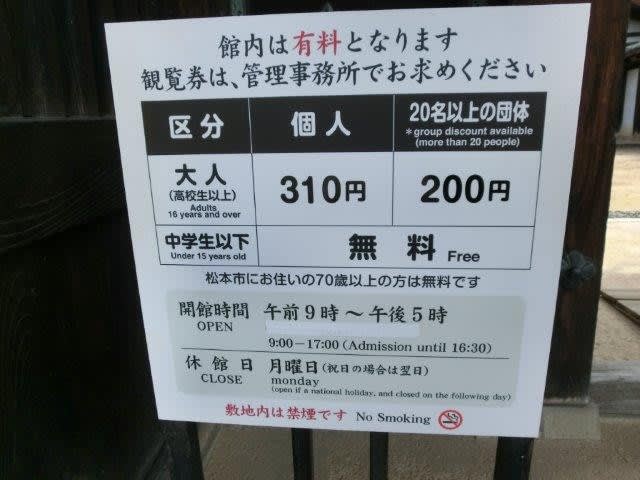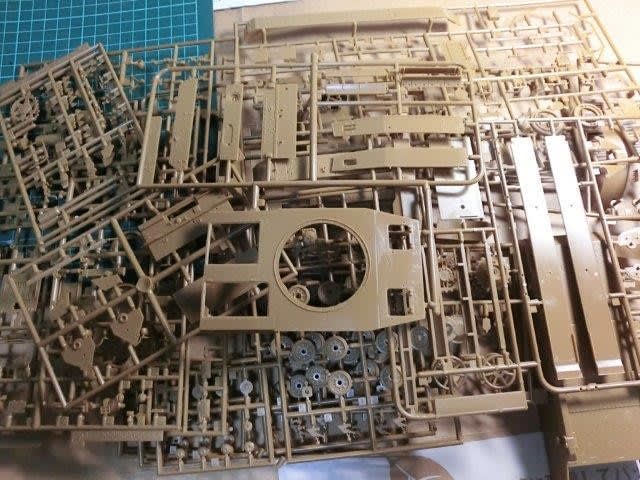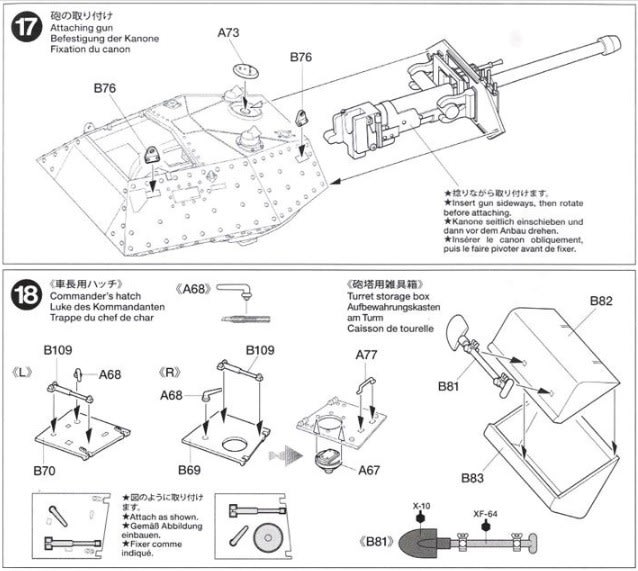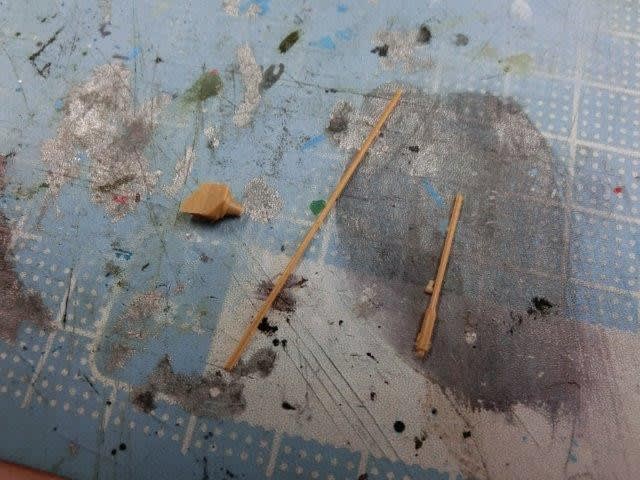大代川側線の南端あたりまで来ました。御覧のようにフェンスに絡まる草が分厚くなっていて、中に留置されている14系客車も上部しか見えませんでした。これは、草枯れの季節に来たほうが良かったかな、と思いました。
ですが、14系客車は、大井川鐡道の保有する4輌全てが大代川側線に留置されていることが確認出来ました。

長いこと風雨にさらされているためか、青色の塗装も白っぽく風化しつつありました。これからも当分使われることは無いのだろうな、と感じました。
この種の客車は、大井川鐡道においては急行かわね路号などの蒸気機関車または電気機関車が牽引する列車にしか使えませんので、急行かわね路号の客車がまだオハ35形である現在においては、使い道が無いのかもしれません。新金谷駅の側線に留置されたままの12系とともに、少しずつ荒廃が進んでいる感じでした。

大代川側線の南端は草藪に覆われて見えませんでしたが、留置車輛がまだあるようには見えず、地山のような地形がうっすらと見えましたので、南端に達したものと判断して引き返しました。上図はさきに見たお座敷客車ナロ80形の南面です。

電気機関車の見える位置まで戻ってきました。改めて見て、E10形かな、と考えました。大井川鐡道は3輌を保有していて、1輌はさきに新金谷車両区の機関車庫に入っているのを見ました。あと1輌の所在は、今回は掴めませんでした。

車体側面にE102の車番と大井川鐡道の社章が打ってありました。昭和24年(1949)製造のE10形の2号機でした。以前は新金谷駅などで見かけたのですが、この機関車も検査切れとなったようです。

付近に積み重ねてあった、鉄板状の部品です。片面が赤錆に覆われ、もう片面は黒色の塗膜が残っていましたので、たぶんこれらも蒸気機関車の外板か何かのパーツだろうな、と考えました。

もときた道を引き返して、今度は新金谷車両区の東の公園に行きました。御覧のように、金谷東公園とあります。

金谷東公園の南に大代川側線の踏切があるのが見えたので、その踏切の前まで行ってみました。踏切の奥の駐車場は、大井川鐡道の職員専用であるようでしたので、踏切を渡るのは控えて、左右の線路を見ました。

踏切の向こうの新金谷車両区の側線には、昔よく見かけた京阪電鉄の3000系テレビカーが廃車後のボロボロの姿で倉庫の代用となっているのが見えました。平成六年(1994)に京阪電鉄より譲渡され、3月20日に同鉄道へ入線し、平成二十六年(2014)まで運用され、その三年後に廃車となったモハ3008、クハ3507のうちの後者にあたります。
私自身は、初めて大井川鐡道に乗った時にこの京阪3000系に乗ったことがあります。それ以前に京阪本線で何度か乗っていましたから、大井川鐡道で見た時には「なんでここに」と驚いた記憶があります。それからもう25年ぐらいが経ったでしょうか。

京阪3000系の北には、上図のED500形電気機関車の1号機、「いぶき501」が停めてありました。ED500形は昭和三十一年(1956)に製造され、大井川鐡道には2輌がありましたが、「いぶき502」が他社に譲渡されて後に廃車となっています。
この「いぶき501」は、このときは修理および検査中であったようで、後で聞いた話では令和六年度中に運行を再開するということでした。

ED500形「いぶき501」の北には、上図の台車っぽいのが二つ並び、さらにシートに覆われた何かがありましたが、これらについては詳細が分かりませんでした。車輪が付いていないので、解体された台車枠だけが置いてある形でした。

その北には上図の南海6000系が停まっていました。最も新しい譲渡車輛ですが、長い事留め置かれたままで、後で聞いた話では令和六年度中に営業運転に投入される見込みだということでした。
おそらく、災害不通により千頭駅に留め置かれたまま朽ち果ててゆく南海21000系1編成と置き換えられるのだろう、と推測しています。もしくは、近々検査に入る東急7200系の代替となるのかもしれません。 (続く)