と、勝手に思っているザリガニです。

あまり貪欲に食べている感じはしませんが、
少しずつ、料理で出た野菜の切れ端や水草などを
齧っているようです。
イトミミズも地下にもぐっているのか、少しずつ
ですが数が減ってきているように思います。

夕方や朝は、よく動きます。
この写真は連続で撮ったものですが、動くときは
見ていて飽きませんね。

でも、何か気配を感じて臆病になると、すぐに
後に逃げます。
向きを反転させて、自分で作った巣穴モドキに
かくれようとします。
我が家のアメザリは脱皮を繰り返すところが
楽しいです。
大きくなっている個体は、くれくれとエサを
ねだりますし。
でも、やはりフォルムはこちらの方が、かっこ
いいんだよなぁ。

あまり貪欲に食べている感じはしませんが、
少しずつ、料理で出た野菜の切れ端や水草などを
齧っているようです。
イトミミズも地下にもぐっているのか、少しずつ
ですが数が減ってきているように思います。

夕方や朝は、よく動きます。
この写真は連続で撮ったものですが、動くときは
見ていて飽きませんね。

でも、何か気配を感じて臆病になると、すぐに
後に逃げます。
向きを反転させて、自分で作った巣穴モドキに
かくれようとします。
我が家のアメザリは脱皮を繰り返すところが
楽しいです。
大きくなっている個体は、くれくれとエサを
ねだりますし。
でも、やはりフォルムはこちらの方が、かっこ
いいんだよなぁ。










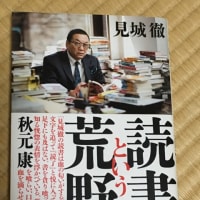

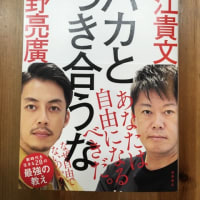

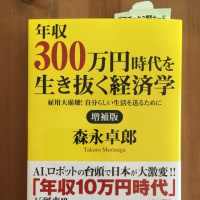





こんなふうに教室の中で飼ったら、さぞや人気者になることでしょう。
教室にあるザリガニ水槽って「水が臭い」というイメージがあるのですが、あれは手入れが悪いだけのことなのでしょうか?
エサをちぎりながら食べるので、魚よりは水を汚しやすいのかもしれませんが、エビの親分みたいなものですから、いわゆる掃除屋なので、けっこう何かしら食べていますね。
水換えの頻度を上げるか(魚よりも手入れが楽なので)、濾過器をつけるかで水は大丈夫と思います。
臭くなるのはやはりエサのやりすぎですよね。
あと、死んだあと放っておかれることで、甲殻類独特の異臭を放ちますよね。
これは複数飼育の際におきやすい共食いもそうすね。
あと、ザリガニは同じエサばかりやると、飽きてしまい食い残しが出てきますね。
私の感覚では、植物性のエサを多くやることと、食べ残さない量にすること、エサの量よりも頻度を多くすることで、魚と変わらない飼育ができています。
(このザリガニも実際に、まだ足し水のみで飼育。)
汚れに強いザリガニですが、ニホンザリガニなどは違うと言われていますね。何せ絶滅危惧種ですからね。
以前は様々なザリガニが飼育できたのですが、法律の関係で、飼育できなくなった事は残念です。それでもアメザリ系は飼育できますので、縄文人さんも、色々な種に挑戦されてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。
野生(?帰化している野良)のアメリカザリガニでも、黒っぽいヤツや、白ヒゲと呼ばれるひげだけ白い個体、何百匹に一匹といわれているマッカチンと呼ばれるまっ赤な個体など、見つけたり、コレクションしたりするのも面白いかもしれません。きっと水系にもよるのでしょうけどね。
ちなみに我が家のグラードン。
今朝脱皮していました。