第5回
宋教仁と国民選挙
『中原の虹』では、冒頭で触れた国民選挙を実現させようとした政治家、宋教仁の演説シーンをいかに描くか、苦労したという。宋教仁の演説はこう結ばれている。
〈そのほかの名誉は何もいらない。私が勲とするところは、ひとえに民の平安である。
敬愛する中華人民諸君!
どうかこの歓呼の声を、私に対してではなく、祖国の未来に向けてほしい。
この地球のまんなかに咲く、大きな華に。けっして枯れることもしおれることもない、中華という大輪の華に。〉
宋教仁は実務家だから勤勉に働いたけれど、書きものはあまり残していなかった。だから宋教仁の演説がどのようなものであったのか、実はわからないのです。上海の駅頭で演説をしたあとで殺されたのは確かなのですけど。どうすれば彼の演説のエッセンスを表現できるのか。最終的には、彼と同郷で彼と最も近い足跡を辿った人は誰かと考えました。すると、うってつけの人を発見しました。陳天華という宋教仁の同志です。この人は宋教仁と世代が同じで同じ時期に日本に留学していて、同じ会派に属していた。しかも同郷でもあるから、思想もかなり近いだろうと読みました。この陳天華は演説記録を残していたんです。彼の演説の草稿をベースにして、これに宋教仁らしい思想をミックスさせて彼の演説を書きました。
『中原の虹』は、親も家もない流民の子、張作霖があるとき老占い師に「汝、満洲の王者たれ」との予言を受けるところから物語がはじまる。天命を持つものだけが手にすることのできる龍玉を、清朝の太祖ヌルハチの墓で手に入れた張作霖は、予言通り馬賊の長としてめきめきと頭角をあらわしてゆく。一連の取材を通じて浅田氏が馬賊の子分のなかで印象に残っているのは、どちらも実在の人物である張景恵(好大人)と馬占山(秀芳)だった。
馬賊の格なら、実は張作霖より張景恵のほうが上だった。けれども張作霖は、総攬把の地位を張景恵から譲られる。そのとき張景恵は「器はこいつのほうが上だろう」と思ったのでしょう。部下は張景恵のほうがずっと多かったけれども、求心力があるのは張作霖だという判断です。張作霖の子分になった張景恵はのちに満洲国の国務総理になる。そして日本の敗戦後に捕まって獄死しました。撫順の収容所で彼が死んだ部屋を見ましたが、感慨あらたなるものがありましたね。実は、彼の息子がその牢獄の看守なんです。偶然、撫順の看守をやっていて、近くの奉天から連れてこられた父親を看取ることになるわけです。まさに事実は小説よりも奇なりですね。
馬占山は神出鬼没
馬占山は『中原の虹』のなかでは先駆けを務める華のある馬賊だ。『中原の虹』では貧しさから地主と関係を持った妻を許せず、妊娠を知りながら捨てたことを悔いている。あるとき討伐に向かった匪賊のなかにその妻を見つけたが、敵として自ら撃ち殺したという人物である。
馬占山は日本軍に最後まで徹底抗戦します。日本でも、「馬占山征伐」というニュースが何回も臨時で出されたほどですから。「馬占山死亡」という記事も何度も報じられています。ところが、そのたびに「やっぱり馬占山は生きていた」と訂正記事が出る。馬占山は神出鬼没、不死身の将軍だったのです。
実は日中戦争当時、日本では馬占山ごっこっていうのが流行ったらしい。その遊びの内容はわからないんです。少し調べてみたのですが、わかりませんでした。おそらく、神出鬼没の鬼であるという要素がどこかに入った遊びなのでしょう。
『中原の虹』を発表する前、浅田氏は中国人小説家たちに「次は張作霖を書く」と伝えたことがあるという。
上海の作家協会で中国人小説家たちと話をしているときに『中原の虹』の構想を伝えたら、満場一致で「張作霖を小説のヒーローとして書けるはずがないじゃないか」という反応でした。なかには爆笑した人もいたほどです。こちらとしては、そうした反応を見て心のなかでガッツポーズをきめました。これほど過小評価されている人物なら、誰もが驚くような小説を書けるに違いないと思ったからです。
張作霖研究家との出会い
張作霖の長男・張学良については『中原の虹』執筆過程における秘話もある。
張学良は二〇〇一年まで生きていて、生前NHKの番組でインタビューも受けています。その張学良の番組を通じて不思議な縁がありました。以前、NHKの番組に出演したことがきっかけで、張学良のインタビュー番組を作ったディレクターとその奥様にお目にかかったのです。話をしてみたら、ディレクターの奥様は富山大学で張作霖を研究している澁谷由里先生だというではありませんか。これは天の助けと思って、当時執筆中の『中原の虹』の校閲を澁谷先生にお願いしました。
その助けがなければ小説のなかで実現できなかったことはたくさんありました。たとえば、満洲語の表現について、その富山大学の先生の恩師である京都大学の先生の助言をいただきました。その方はもう相当のご高齢なのだけれども満洲語を専門にされている方で、もしかしたら日本で最後の満洲語研究家かもしれません。その先生に満洲語の表現や発音を教えていただきました。そうした助けもあって『中原の虹』は完成したのです。
『中原の虹』を発表したあと、実際に昔の満洲を知っている人からの手紙がたくさん届いたという。たとえば、「私は現在九〇歳で、もとは満鉄の社員でした。張作霖の『打聴、満洲風』という言葉にしびれました」といった感想がとてもうれしかったという。
つまり、実際の満洲を知る人たちにとってもリアルな満洲の風や大地の一端を描けていたのだと思う。当時の満洲に渡った人たちは、何かしらの青雲の志を持っていた方が多い。そういう気持ちを持っていた人たちの心に「打聴、満洲風」という言葉が響いたのだとすれば、こんなにうれしいことはありません。
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=g2_pc-22&o=9&p=16&l=st1&mode=books-jp&search=%E6%9F%B3%E7%BE%8E%E9%87%8C&fc1=000000&lt1=_blank&lc1=3366FF&bg1=FFFFFF&f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="336" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe>
-->









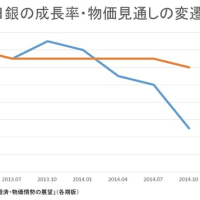
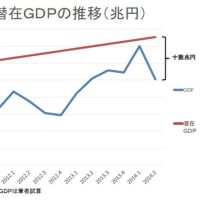
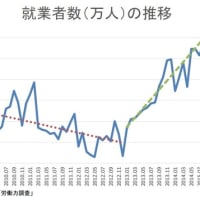
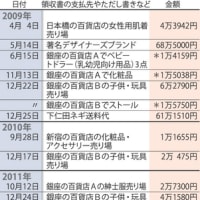
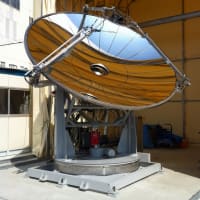
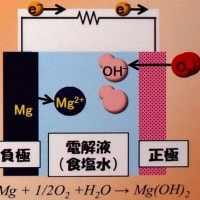

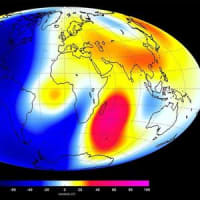


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます