第4回
植民地政策と西洋の良心
浅田氏は『蒼穹の昴』のなかでカスチリョーネ(郎世寧)というナポリ出身の実在の人物を登場させている。清王朝の康熙・雍正・乾隆の三代にわたって仕えた技術者で、もともとは画家だが、音楽も建築も専門家で、都市のインフラ整備、とりわけ当時の北京の下水道整備などで活躍した人物である。また、円明園という西洋式の庭園の設計も残している。
私が小説にカスチリョーネを登場させたのは、中国に対して悪いことばかりをしていた西洋社会の良心の所在を考えるためです。カスチリョーネというのはこの作中で真正面からテーマを語っている唯一の人物です。彼の絵はずいぶん残されているのだけれど、見るたびに心を打たれます。彼の絵は西洋画の画法としての陰影や遠近のつけかたをきちんとしている。それと同時にルネサンスの西洋においてはありえなかった細密画法、つまり精密なほど美しいとされる中国画の画法も取り入れている。非常に面白い折衷の仕方をしています。
私はカスチリョーネの絵から彼の人格を想像してみました。
カスチリョーネの人柄を考察するための史料としては、ほとんど芸術作品そのものしか残されていない。それでも浅田氏は作品を通して語りかけてくるその人格に打たれ、そこにヨーロッパ覇権主義の良心を感じたという。
そもそも、西洋の植民地政策はすでに乾隆帝の時代には盛んでした。当時のイエズス会はヨーロッパの王権と結びついて、世界各地を植民地にするための方策を練っていましたから。当時のイエズス会士と法王庁の間での書簡、あるいはイエズス会士とフランス・イエズス会の間に交わされた書簡を読んでみると、面白おかしく中国における見聞が書いてあります。そればかりでなく、政争の状態、政治の形態、軍事の状況までこと細かく書かれていました。おそらく宣教師たちはスパイとしての役割も担っていたのでしょう。
しかし、なかにはカスチリョーネのように、スパイとして中国に送りこまれながらも中国の美しさに触れて「中国人になろう」と三代の皇帝に忠義をつくして、中国で生きて中国で死んだ人物もいたわけです。これこそ、西洋の良心ではないでしょうか。しかも、カスチリョーネは乾隆帝の教育係にあたっていたわけです。おそらく、カスチリョーネは清王朝の支配階級における思想の中心部分をつくった人物の一人ではないかと思うのです。
芸術とは誰のものか
浅田氏はカスチリョーネの生きかたを通して、小説のなかに自分自身の芸術論を投影させた。浅田氏は、芸術は常に大衆と共にあるべきもので、閉じられたサロンのものであるべきではないと確信している。
芸術をあまりにアカデミックなものにしたのは近代の犯した過ちでしょう。歴史を遡れば、純粋な芸術作品は庶民の手の届く場所にあって、人間が病気や飢餓に苦しんでいたときの「なぐさめ」になっていたのではないでしょうか。私はそんな想像をしているのです。古今東西、権力者のほうを向いている芸術家というのはロクなものではありませんから。
西洋の芸術家としての教養と技術を持ちあわせながら中国に生き、作品のみを残して死んだカスチリョーネの魂は、私の理想の芸術家像に近い。はじめは命じられて中国に赴任したのでしょう。しかし、中国で生きるうちに少しでも自分の手で、美しいものをこの中国に生きる人たちに見せてやりたいと思ったのではないでしょうか。彼こそ、真の芸術家です。私も、そういう気持ちで小説を書いていきたいと思っています。
『蒼穹の昴』の続編である『珍妃の井戸』の舞台は、列強諸国に蹂躙され荒廃した清朝最末期の北京だ。その混乱のさなか、紫禁城の奥深くで一人の妃が無残に命を奪われた。皇帝の寵愛を一身に受けた美しい妃は、なぜ、そして誰に殺されたのか。犯人探しに乗り出した日英独露の高官が知った真相は―。芥川龍之介の『藪の中』のようなスタイルで幾つもの角度から語られる珍妃殺害の事実は、列強諸国自身が中国に対しておこなった現実をあらためて知らしめることになった……。
本来は『蒼穹の昴』の大団円に義和団事件を書こうと思っていました。しかし、書き進むうちに義和団事件そのものは別のテーマで書いたほうがいいと思うようになったのです。つまり、義和団事件はひとつの物語の最後につけ加えてそれで済むほど、簡単な話ではなかったのです。だから『珍妃の井戸』というもうひとつの作品にして書いてみました。この小説では、義和団事件と、そのあとの軍閥の台頭に焦点を当てました。
少し気になるのは、『蒼穹の昴』や『中原の虹』の販売部数に比べて『珍妃の井戸』の読者が少ないことです。これは怖い。つまり、『蒼穹の昴』を読んでそのまま『珍妃の井戸』の存在に気づかずに『中原の虹』を読んでいる人がたくさんいるのではないか。ところが『珍妃の井戸』を読んでいないとその後の展開がわからない部分が相当ある。たとえば『中原の虹』で袁世凱殺害にかかわる重要な人物も『珍妃の井戸』に出てくるから、是非読んでおいていただきたいのですけど。
「未知の大地」の風を感じて
『蒼穹の昴』『珍妃の井戸』を書きあげた浅田氏は、続編である『中原の虹』を中国東北部での綿密な取材を重ねて執筆していった。『蒼穹の昴』執筆当時、まだ一度も中国に行ったことがなかった浅田氏にとって、かつて満洲と呼ばれた中国東北部への旅は積年の夢だった。
『蒼穹の昴』は文学書や歴史書や史料を中心に想像して描いた世界でした。はじめて中国に行ったのは一九九七年で、『蒼穹の昴』刊行の翌年。当時から『中原の虹』の構想はあったので、その取材のため万里の長城に出かけたわけです。万里の長城に立って「ここから向こうが満洲なのか」と思ったときの感動は、よく覚えています。『中原の虹』の主人公である張作霖が馬賊たちと共に万里の長城を越えてきた、その大地のイメージがまざまざと頭のなかに浮かびました。理屈抜きで、これが満洲なんだと体験できたのです。
現在の瀋陽(旧奉天)は大都会だが、一九九七年に訪れた頃はまだ「田舎の風情」が感じられたという。浅田氏の中国東北部に対する第一印象は「気候のいいところだなぁ」ということ。夏に出かけたので、空気がサラッとしていて非常に過ごしやすく、夏の北海道のようだったという。
中国東北部がどんなに寒くても、氷に閉ざされているのはせいぜい数ヵ月です。夏の気候は本当に素晴らしい。だから、直感で悪い土地ではないなと思いました。そして土の色を見てみたら、北京周辺の河北省に比べてずっと土地が肥えているとわかったのです。
満洲の森林と草原を前にして、「豊かな土地だ」と感じた浅田氏は、かつて日本がこの土地に固執した理由もわかるような気がしたそうだ。もっと冷たく荒れ果てたところかと想像していたが、とても魅力的な土地だったのだ。
『中原の虹』の取材では何度も北京や瀋陽に行ったので、とてもリアリズムのある小説になったと思います。満洲のさまざまな季節をこの目で見たからこそ、『中原の虹』で張作霖が「東三省をわがものとするつもりか」と問われたときに「打聴、満洲風(満洲の風に聴け)」と言うシーンを書けた。あれは満洲の風を知っていなければ書けない言葉ですから。
張作霖は満洲の風を愛しており、自分が生まれ育った土地を愛している。だから「自分の行く末のことなんて満洲の風に聴けばよかろう」と言うのだ。
中国の共産主義というのは、ソ連からの影響だけではなくて、中国内部のいろいろな個人の思想の影響を受けたものではないでしょうか。中国の共産主義には、たとえば清代末期に康有為が唱えた平等主義・大同思想の影響を明らかに受けているところがあります。同時に張作霖のものの考えかたも、中国共産主義に何かしら影響をおよぼしているのではないでしょうか。馬賊出身で、あれだけの貧乏人でありながら国土の四分の一を支配したというのは、中国の歴史のなかでは異例です。張作霖の貧乏人根性は、中国共産主義にどこかで影響を与えたのではないかと想像しています。
張作霖は五三歳で死ぬまで、けっして貧乏人根性を忘れませんでした。
満洲では張作霖にまつわる具体的なエピソードを耳にしました。たとえば、こんな話です。ふつう、リアカーというのは自転車の後ろにつけるものでしょう。ところが、瀋陽の街では、人々がリアカーを自転車の前につけて押している。不思議に思って私が地元の人に「なんでリアカーを押しているの?」と質問したら、「実はこれは張作霖が『こうしたほうがいい』と発案したんだ」と言う。「押していたら、自分の目で荷物が見えているから事故が少なくて、泥棒に盗られにくいぞ」と。そんな形で張作霖の政治は現在も生きている。そういう発想って貧乏人でなければ思いつかないでしょう? だから、張作霖の思想は、のちの体制にも影響を与えたのではないかと思っているのです。
近代的な軍事教育を受けていない張作霖が戦争を指揮することは、近代の軍事理論の常識を超えている。『中原の虹』のなかでは、日露戦争以降、つまり日本の軍事教育が完成されたあとの日本軍人は張作霖を見て「無教養な人物に一個師団を率いることは不可能」と侮る。しかし、張作霖は簡単に統率してしまった。なぜ張作霖はそんなことができたのか。
馬賊の場合、指揮する馬の数は数十頭までが普通でしょう。あとは子分がいても見えないのだから「戦争」の範疇に入らない。つまり「喧嘩」の範囲に留まっていた連中を率いて「戦争」を指揮してしまったのが張作霖なのです。なぜそんなことができたのだろうと不思議に思います。そもそも知識がないのだから、軍事的な才能があったとは思えません。やはり求心力や神がかり的なところがあったから実現できたのでしょう。
張作霖は、空に投げたコインを撃ちおとすほどの神業的なピストルの達人でした。若い時分から馬賊の頭目として数えきれないぐらいの人を殺してきた逸話も残されています。いくら人間の命の価値が安かったとはいえ、ここまで人殺しに精を出し続けてきた男が、なぜ国民に人気があったのか。その魅力を想像で探っていくプロセスは興味深かったです。小説のなかでは、私は張作霖にこんなセリフを語らせています。「百万も千万も殺してやるさ。百年ののちに十億の民が腹いっぱいに食って、天寿を全うできればそれでよかろう」。これは想像の言葉ですが、張作霖の思想ではないかと思っています。










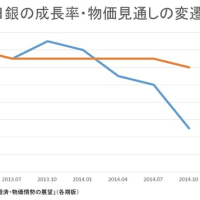
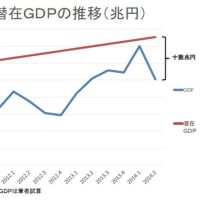


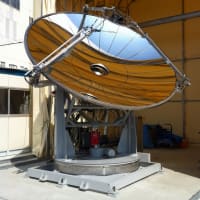
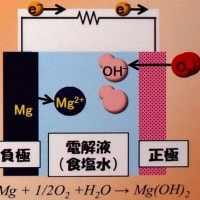

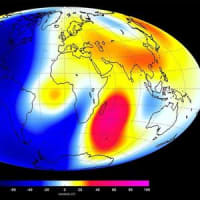


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます