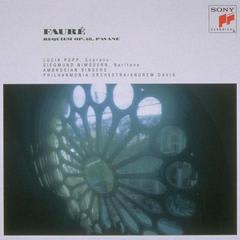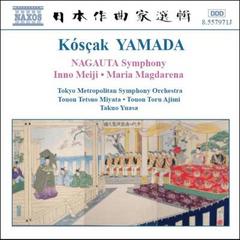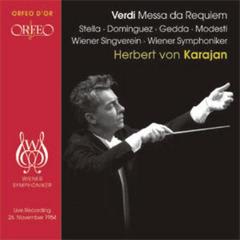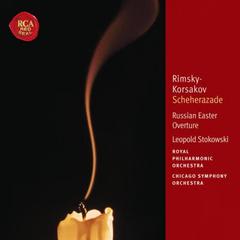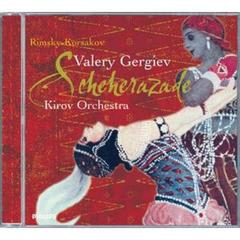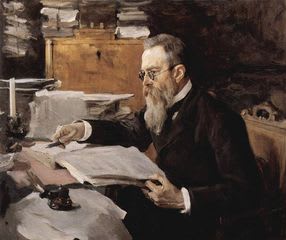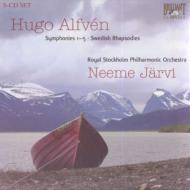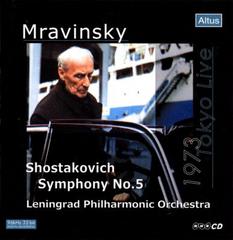DVD『カラヤン&ベルリン・フィル:ライヴ・イン・大阪 1984』
発売が長らく待たれていたライヴ映像で特にレスピーギ:交響詩『ローマの松』は伝説に
残る名演と言われています。
本拠地ベルリンでの映像は多数残されていますが、来日公演時の映像となると少ないので
これを映像で観られるのは大変うれしいです。
《プログラム》
モーツァルト:ディヴェルティメント第15番変ロ長調 K.287
R.シュトラウス:交響詩『ドン・ファン』 op.20
レスピーギ:交響詩『ローマの松』
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
1984年10月18日、ザ・シンフォニー・ホール、大阪
追伸:DVDから音声データだけを抜き出してiPodでも聴いていますが、この日のライヴで
演奏された”レスピーギ:交響詩『ローマの松~アッピア街道の松』”は物凄い迫力
です。特に金管とティンパニーが圧巻です~
発売が長らく待たれていたライヴ映像で特にレスピーギ:交響詩『ローマの松』は伝説に
残る名演と言われています。
本拠地ベルリンでの映像は多数残されていますが、来日公演時の映像となると少ないので
これを映像で観られるのは大変うれしいです。
《プログラム》
モーツァルト:ディヴェルティメント第15番変ロ長調 K.287
R.シュトラウス:交響詩『ドン・ファン』 op.20
レスピーギ:交響詩『ローマの松』
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
1984年10月18日、ザ・シンフォニー・ホール、大阪
追伸:DVDから音声データだけを抜き出してiPodでも聴いていますが、この日のライヴで
演奏された”レスピーギ:交響詩『ローマの松~アッピア街道の松』”は物凄い迫力
です。特に金管とティンパニーが圧巻です~