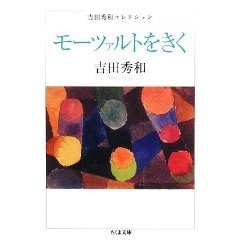今春から今いちど日本の歴史についての書籍を読んでいるのですが、その中でも文章と併せて写真と
図解でわかりやすく理解できる書籍と言えば「学習研究社」が出版している『歴史群像』シリーズがあります。
この書籍と初めて出会ったのは13年前で、きっかけは歴史に造詣の深い友人からでした。
それ以来、大の『歴史群像』シリーズ・ファンとなり、現在に至っています。
私は日本の歴史の中でも特に古代史が好きです。
理由は古代史には未だ解明されていない謎が数多く存在し、否応なく歴史ロマンに駆り立てられるからです。


古事記―記紀神話と日本の黎明 (歴史群像シリーズ (67)) 歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈 (歴史群像シリーズ (69))
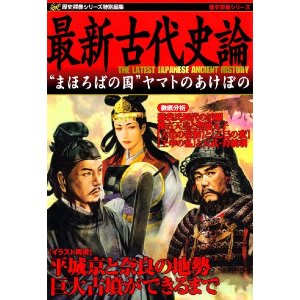

最新古代史論―”まほろばの国”ヤマトのあけぼの (歴史群像シリーズ) 飛鳥王朝史―聖徳太子と天智・天武の偉業 (歴史群像シリーズ)
「岩波書店」の新書「シリーズ 〈日本古代史〉」気になっています。


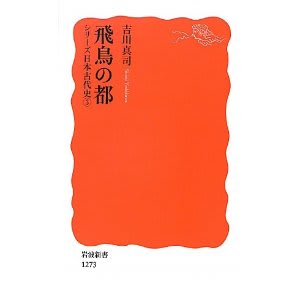
農耕社会の成立〈シリーズ 日本古代史 1〉 ヤマト王権〈シリーズ 日本古代史 2〉 飛鳥の都〈シリーズ 日本古代史 3〉


平城京の時代 〈シリーズ 日本古代史 4〉 平安京遷都 〈シリーズ 日本古代史 5〉
図解でわかりやすく理解できる書籍と言えば「学習研究社」が出版している『歴史群像』シリーズがあります。
この書籍と初めて出会ったのは13年前で、きっかけは歴史に造詣の深い友人からでした。
それ以来、大の『歴史群像』シリーズ・ファンとなり、現在に至っています。
私は日本の歴史の中でも特に古代史が好きです。
理由は古代史には未だ解明されていない謎が数多く存在し、否応なく歴史ロマンに駆り立てられるからです。


古事記―記紀神話と日本の黎明 (歴史群像シリーズ (67)) 歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈 (歴史群像シリーズ (69))
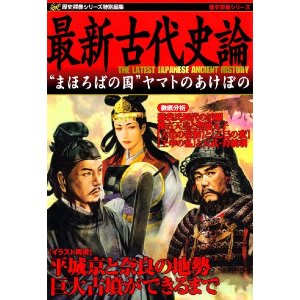

最新古代史論―”まほろばの国”ヤマトのあけぼの (歴史群像シリーズ) 飛鳥王朝史―聖徳太子と天智・天武の偉業 (歴史群像シリーズ)
「岩波書店」の新書「シリーズ 〈日本古代史〉」気になっています。


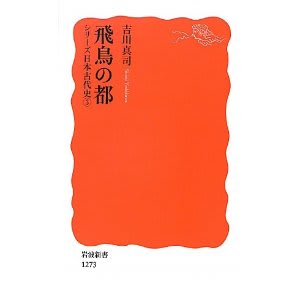
農耕社会の成立〈シリーズ 日本古代史 1〉 ヤマト王権〈シリーズ 日本古代史 2〉 飛鳥の都〈シリーズ 日本古代史 3〉


平城京の時代 〈シリーズ 日本古代史 4〉 平安京遷都 〈シリーズ 日本古代史 5〉