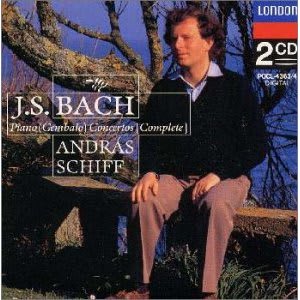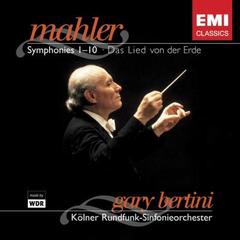芸術の秋が近づく中、素晴らしいクラシックCDが発売されます。
以前発売された時はその真価がまだわからず見過ごしてしまい気付いたら数タイトルが廃盤となっていて
その後、中古盤で入手したブルックナーの交響曲第5番と第8番...
最晩年のチェリビダッケは作品によっては解釈が大胆過ぎる場合があり、人によっては好き嫌いが分かれるところですが
私はその解釈に惹き付けられ他の演奏も聴きたいと思うようになりました。
その最晩年の演奏をプライスダウンのボックスセットで再発売されることは悦ばしいかぎりです。
来年2012年は指揮者セルジュ・チェリビダッケ生誕100周年のメモリアル・イヤーということもあり
このセットをじっくり聴きながらお祝いしたいと思います。
《EMI チェリビダッケ・エディション》 全4集 (2011/10/17発売予定)
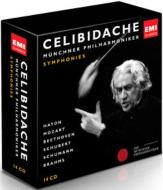
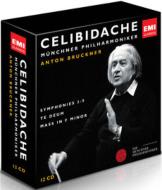


左から 第1集/ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームス:交響曲集(14CD)
第2集/ブルックナー:交響曲集(12CD)
第3集/フランス、ロシア音楽集(11CD)
第4集/宗教音楽、オペラ序曲集(11CD)
以前発売された時はその真価がまだわからず見過ごしてしまい気付いたら数タイトルが廃盤となっていて
その後、中古盤で入手したブルックナーの交響曲第5番と第8番...
最晩年のチェリビダッケは作品によっては解釈が大胆過ぎる場合があり、人によっては好き嫌いが分かれるところですが
私はその解釈に惹き付けられ他の演奏も聴きたいと思うようになりました。
その最晩年の演奏をプライスダウンのボックスセットで再発売されることは悦ばしいかぎりです。
来年2012年は指揮者セルジュ・チェリビダッケ生誕100周年のメモリアル・イヤーということもあり
このセットをじっくり聴きながらお祝いしたいと思います。
《EMI チェリビダッケ・エディション》 全4集 (2011/10/17発売予定)
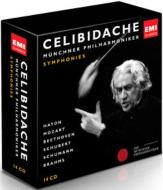
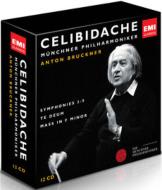


左から 第1集/ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームス:交響曲集(14CD)
第2集/ブルックナー:交響曲集(12CD)
第3集/フランス、ロシア音楽集(11CD)
第4集/宗教音楽、オペラ序曲集(11CD)