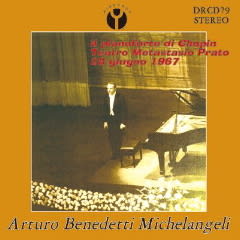クラシック音楽家シリーズの第9弾です。
《Richard Strauss=リヒャルト・シュトラウス》(ドイツ 1864-1949)作曲家・指揮者
〈交響詩〉=〈各楽章に標題を付けた描写音楽〉を確立した作曲家として最も有名です。
〈交響詩〉というジャンルが無かった時代にベートーヴェンが交響曲第6番〈田園〉の
各楽章に標題を付けたのが後の〈交響詩〉へ発展したとも言われています。
*ベートーヴェン:交響曲第6番〈田園〉(1807~1808年作曲)
第1楽章:田舎に到着したときの晴れやかな気分
第2楽章:小川のほとりの情景
第3楽章:農民達の楽しい集い
第4楽章:雷雨、嵐
第5楽章:牧人の歌-嵐の後の喜ばしく感謝に満ちた気分
リヒャルト・シュトラウスが確立した〈交響詩〉の特徴は各楽章の区切りがなく、続けて
演奏されるので、まるで〔一大絵巻〕を聴いて(観て)いるような印象を受けます。
リヒャルト・シュトラウス〈交響詩〉の代表作
『ドン・ファン』(1888年作曲)
『死と変容』(1889年作曲)
『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』(1895年作曲)
『ツァラトゥストラはこう語った』(1896年作曲)*映画「2001年宇宙の旅」で有名
『ドン・キホーテ』(1897年作曲)

自作自演盤
『英雄の生涯』(1898年作曲)

自作自演盤
それと〈交響詩〉ではありませんが、私が好きな『アルプス交響曲』も各楽章の区切りが
なく、続けて演奏されます。
目を閉じて聴くとあたかも自分自身が登山し、目の前にアルプス山脈が聳えるようです。
リヒャルト・シュトラウス:『アルプス交響曲』(1915年作曲)
「夜~日の出~登山~森への立ち入り~小川のほとりの旅~ 滝で~幻影~花盛りの風景~
アルプスの牧草地で~藪と繁みに迷って~氷河の上~危ない瞬間~頂上~光景~霧が
立つ~日は次第に翳る~悲歌~嵐の前の静けさ~ 雷雨と嵐、下山~日没~終結~夜」
全22章

自作自演盤

*推薦盤 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年録音)

*推薦盤 カラヤン&ベルリン・フィル(1983年ベルリンでのライヴ映像)
また指揮者としても有名だったリヒャルト・シュトラウスが振ったベートーヴェン:
交響曲第5&7番の録音も残されています。

リヒャルト・シュトラウス&ベルリン国立歌劇場管弦楽団(1926年,1928年録音)
栄光に満ちたリヒャルト・シュトラウスの生涯ではありますが、晩年には暗雲が立ちこめ
てきます。それはナチスが台頭した1930年代以降からで、ナチスが創設した第三帝国・
帝国音楽院総裁の任に就きます。リヒャルト・シュトラウス本人の真意がどのようなもの
であったかは後年様々な事が言われてきましたが、戦後この件によって非ナチ化裁判にか
けられることになります(結果は無罪)
政治的事実はその時代に生きた人々の価値観などによって大きく左右されるでしょうが、
こと芸術によって生み出された作品は時代には左右されない普遍性が備わっているのでは
ないでしょうか。
リヒャルト・シュトラウスが遺した音楽作品を聴くとそのように感じます。
《Richard Strauss=リヒャルト・シュトラウス》(ドイツ 1864-1949)作曲家・指揮者
〈交響詩〉=〈各楽章に標題を付けた描写音楽〉を確立した作曲家として最も有名です。
〈交響詩〉というジャンルが無かった時代にベートーヴェンが交響曲第6番〈田園〉の
各楽章に標題を付けたのが後の〈交響詩〉へ発展したとも言われています。
*ベートーヴェン:交響曲第6番〈田園〉(1807~1808年作曲)
第1楽章:田舎に到着したときの晴れやかな気分
第2楽章:小川のほとりの情景
第3楽章:農民達の楽しい集い
第4楽章:雷雨、嵐
第5楽章:牧人の歌-嵐の後の喜ばしく感謝に満ちた気分
リヒャルト・シュトラウスが確立した〈交響詩〉の特徴は各楽章の区切りがなく、続けて
演奏されるので、まるで〔一大絵巻〕を聴いて(観て)いるような印象を受けます。
リヒャルト・シュトラウス〈交響詩〉の代表作
『ドン・ファン』(1888年作曲)
『死と変容』(1889年作曲)
『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』(1895年作曲)
『ツァラトゥストラはこう語った』(1896年作曲)*映画「2001年宇宙の旅」で有名
『ドン・キホーテ』(1897年作曲)

自作自演盤
『英雄の生涯』(1898年作曲)

自作自演盤
それと〈交響詩〉ではありませんが、私が好きな『アルプス交響曲』も各楽章の区切りが
なく、続けて演奏されます。
目を閉じて聴くとあたかも自分自身が登山し、目の前にアルプス山脈が聳えるようです。
リヒャルト・シュトラウス:『アルプス交響曲』(1915年作曲)
「夜~日の出~登山~森への立ち入り~小川のほとりの旅~ 滝で~幻影~花盛りの風景~
アルプスの牧草地で~藪と繁みに迷って~氷河の上~危ない瞬間~頂上~光景~霧が
立つ~日は次第に翳る~悲歌~嵐の前の静けさ~ 雷雨と嵐、下山~日没~終結~夜」
全22章

自作自演盤

*推薦盤 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年録音)

*推薦盤 カラヤン&ベルリン・フィル(1983年ベルリンでのライヴ映像)
また指揮者としても有名だったリヒャルト・シュトラウスが振ったベートーヴェン:
交響曲第5&7番の録音も残されています。

リヒャルト・シュトラウス&ベルリン国立歌劇場管弦楽団(1926年,1928年録音)
栄光に満ちたリヒャルト・シュトラウスの生涯ではありますが、晩年には暗雲が立ちこめ
てきます。それはナチスが台頭した1930年代以降からで、ナチスが創設した第三帝国・
帝国音楽院総裁の任に就きます。リヒャルト・シュトラウス本人の真意がどのようなもの
であったかは後年様々な事が言われてきましたが、戦後この件によって非ナチ化裁判にか
けられることになります(結果は無罪)
政治的事実はその時代に生きた人々の価値観などによって大きく左右されるでしょうが、
こと芸術によって生み出された作品は時代には左右されない普遍性が備わっているのでは
ないでしょうか。
リヒャルト・シュトラウスが遺した音楽作品を聴くとそのように感じます。