東京のれきし(歴史)地区や
下町を おとずれるたび、
 いまだ、「江戸の粋
いまだ、「江戸の粋 」なるものを、かしこにかんじる・クリンたち。
」なるものを、かしこにかんじる・クリンたち。
さりとて、
それが、どのようなものか?
 言葉でせつめい(説明)するとなると、
言葉でせつめい(説明)するとなると、
なかなか・むずかしいものがあります。。
 (←千葉生まれ・埼玉育ち・多摩在住、というハンデ
(←千葉生まれ・埼玉育ち・多摩在住、というハンデ )
)
 その、言葉足らずをおぎなって、「粋って、こんなことだよ
その、言葉足らずをおぎなって、「粋って、こんなことだよ 」
」
と、示してくれるのが
学者のしごと(仕事)だと、
 うちのチット
うちのチット は、言っています。
は、言っています。
その学者の一人に、
くき・しゅうぞう(かんじ:九鬼周造)
という人が いるのですが、
 この人が、谷中にゆかりのある・人物なので、
この人が、谷中にゆかりのある・人物なので、
ちょっと
とりあげてみたい と思います
と思います
 <代表作は、「『いき』の構造」
<代表作は、「『いき』の構造」 >
>
くき・しゅうぞう は、
は、
明治時代、
文部省の役人だった
「九鬼隆一 」の 息子でした
」の 息子でした
 お父さんは、「日本美術を保護しよう
お父さんは、「日本美術を保護しよう 」と、がんばった人で、「東京美術学校」(今の芸大)の
」と、がんばった人で、「東京美術学校」(今の芸大)の
そうせつ(創設)にも
かかわりました
 「東京美術学校」の そうせつ(創設)者といえば、おかくら(岡倉)天心
「東京美術学校」の そうせつ(創設)者といえば、おかくら(岡倉)天心 が
が
いちばんの
功労者ですが、
おかくら天心は、
くき・りゅういち の
の
部下だったのです
 ゆうしゅう(優秀)で、ねつい(熱意)ある・天心
ゆうしゅう(優秀)で、ねつい(熱意)ある・天心 を 部下にもち、
を 部下にもち、
アメリカ人・フェノロサと
関係をもったことで、
「九鬼隆一」は 出世し
文部省のトップに立つまでに
なりました
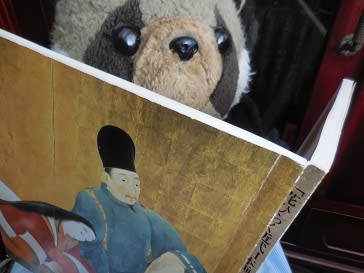 くき(九鬼)と天心のチームは、まことに良いしごと(仕事)をし、
くき(九鬼)と天心のチームは、まことに良いしごと(仕事)をし、
「西洋化一辺倒」に
なりかかっていた・日本から、
価値ある作品が
流出しないよう、
でんとう・びじゅつ(伝統美術)の後押しに、
全力を 注ぎました
そう・・・、
 2人が、ある事件をきっかけに、決定的にけつれつ(決裂)するまでは
2人が、ある事件をきっかけに、決定的にけつれつ(決裂)するまでは


 その事件とは、天心と、「九鬼夫人
その事件とは、天心と、「九鬼夫人 」が、男女の仲になってしまうという、
」が、男女の仲になってしまうという、
フリンでした
 くき(九鬼)
くき(九鬼) と、夫人との間には、4人の子がいましたが、
と、夫人との間には、4人の子がいましたが、
くき(九鬼)はとかく・女好きで、
年中
よそで、
うわき(浮気)をしていました
 さらに、ていしゅ(亭主)関白で いばってるので、
さらに、ていしゅ(亭主)関白で いばってるので、
そんな夫に
イヤ気がさしてたところに、
 天心が、何かと 世話してくれたものだから、夫人は、天心のことが
天心が、何かと 世話してくれたものだから、夫人は、天心のことが
好きになっちゃったのです
 二人の接近をしった・くき(九鬼)は、
二人の接近をしった・くき(九鬼)は、
ことが明るみに出る前に
二人を引きはなそうと しました
しかし!
 夫人は、天心にベタボレで
夫人は、天心にベタボレで 、
、
かんし(監視)の目をくぐりぬけて
天心に会ったり、
京都にかくり(隔離)されても、
すぐに
天心のいる東京にもどるなど、
おぼれていました
 天心は天心で、さいし(妻子)がいるのに、夫人にはまり込み
天心は天心で、さいし(妻子)がいるのに、夫人にはまり込み 、
、
自分の立場も考えず、
上司(九鬼)の立場も考えず、
つま(妻)の逆上も
なんのその
 はめつ(破滅)的な恋に もえました
はめつ(破滅)的な恋に もえました
この事件は
まもなく スキャンダルとして
おおやけになり、
それがもとで
天心は
せっかく・なった、「東京美術学校校長」を
やめさせられたそうです
 それが、たまたま・学校うんえい(運営)でもめてる
それが、たまたま・学校うんえい(運営)でもめてる 時だったので、
時だったので、
天心派の「日本画科・教授」たちも
いっせいに
学校をやめる、
美校事件に
はってん(発展)してしまいます
 「男爵家の対面
「男爵家の対面 」を 保つため、なかなか・りこん(離婚)して
」を 保つため、なかなか・りこん(離婚)して
もらえなかった
くき(九鬼)夫人は、
数年かかって
りこん(離婚)を かちとります
が、
けっきょく
天心とは 引きさかれ、
ニ度と 会えませんでした
 さらに!この時のぜつぼう(絶望)から 気がおかしくなり
さらに!この時のぜつぼう(絶望)から 気がおかしくなり
せいしん・びょういん(精神病院)に
入院させられて、
71さいで死ぬまで
そこで
さびしく くらしたそうです。。
 「お母さんは死んだ。」ときかされて育った・息子(九鬼周造)
「お母さんは死んだ。」ときかされて育った・息子(九鬼周造) は、
は、
「魅力的だった」とされる母を
したいつづけ、
「美術界のドン」とされた
父の家で、
 おかくら(岡倉)天心のえいきょう(影響)をも、
おかくら(岡倉)天心のえいきょう(影響)をも、
つよくうけながら、
美的なものを
追い求める、
てつがく(哲学)的な大人に
なったそうです
(つづく)
 木場のアート・ギャラリー
木場のアート・ギャラリー の ショップで、
の ショップで、 クリンは、見たこともきいたこともない・しょくぶつ(植物)に、
クリンは、見たこともきいたこともない・しょくぶつ(植物)に、
 「リトープス」っていう名前
「リトープス」っていう名前 (※まんなかの、パカッてわれてるやつです
(※まんなかの、パカッてわれてるやつです )
) 「石に擬態し、動物や昆虫などに食べられないよう、
「石に擬態し、動物や昆虫などに食べられないよう、
 「生ける宝石
「生ける宝石 」と、だい(題)された、その小さな・しょくぶつ(植物)
」と、だい(題)された、その小さな・しょくぶつ(植物) は、
は、
 「
「 多肉植物の珍種、今、流行っているんだってね~。
多肉植物の珍種、今、流行っているんだってね~。
 )
) 












 東京都現代びじゅつかん(美術館)が、すぐ・近くにあるだけあって、
東京都現代びじゅつかん(美術館)が、すぐ・近くにあるだけあって、 木場は、現代アートを 羽ばたかせる、自由な気風が
木場は、現代アートを 羽ばたかせる、自由な気風が

 今回の作品てん(展)も、
今回の作品てん(展)も、

 さて、ここ、「アース・プラス・ギャラリー」は、
さて、ここ、「アース・プラス・ギャラリー」は、 、
、 これが、ただごとでない・おしゃれ空間です
これが、ただごとでない・おしゃれ空間です
 おそらく、今まで作品てん(展)をやった、プロの作家さんの
おそらく、今まで作品てん(展)をやった、プロの作家さんの 一つ一つに、きせい(既成)品とはちがう・おもみがあり、
一つ一つに、きせい(既成)品とはちがう・おもみがあり、
 「美術手帖」とかも おいてあって、よめます
「美術手帖」とかも おいてあって、よめます
 「
「
 あの、どでかい焼き物ロック(岩)も、ここから見ると、
あの、どでかい焼き物ロック(岩)も、ここから見ると、
 こった・お料理も あるらしいので
こった・お料理も あるらしいので 、
、
 (つづく)
(つづく) すさき(洲崎)神社の入り口で、とつぜん・チット
すさき(洲崎)神社の入り口で、とつぜん・チット の本を
の本を 「
「

 荷風が『深川の唄』で、こう書いてるの。・・・」
荷風が『深川の唄』で、こう書いてるの。・・・」 倉庫の屋根のかげになって、
倉庫の屋根のかげになって、 「
「 「ダメ
「ダメ 今日はこれから、こてん(個展)に行くんだよ!」
今日はこれから、こてん(個展)に行くんだよ!」 を
を )
) 
 しき地も、はいでん(拝殿)も、小さくて、
しき地も、はいでん(拝殿)も、小さくて、
 (・・・ん?)
(・・・ん?) 」
」
 (こんなところに、なぜ・・?)
(こんなところに、なぜ・・?) <寛政三年(1791)、深川洲崎一帯に襲来した
<寛政三年(1791)、深川洲崎一帯に襲来した (このへん、海だったんだっけ・・
(このへん、海だったんだっけ・・ )
) もと・海があった、すみだ(隅田)川・左岸が、
もと・海があった、すみだ(隅田)川・左岸が、 当時の海岸せん(線)がわかる。。
当時の海岸せん(線)がわかる。。 、
、
 住民は、たびたび・海あらし(嵐)
住民は、たびたび・海あらし(嵐) この近くだけでも、「越中島」「大島」「永代島」・・・
この近くだけでも、「越中島」「大島」「永代島」・・・


 (れきし(歴史)の きょうくん(教訓)は
(れきし(歴史)の きょうくん(教訓)は

 ちょっとだけ、なつかしの下町ふぜい(風情)が ただよいます
ちょっとだけ、なつかしの下町ふぜい(風情)が ただよいます 「物流の動脈」として、江戸の各地につくられたという、うんが(運河)
「物流の動脈」として、江戸の各地につくられたという、うんが(運河) このあたりの水は、淡水と海水が入りまじり、
このあたりの水は、淡水と海水が入りまじり、
 その・丸太をはこぶのは、「川並さん」とよばれる
その・丸太をはこぶのは、「川並さん」とよばれる

 木場の川並さんたちが、「労働歌」として うたっていたという
木場の川並さんたちが、「労働歌」として うたっていたという

 今、このあたりで、耳をすましても、きやりうたは、
今、このあたりで、耳をすましても、きやりうたは、
 材木おき場や、材木ぎょう(業)者を、ほとんど
材木おき場や、材木ぎょう(業)者を、ほとんど  材木問屋のならびに、たくさん・うえられていたという、
材木問屋のならびに、たくさん・うえられていたという、 木場・いったい(一帯)に ただよっていたという、
木場・いったい(一帯)に ただよっていたという、
 げんざい・のこっているのは、ゆたかな水
げんざい・のこっているのは、ゆたかな水 (つり好きのおにいちゃんは、このまち、気に入るかも・・
(つり好きのおにいちゃんは、このまち、気に入るかも・・ クリンは、江東区・木場に 出かけました
クリンは、江東区・木場に 出かけました
 ここに、材木おき場があったのに、由来しています
ここに、材木おき場があったのに、由来しています

 しょっちゅう・まち(街)が もえていたので
しょっちゅう・まち(街)が もえていたので 、
、 「建築資材」である木を、たくさん・ひつよう(必要)とした
「建築資材」である木を、たくさん・ひつよう(必要)とした
 材木商たちも、たくさん・あつまってきました
材木商たちも、たくさん・あつまってきました 天下にその名をとどろかせた
天下にその名をとどろかせた

 またたく間に、有名花まち(街)になりました
またたく間に、有名花まち(街)になりました しかし、今、都立公えん(園)となった・木場には、
しかし、今、都立公えん(園)となった・木場には、 「貯め木」がおかれていた・
「貯め木」がおかれていた・ ふだんは、江東区民のいこい(憩い)のスペース以外の
ふだんは、江東区民のいこい(憩い)のスペース以外の

 江戸時代のおもかげが かいま見える気がするのは、
江戸時代のおもかげが かいま見える気がするのは、 馬車道で、牛なべ
馬車道で、牛なべ も 食べちゃいます
も 食べちゃいます

 「ねえ、チット~。きばってどこよ?」
「ねえ、チット~。きばってどこよ?」
 (江戸さんぽに つづいちゃう
(江戸さんぽに つづいちゃう
 ここには 「富貴楼」という、ちょう(超)・有名な りょうてい(料亭)が
ここには 「富貴楼」という、ちょう(超)・有名な りょうてい(料亭)が 大久保利通
大久保利通  伊藤博文
伊藤博文 井上かおる(馨)
井上かおる(馨)  むつ・むねみつ(陸奥宗光)
むつ・むねみつ(陸奥宗光) 明治初期、日本一・もりあがってた
明治初期、日本一・もりあがってた
 おくら(倉)は、江戸下町の とび(鳶)の娘でしたが、
おくら(倉)は、江戸下町の とび(鳶)の娘でしたが、 大官たちを 手玉にとりました
大官たちを 手玉にとりました
 開港地となった・ヨコハマに いち早く目をつけ、
開港地となった・ヨコハマに いち早く目をつけ、 ここ・おのえちょう(尾上町)の女王
ここ・おのえちょう(尾上町)の女王 政財界のサロンと化し、
政財界のサロンと化し、 その 名物おかみ(女将)となった・
その 名物おかみ(女将)となった・ 弟子たちに
弟子たちに 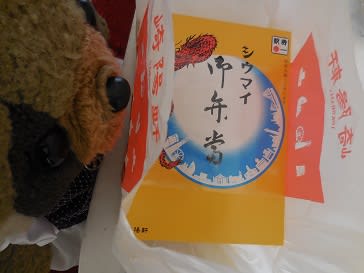 そんな、世わたり・上手な おかみ(女将)の
そんな、世わたり・上手な おかみ(女将)の
 てってい的に 入れあげて
てってい的に 入れあげて

 まわりに、金も力も、みりょく(魅力)もある男たちが
まわりに、金も力も、みりょく(魅力)もある男たちが 


 と きようけん(崎陽軒)の シウマイ弁当を食べながら
と きようけん(崎陽軒)の シウマイ弁当を食べながら シュウマイよりも、付け合せのタケノコが好きだね
シュウマイよりも、付け合せのタケノコが好きだね ぶろぐ、さいかい(再開)しますので
ぶろぐ、さいかい(再開)しますので
 」
」 ふたたび、にっぽり(日暮里)駅へ
ふたたび、にっぽり(日暮里)駅へ


 「今度また、ここら辺来ようね
「今度また、ここら辺来ようね
 「おにいちゃあん~。アンヨ・つかれた~。。」
「おにいちゃあん~。アンヨ・つかれた~。。」 「あ~、キモチいい・・
「あ~、キモチいい・・







 ゆうやけだんだん
ゆうやけだんだん 昭和30~40年代?を かんじさせる、商店がい(街)
昭和30~40年代?を かんじさせる、商店がい(街) せまい通りに、ちっちゃい・個人けいえい(経営)の店が、
せまい通りに、ちっちゃい・個人けいえい(経営)の店が、 酒屋さん
酒屋さん


 青果店・せい(精)肉店
青果店・せい(精)肉店




 おそうざい(惣菜)屋さんなど・・
おそうざい(惣菜)屋さんなど・・ かん(観)光客向けのお店もあるけど・・
かん(観)光客向けのお店もあるけど・・
 「おにいちゃん、このメンチカツ、A5ランクのお肉つかってるんだよ!」
「おにいちゃん、このメンチカツ、A5ランクのお肉つかってるんだよ!」 いまだ、「江戸の粋
いまだ、「江戸の粋 言葉でせつめい(説明)するとなると、
言葉でせつめい(説明)するとなると、
 (←千葉生まれ・埼玉育ち・多摩在住、というハンデ
(←千葉生まれ・埼玉育ち・多摩在住、というハンデ )
) その、言葉足らずをおぎなって、「粋って、こんなことだよ
その、言葉足らずをおぎなって、「粋って、こんなことだよ 」
」 うちのチット
うちのチット この人が、谷中にゆかりのある・人物なので、
この人が、谷中にゆかりのある・人物なので、 <代表作は、「『いき』の構造」
<代表作は、「『いき』の構造」

 「東京美術学校」の そうせつ(創設)者といえば、おかくら(岡倉)天心
「東京美術学校」の そうせつ(創設)者といえば、おかくら(岡倉)天心 ゆうしゅう(優秀)で、ねつい(熱意)ある・天心
ゆうしゅう(優秀)で、ねつい(熱意)ある・天心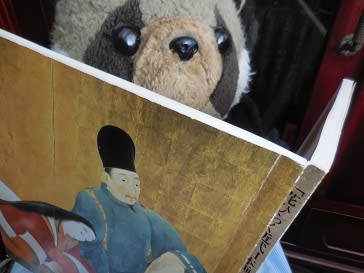 くき(九鬼)と天心のチームは、まことに良いしごと(仕事)をし、
くき(九鬼)と天心のチームは、まことに良いしごと(仕事)をし、
 2人が、ある事件をきっかけに、決定的にけつれつ(決裂)するまでは
2人が、ある事件をきっかけに、決定的にけつれつ(決裂)するまでは

 その事件とは、天心と、「九鬼夫人
その事件とは、天心と、「九鬼夫人
 くき(九鬼)
くき(九鬼) さらに、ていしゅ(亭主)関白で いばってるので、
さらに、ていしゅ(亭主)関白で いばってるので、 天心が、何かと 世話してくれたものだから、夫人は、天心のことが
天心が、何かと 世話してくれたものだから、夫人は、天心のことが
 二人の接近をしった・くき(九鬼)は、
二人の接近をしった・くき(九鬼)は、 夫人は、天心にベタボレで
夫人は、天心にベタボレで 天心は天心で、さいし(妻子)がいるのに、夫人にはまり込み
天心は天心で、さいし(妻子)がいるのに、夫人にはまり込み はめつ(破滅)的な恋に もえました
はめつ(破滅)的な恋に もえました それが、たまたま・学校うんえい(運営)でもめてる
それが、たまたま・学校うんえい(運営)でもめてる 時だったので、
時だったので、 「男爵家の対面
「男爵家の対面 さらに!この時のぜつぼう(絶望)から 気がおかしくなり
さらに!この時のぜつぼう(絶望)から 気がおかしくなり 「お母さんは死んだ。」ときかされて育った・
「お母さんは死んだ。」ときかされて育った・ おかくら(岡倉)天心の
おかくら(岡倉)天心の
 上野せんそう(戦争)
上野せんそう(戦争) で 官軍とたたかった、「彰義隊」の
で 官軍とたたかった、「彰義隊」の しょうぎたい(彰義隊)をかくまった、きょうおうじ(経王寺)の山門には、
しょうぎたい(彰義隊)をかくまった、きょうおうじ(経王寺)の山門には、 官軍がうった、てっぽう玉のあとがのこっています
官軍がうった、てっぽう玉のあとがのこっています
 さらに、おはか(墓)まで・たててあげるのは、
さらに、おはか(墓)まで・たててあげるのは、 ばくふ(幕府)のためにたたかった、
ばくふ(幕府)のためにたたかった、
 (←羽二重団子の店にも、彰義隊士の遺物が大切に保管されてました)
(←羽二重団子の店にも、彰義隊士の遺物が大切に保管されてました) かながき・ろぶん(仮名垣魯文)
かながき・ろぶん(仮名垣魯文) かれらが、この辺りの住人だったからなのかな・・
かれらが、この辺りの住人だったからなのかな・・


 ちょうど、クリンたちが おとずれた時、はぎ(萩)の花が咲いていました
ちょうど、クリンたちが おとずれた時、はぎ(萩)の花が咲いていました
 秋のこうらく(行楽)といえば、「紅葉狩り
秋のこうらく(行楽)といえば、「紅葉狩り 」ですが、
」ですが、 そのかわり、庶民には、月見
そのかわり、庶民には、月見 と、菊見
と、菊見 うちのチット
うちのチット 経王寺、と道をはさんで 向かいにある、シニセ(老舗)の
経王寺、と道をはさんで 向かいにある、シニセ(老舗)の 人気店、「谷中せんべい」の ぼう(棒)おかきは、
人気店、「谷中せんべい」の ぼう(棒)おかきは、 おもちの風味と、しょうゆの香りがただよう、かるい・しょっかん(食感)
おもちの風味と、しょうゆの香りがただよう、かるい・しょっかん(食感) (つづく)
(つづく) せんろ(線路)の向こうの ガケの上に、
せんろ(線路)の向こうの ガケの上に、 かわった形の まっ赤な・たてものが見えました。
かわった形の まっ赤な・たてものが見えました。 でんしゃ(電車)の中から、このぜっぺき(絶壁)にたつ、
でんしゃ(電車)の中から、このぜっぺき(絶壁)にたつ、 前から気になっていたそうです。
前から気になっていたそうです。
 「この際、何の建物か、確かめる
「この際、何の建物か、確かめる
 すると、そこは「本行寺」という お寺の けい(境)内で・・・
すると、そこは「本行寺」という お寺の けい(境)内で・・・
 たねだ・さんとうか(種田山頭火)
たねだ・さんとうか(種田山頭火) (赤い・・)
(赤い・・) 本堂のうらが、ぼち(墓地)になっており、
本堂のうらが、ぼち(墓地)になっており、 ぼち(墓地)のすぐ下は、せんろ(線路)です。
ぼち(墓地)のすぐ下は、せんろ(線路)です。 赤いたてものが、チラッと見えました
赤いたてものが、チラッと見えました
 反対がわ(側)からは、ちょっと・見えました
反対がわ(側)からは、ちょっと・見えました にしては、なんなんだろう?
にしては、なんなんだろう?

 (つづく)
(つづく)

