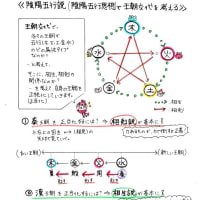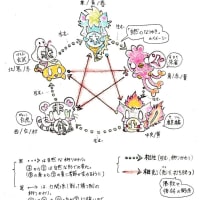歴史模擬授業第二十回 江戸時代文化・諸産業です。詳しくは、前の記事をご覧ください。
-------------------------------------------
 「さて、今日はいったん政治から離れて、江戸時代の産業と文化をやっていきましょう。」
「さて、今日はいったん政治から離れて、江戸時代の産業と文化をやっていきましょう。」
 「はーい。」
「はーい。」
 「まずは産業。産業には、農業・漁業・工業などがありますね。」
「まずは産業。産業には、農業・漁業・工業などがありますね。」
 「はい。」
「はい。」
 「これらの産業は、江戸時代にとってもさかんになるの。
「これらの産業は、江戸時代にとってもさかんになるの。
まずは農業をみていこう。
幕府や藩は年貢を税としてとっていたからちゃんと米が安定してとれるように
、かんがい用水の整備や新田開発が行ったの。
それで豊臣秀吉の時代に比べて耕地面積が約2倍に増えたの。」
 「そうなんだ!すごい!」
「そうなんだ!すごい!」
 「農具も発達してね。
「農具も発達してね。
深くまで掘れるようになった備中ぐわ、脱穀(だっこく)ができる千歯こき、
穀粒を選別するための千石どおし、穀物からもみ殻などを風力でえりわける装置の唐み、などの
新しい農具が次々に誕生して、生産効率があがったの。」

 「平和な時代だからこそ、材料を武器でなく農具に使用できたのかな(予想)」
「平和な時代だからこそ、材料を武器でなく農具に使用できたのかな(予想)」
 「あと、漁業も発達してね。有名なのは、九十九里浜のいわし漁とか、土佐のかつお漁など。」
「あと、漁業も発達してね。有名なのは、九十九里浜のいわし漁とか、土佐のかつお漁など。」
 「へー。」
「へー。」
 「幕府は鉱山の開発も努めた。佐渡の金山(新潟)や、生野の銀山(兵庫)など。」
「幕府は鉱山の開発も努めた。佐渡の金山(新潟)や、生野の銀山(兵庫)など。」
 「へー。」
「へー。」
 「工業の形態も変わったの。
「工業の形態も変わったの。
それまでは、1人1人が最初から最後までつくったりしていたり、
個人で原料を買ってつくったりしてたんだけど、
問屋(とんや)という仲介業者が、農民に原料や道具を貸して品物を作らせて、
それをひきとって、お店に売って、お店でお客が買う、という形にね。」
 「今の内職を頼む会社みたいなものね。」
「今の内職を頼む会社みたいなものね。」
 「このように、問屋が農民に材料を貸して、農民がつくったものを引き取る、という工業のことを、
「このように、問屋が農民に材料を貸して、農民がつくったものを引き取る、という工業のことを、
問屋制家内工業(とんやせいかないこうぎょう)と言います。」
 「ほんとにいろいろなものが発達したんだね。平和っていいね。」
「ほんとにいろいろなものが発達したんだね。平和っていいね。」
 「品物ができれば、それを売るために、遠くまで行く必要もあるよね。
「品物ができれば、それを売るために、遠くまで行く必要もあるよね。
それで水上交通も発達する。
 「へー。」
「へー。」
 「また、幕府は、五街道という道も定めたの。
「また、幕府は、五街道という道も定めたの。
五街道はすべて江戸の日本橋を起点にしてね。
どこに行こうとも、ぜったいに江戸は通らなければいけない、という意図で。
そしたら見はりやすいでしょ。
たとえば幕府を倒そうとする東北地方の人が幕府から隠れて、味方のいる京都に行けないように、とか。」
 「あいかわらず、江戸幕府は徹底しているね。」
「あいかわらず、江戸幕府は徹底しているね。」
 「この五街道はすべておおまかなルートと街道名を覚えてね。
「この五街道はすべておおまかなルートと街道名を覚えてね。
江戸~東北地方ルート:奥州街道、
江戸~日光(栃木にある徳川家康が神として祀られる場所があるところ)ルート:日光街道
江戸~甲府~下諏訪(長野):甲州街道
江戸~静岡・愛知~京都ルート:東海道
江戸~長野~京都ルート:中山道(中仙道)」
 「東北地方には奥羽山脈があるから、奥州とおぼえるとわすれなさそう。」
「東北地方には奥羽山脈があるから、奥州とおぼえるとわすれなさそう。」
 「甲州街道も甲府を通るから、と覚えればいいね。」
「甲州街道も甲府を通るから、と覚えればいいね。」
 「ちなみに、東海道と中山道は、スタートとゴール地点は一緒。江戸⇔京都。
「ちなみに、東海道と中山道は、スタートとゴール地点は一緒。江戸⇔京都。
ルートが海側なのが東海道、
山側なのが、中山道ね。」
 「東海道新幹線の通るルートと、ほとんど東海道は一致するね♪」
「東海道新幹線の通るルートと、ほとんど東海道は一致するね♪」
 「そうね、電車が好きだと、よりわかりやすいよね。」
「そうね、電車が好きだと、よりわかりやすいよね。」
 「あと、当時は、歩いて(もしくは馬)で移動するから、1日で行ける距離が限られてくる、
「あと、当時は、歩いて(もしくは馬)で移動するから、1日で行ける距離が限られてくる、
そこで、街道の途中で、宿場町がたくさん出来てくるの。
宿場町っていうのは宿を中心とした町。
愛知県では鳴海が有名。東海道の宿場町ね。」
 「だから、鳴海は昔ながらの風景が残っているんだ!」
「だから、鳴海は昔ながらの風景が残っているんだ!」
 「あと、愛知県から行きやすい宿場町の面影を残しているのが、
「あと、愛知県から行きやすい宿場町の面影を残しているのが、
岐阜の馬籠宿(まごめじゅく)、長野の妻籠宿(つまごじゅく)・奈良井宿(ならいじゅく)。
こちらは中仙道の宿場町ね。
馬籠宿は、食べるお店などもたくさん立ち並んでいて遊べるし(島崎藤村の「夜明け前」の舞台でもある)、
妻籠はほんとに昔の面影が残っているよ。
奈良井宿は伝統工芸品のお店が多く、また中央線路沿いにあるから、電車でも行きやすいわ。」
「へー。今度行ってみようかな!」
「どれも江戸時代にタイムスリップしたみたいで良いわよ!」
「楽しそう!」
「あと、宿場町以外でも、江戸時代には様々な都市が発達するの。
城のまわりで発達したのが城下町。江戸や松本、名古屋などがそうね。
港を中心として発達したのが、港町。長崎、博多などが。
神社や寺のまわりで発達したのが、門前町。神社・寺には必ず門があるから、
その門の手前で発達したから門前町。奈良や
、宇治山田(伊勢神宮のある三重)、長野(善光寺のある長野市)など。
あと、宿場町で有名なのが、品川や小田原や草津。」
 「小田原って箱根温泉が近いし、草津温泉など温泉街は宿場町が発達したのかな?」
「小田原って箱根温泉が近いし、草津温泉など温泉街は宿場町が発達したのかな?」
 「全部がそうとはいえないけど、多くはそうかもね。」
「全部がそうとはいえないけど、多くはそうかもね。」
 「名古屋は城下町なんだね。確かに、名古屋城のまわりにある場所が一番発達してるもんね。
「名古屋は城下町なんだね。確かに、名古屋城のまわりにある場所が一番発達してるもんね。
古い街並みも残っているし。」
 「あと、発達した都市の中でとくに、政治・経済・文化の中心地だったところを三都と呼ぶの。
「あと、発達した都市の中でとくに、政治・経済・文化の中心地だったところを三都と呼ぶの。
政治の中心はもちろん、将軍のいる江戸。別名、「将軍さまのおひざものと」と呼ばれるわ。
経済の中心は大阪。別名、「天下の台所」。たくさんの作物が大阪に来る。
年貢米を貯蔵する蔵屋敷がずらっと立ち並んでいたそうよ。
あとは、文化の中心は、伝統のある京都。織物・美術・工芸品などが発達したの。」
 「へー。」
「へー。」
「では、次は文化をみていきましょう。」
ーーーーーーーー
続く。文字数の関係で記事を新たにつくります。
ーーーー
わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。