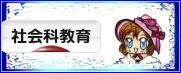歴史模擬授業(旧) 第27回 第二次世界大戦前 2-1 世界恐慌です。
詳細はこちらの前の記事(ご注意)をご覧ください。
※わかりやすく解説したいので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「さて、今日は昭和時代を行いましょう。」
「さて、今日は昭和時代を行いましょう。」
 「ついに、昭和時代!」
「ついに、昭和時代!」
 「平成も一部は行うけど、昭和でほとんど習う歴史は終わるので、あと一息、がんばりましょう!」
「平成も一部は行うけど、昭和でほとんど習う歴史は終わるので、あと一息、がんばりましょう!」
 「はい!」
「はい!」
 「昭和時代は、長いうえに、ある時を境にして180度社会状況がかわっていくので、
「昭和時代は、長いうえに、ある時を境にして180度社会状況がかわっていくので、
大きく3つに分けます。
第二次世界大戦前(戦前)
第二次世界大戦中
第二次世界大戦後(戦後)
の3つ。
よく戦後、という言葉はこれから使うけど、それは、第二次世界大戦後のことを指すので、
覚えておきましょう。」
 「はい。」
「はい。」
 「では、今日は、第二次世界大戦前の、戦争がおこる原因・きっかけを見ていきましょう。」
「では、今日は、第二次世界大戦前の、戦争がおこる原因・きっかけを見ていきましょう。」
 「第一次世界大戦は、植民地の取り合いだったのが戦争がおこる背景にあったけど、
「第一次世界大戦は、植民地の取り合いだったのが戦争がおこる背景にあったけど、
第二次世界大戦はどうだったんだろう?」
 「ではでは、始めます。
「ではでは、始めます。
第二次世界大戦が、はじまるきっかけとなった1つには、
世界規模の大不況(大不景気)がおこったからと
言われています。
多くの国が、景気対策をしていくんですが、だんだんといきづまっていき、
それが限界に達したと時に戦争がおこってしまいます。
第一次世界大戦同様、その背景には、
植民地の取り合い、世界の覇権争い(はけんあらそい:誰が一番になって、世界をまとめるか、という争い)がありますが・・・。」
 「世界規模の大不況がおこったんだ・・。」
「世界規模の大不況がおこったんだ・・。」
 「1929年にアメリカのニューヨークで、数年間上昇していた株価が突然、大暴落してしまいます。
「1929年にアメリカのニューヨークで、数年間上昇していた株価が突然、大暴落してしまいます。
それがきっかけに、アメリカは大不景気になってしまいました。」
 「なんか・・・、何年か前のアメリカから始まった不景気と似ている・・。(独り言)」
「なんか・・・、何年か前のアメリカから始まった不景気と似ている・・。(独り言)」
 「で、この不景気はアメリカだけの問題だけではなかった。
「で、この不景気はアメリカだけの問題だけではなかった。
実は、第一次世界大戦でヨーロッパの国々はお金をたくさん使ってしまった。
イギリスやフランスは、アメリカの資金援助や、
ベルサイユ条約で決められたドイツからの賠償金を頼りに、戦後の復興をしていた。
ドイツは賠償金を出すお金がなかったから、お金をアメリカに借りて、
それでイギリスやフランスに賠償金を払っていた。
また、アメリカは世界各国と貿易をして、日本もアメリカと貿易をしていました。」
 「つまり、この当時はアメリカに、世界のほとんどの国がおんぶにだっこだったのね・・。」
「つまり、この当時はアメリカに、世界のほとんどの国がおんぶにだっこだったのね・・。」
 「そうなると、ほとんどの国を支えていたアメリカが倒れたら、共倒れになっちゃうよね。」
「そうなると、ほとんどの国を支えていたアメリカが倒れたら、共倒れになっちゃうよね。」
 「あ、つまり、アメリカが不況になれば、アメリカと関係のあった国も不況になってしまう?!」
「あ、つまり、アメリカが不況になれば、アメリカと関係のあった国も不況になってしまう?!」
 「そういうことなの。
「そういうことなの。
アメリカのこの株価大暴落をきっかけに、世界中に広がった大不況を
世界恐慌と言います。」
 「日本も不景気になったの?」
「日本も不景気になったの?」
 「うん、なった。しかも、6年まえに関東大震災がおこっていたから、日本は不景気の状態だった。
「うん、なった。しかも、6年まえに関東大震災がおこっていたから、日本は不景気の状態だった。
それに世界恐慌は日本の不景気に追い打ちをかけた。アメリカへの輸出が衰えてしまってね・・。
都市での失業者が増え、農作物の値段が下がり(不景気の場合は値段が下がる傾向にあります)農民たちも
生活が苦しくなる。」
 「生きるか死ぬか、の厳しい状態になったってことだね・・。」
「生きるか死ぬか、の厳しい状態になったってことだね・・。」
 「会社や銀行などもつぶれていく。
「会社や銀行などもつぶれていく。
そんな中、三井・三菱・住友・安田などの財閥は、(つぶれそうな)会社や銀行を吸収していくの。」
 「不景気のときって、生き残りをかけて会社・銀行の吸収合併もするもんね・・。」
「不景気のときって、生き残りをかけて会社・銀行の吸収合併もするもんね・・。」
 「財閥はどんどん大きくなる。
「財閥はどんどん大きくなる。
そうすると、経済の分野だけの支配だけでなく、政治分野まで
影響力を強めていく。」
 「そうだったんだ・・。」
「そうだったんだ・・。」
 「それが、のちの戦争がおこる一因とも言われています。」
「それが、のちの戦争がおこる一因とも言われています。」
 「そうだったのか・・。」
「そうだったのか・・。」
 「悪い言い方をすれば、
「悪い言い方をすれば、
戦争がおこるとお金は動く。
どうしても武器などは売れるから、売れるものを確実に
つくって売ればもうかるでしょ。また、植民地を持てば、そこに輸出してそれでもうけることだってできる。
(良いことではありません。絶対にしてはいけないことです。
また、現在の企業を批判しているわけではありませんので、これはあくまで過去のものとして考えてください。)
 「そんな・・・。」
「そんな・・・。」
 「では、この世界恐慌による景気対策を列強諸国はどうしていったか?
「では、この世界恐慌による景気対策を列強諸国はどうしていったか?
やり方は大きく分けて3つあります。
1つは、貿易の関税率を操作して、自分の国だけで不景気から抜け出す、というやり方です。」
 「?」
「?」
 「これは、経済観念の問題なので、ちょっとむずかしいと思います。
「これは、経済観念の問題なので、ちょっとむずかしいと思います。
なので、簡単に説明するね。
外国からの輸入品は高い関税をかける。
そうすると、自分の国(本国)や自国(本国)の植民地は、外国からの輸入品を買うのを控えるでしょ。
自国(本校)の植民地は自国(本国)の輸入品を買うようになるから、自国(本国)だけでも利益は出たりね・・。
そして、自国と植民地だけで自給自足をして、自分たちだけでも経済を立て直そうとしたの。
このように、植民地と本国(自国)の経済的結束を固めたような景気対策をブロック経済政策と言います。
(もし、この説明で意味がわからなければ、とにかく関税を利用して植民地と本国で結束を強くして
景気回復をしようとしたのがブロック経済政策なんだ、と思ってもかまいません。)」
 「えー、なんか国際的にみんなで不景気から回復しようと、するのでなく、自分たちだけでも!という形なんだ。」
「えー、なんか国際的にみんなで不景気から回復しようと、するのでなく、自分たちだけでも!という形なんだ。」
 「うん、悪い言い方をするとそうだよね。このブロック経済政策って、植民地を多く持ってないとできない政策だよね。」
「うん、悪い言い方をするとそうだよね。このブロック経済政策って、植民地を多く持ってないとできない政策だよね。」
 「うん。そうだよね・・・。」
「うん。そうだよね・・・。」
 「だから、ブロック経済をすることができた国って、たとえば・・。」
「だから、ブロック経済をすることができた国って、たとえば・・。」
 「えーと、第一次世界大戦で勝ってないと、植民地は失うから、勝った国で・・もともと植民地が
「えーと、第一次世界大戦で勝ってないと、植民地は失うから、勝った国で・・もともと植民地が
多かった国というと・・・イギリスやフランス?」
 「そういうことね。景気回復対策において,イギリスやフランスがブロック経済政策を行います。」
「そういうことね。景気回復対策において,イギリスやフランスがブロック経済政策を行います。」
 「そのように、関連付けて覚えるといいのね。」
「そのように、関連付けて覚えるといいのね。」
 「あと、アメリカも植民地は持っていたんだけど、イギリスやフランスよりは多くない。
「あと、アメリカも植民地は持っていたんだけど、イギリスやフランスよりは多くない。
しかし、アメリカというのは、他の国とは違う状況を持っていた。
それは(近代史としての)歴史がまだ浅く、近代化(工業化)が住んでいない場所が多かった。
それを利用して、景気対策を行おうとした。それが、2つ目。」
 「ほえー。」
「ほえー。」
 「アメリカの景気対策というのはどういうものなのかと言うと、
「アメリカの景気対策というのはどういうものなのかと言うと、
政府が公共事業を行い、その労働者を雇うことで、失業者を少なくし、
さらに、その公共事業で国全体がさらに
発展させる、というしたもの。
公共事業とは、たとえば、ダムの建設などね。
ダムを作るから,その建設のお仕事をしたい人集まってね~!
そしてそのお仕事をした人にはお給料を払うよ,というもの。
世界恐慌でお仕事を無くした人が多いから,その人たちが
そのダム建設という一時的なお仕事だとしても,その仕事の間は
給料をもらえるから生活できるってこと。
このように、積極的に政府が公共事業などを行い、資金援助をして景気を回復させようとした政策を
ニューディール政策と言います。このニューディール政策を行ったのはアメリカで
当時のアメリカ大統領は、フランクリン=ルーズベルト。」
 「ほえー。現代でも、不景気のときに公共事業をするのは、ここからきているのかな?(予想)」
「ほえー。現代でも、不景気のときに公共事業をするのは、ここからきているのかな?(予想)」
 「しかし、このようなやり方は、まだ工業化などの開発途中の段階にあったアメリカだからできたことです。
「しかし、このようなやり方は、まだ工業化などの開発途中の段階にあったアメリカだからできたことです。
もう、工業化しつくしてしまった国や、政府そのものもお金がないところは、このようなことをすることは
できない。」
 「たしかに・・・。」
「たしかに・・・。」
 「だから、イギリス・フランスのようにブロック経済政策ができるほど植民地を持っていない国、
「だから、イギリス・フランスのようにブロック経済政策ができるほど植民地を持っていない国、
アメリカよりもすでに工業化などが住んでしまっている国(もしくは政府内にお金があまりない)国は
どうすれば、経済の立て直しができるか?という問題がでてくる。」
 「そうだよね。しかもブロック経済政策が行われているため、
「そうだよね。しかもブロック経済政策が行われているため、
自分の国の商品は高い関税がかけられているため外国で売れなかったりするだろうし。」
 「・・で、このように追いつめられると、過激な行動に出てしまう、というおそろしいことがおこる。」
「・・で、このように追いつめられると、過激な行動に出てしまう、というおそろしいことがおこる。」
 「え・・。」
「え・・。」
 「植民地がなければ、戦争をして奪ってでも手に入れて、少しでも自分たちの国の景気を良くしていこうと、
「植民地がなければ、戦争をして奪ってでも手に入れて、少しでも自分たちの国の景気を良くしていこうと、
という考え方が出てきた。」
 「う・・・。」
「う・・・。」
 「軍事力で政治を動かすようになる。その際に、独裁者が出てくる。
「軍事力で政治を動かすようになる。その際に、独裁者が出てくる。
1人の人(独裁者)にすべてを任せて、国が一丸となって苦しみから逃れようとね・・・。
しばしば、追いつめられると独裁者を生む傾向があります。(独裁者を良し、とした意見ではありません)」
 「そうなんだ・・・。」
「そうなんだ・・・。」
 「このように、権力で支配する独裁政治をファシズムと言います。
「このように、権力で支配する独裁政治をファシズムと言います。
そして、このファシズムは、軍事色をどんどんと強めていきます。」
 「こわいな・・・。」
「こわいな・・・。」
 「ファシズムを行うようになった、国って今までの流れから予想できないかな?
「ファシズムを行うようになった、国って今までの流れから予想できないかな?
植民地をほとんど奪われ、お金にも困り、追いつめられた国・・・。」
 「それって、つまり第一次世界大戦で負けた国だよね・・、そして賠償金も払わなくてはならないから、お金に
「それって、つまり第一次世界大戦で負けた国だよね・・、そして賠償金も払わなくてはならないから、お金に
困って・・・、あ、もしかしてドイツ?」
 「そう、ドイツ。
「そう、ドイツ。
ベルサイユ条約で多額の賠償金を払うことになり、世界恐慌が追い打ちをかけ、
自分たちの日々の生活さえ苦しいのに、なぜ、外国にまでお金を・・・という気持ちでいっぱいいっぱいのとき
に、
ある人が「ベルサイユ条約の言うことを聞かないで良い!賠償金なんて払う必要がない!」という
言いだした。
そのときに、精神的にいっぱいいっぱいだった人々には、それが救いになったの。
(その言葉や内容が良い、と言っているわけではありません。)」
 「うーん、たしかに、それは当時の人々から救いの言葉になったのかもしれないね・・。(その言葉が良い,と言っているわけではありません。)」
「うーん、たしかに、それは当時の人々から救いの言葉になったのかもしれないね・・。(その言葉が良い,と言っているわけではありません。)」
 「で、その言葉を言った人を人々は支持し、しだいに、その人の独裁政治になっていった。
「で、その言葉を言った人を人々は支持し、しだいに、その人の独裁政治になっていった。
ドイツのその独裁者をヒトラー(ヒットラー)と言います。
そのヒトラーが属していた政党をナチス党(ナチ党)と言います。」
 「そうだったんだ・・。」
「そうだったんだ・・。」
 「あと、ドイツよりも先にファシズムを行ったのは、イタリアです。
「あと、ドイツよりも先にファシズムを行ったのは、イタリアです。
イタリアは第一次世界大戦では途中で同盟国を裏切り、連合国側についたとは前に話したよね。
しかし、戦争がおわってからの連合国の対応は、冷たいものだった。
だから、次第にイタリアも窮地(きゅうち:苦しいところ)においつめられていた。
それで、ファシスト党のムッソリーニが軍事力を強めて、独裁政治をし始めたのです。」
 「ドイツとイタリアの2つがファシズムか・・。」
「ドイツとイタリアの2つがファシズムか・・。」
 「いえ、もう一国、われわれにとって最も身近な国がファシズムになりました。」
「いえ、もう一国、われわれにとって最も身近な国がファシズムになりました。」
 「え?」
「え?」
 「植民地もイギリスみたいに多くない、第一次世界大戦後にイギリスからの同盟も破棄され、
「植民地もイギリスみたいに多くない、第一次世界大戦後にイギリスからの同盟も破棄され、
経済・政治の中心部に大地震がおこり、不景気がさらに苦しくなり、それにさらに世界恐慌に
追い打ちをかけられた国がある・・・。」
 「え・・・それって・・・。」
「え・・・それって・・・。」
 「うん、そう。」
「うん、そう。」
 「に・・・日本・・?」
「に・・・日本・・?」
 「そう、日本。」
「そう、日本。」
 「ええええええ?!」
「ええええええ?!」
 「今まで、あなたたちはもしかして、ドイツやイタリアは大変だな~と上から目線で見ていなかった?」
「今まで、あなたたちはもしかして、ドイツやイタリアは大変だな~と上から目線で見ていなかった?」
 「う・・・たしかに・・。」
「う・・・たしかに・・。」
 「細かいところはそれぞれの国では違うけど、日本もほぼ,ドイツやイタリアと同じ状況だったのよ!」
「細かいところはそれぞれの国では違うけど、日本もほぼ,ドイツやイタリアと同じ状況だったのよ!」
 「う・・自分たちのおごり高ぶりがはずかしい・・。」
「う・・自分たちのおごり高ぶりがはずかしい・・。」
 「歴史を学ぶときは、馬鹿にしたり同情したりする目でみてはならない。
「歴史を学ぶときは、馬鹿にしたり同情したりする目でみてはならない。
常に同じ状況下に置かれたときには、自分たちだって、同じ行動をとる可能性があるかもしれない、という
恐れを常に抱き、そのような同じ悲劇を繰り返さないように、理性で抑えるようにするのよ。」
 「はい!歴史の失敗を学んで、明るい未来をつくるのが、歴史の意義の1つだったよね。つい忘れてた・・。」
「はい!歴史の失敗を学んで、明るい未来をつくるのが、歴史の意義の1つだったよね。つい忘れてた・・。」
 「まあ、私もつい、そういう状況におちいることがあるから大きなことがいえないけど、
「まあ、私もつい、そういう状況におちいることがあるから大きなことがいえないけど、
途中で気がついて、最悪な状況までに陥らなければいいよ。」
 「はい!」
「はい!」
 「では、ファシズムを行った主な国はドイツ・イタリア・日本。
「では、ファシズムを行った主な国はドイツ・イタリア・日本。
ドイツの独裁者はナチス(ナチ党)のヒトラー。
イタリアの独裁者はファシスト党のムッソリーニ。
そして、日本は・・、ですが、ドイツ・イタリアとはすこし異なります。
ヒトラーやムッソリーニのように、民間人の独裁者というのが存在しなく、
軍部という集まりによる独裁になります。
ただし、その軍部が奉ったのが(上にかかげた)のは天皇になります。
軍部は、最終的には「天皇のために」という呪文のような言葉で、国民を動かしていったのです。
(こちらは天皇を批判した意見ではありません。)」
 「そうだったんだ・・。」
「そうだったんだ・・。」
 「では、次回は、日本がどのようにファシズムの道を歩み、戦争に突入していったのかをみましょう。
「では、次回は、日本がどのようにファシズムの道を歩み、戦争に突入していったのかをみましょう。
では終わります!起立,礼!」


 「ありがとうございました。」
「ありがとうございました。」
ーーーーーーーーーーーーー
わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。
ーーーーーーーーー
ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けるとうれしいです。