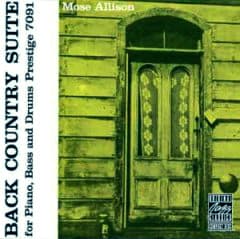このCDの帯には「和みのヴォーカル」とキャッチフレーズが振ってある。言い得て妙だ。
ヴォーカリストで成功するには、歌がうまいだけではダメで、相当個性的な表現力を持ち合わせていなければいけない。
そういう意味においてこのステーシー・ケントは完璧だ。彼女の歌声を聴いて和めない人はいないのではないかと思う。
もちろん人によっては好き嫌いがあるだろう。でも彼女の囁くような声は天性のもので、決して他人が真似できるものではない。どことなく子どもっぽく、適度に甘く、ほんのりとした色気が漂う。色に例えるとパステルカラーの雰囲気を持った人だ。
さて以前にもお話ししたが、個人的にリチャード・ロジャースのつくった「Bewitched...」が大好きだ。
数ある彼女のアルバムでどれを推薦しようかと思ったが、やはりこの曲が入っている「IN LOVE AGAIN」に決めた。そう、このアルバムもリチャード・ロジャースの歌曲集なのだ。
但し彼女のアルバムには駄作がなく、どれもこれも安心して推薦できるので、どのアルバムでも結構、ぜひ一度聴いていただきたい。
春のほんわかした日差しの中で、まどろみながら聴くのが正解だ。