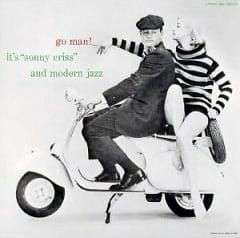これはお茶の水にあるディスクユニオンで見つけた。
ちょっと薄暗い急な階段を上がると2階と3階がジャズ館になっている。ここは中古のCDとLPが独立したフロアにあるので、掘り出し物を探すときには重宝する店だ。
ディスクユニオンは渋谷にも新宿にもあるが、なぜかこのお茶の水店に愛着があって上京した折には時々覗いている。
私がこういった中古のアルバムを探すときは、ある程度狙いをつけていることが多い。例えば今日は中間派の掘り出し物がないかどうかを最初に探そう、といった具合だ。
もちろん気に入ったものがあるとは限らない。今日は来てよかった、と思えるのはせいぜい3回に1回あればいい方である。
第一のお目当てがなかった場合は、第二希望の商品を探す。私の基準はこうした中古ショップでしかなかなか出会えないアルバムを探すことである。内容の好き嫌いはともかく、それは店内のあちこちにある。それを一つ一つ見ていって購入するかどうかを決めるのだ。決め手は価格も大きな要因ではあるが、私の場合それ以上にジャケットの雰囲気で判断する。
ここでご紹介するハーブ・ゲラーの「THE GELLERS」もそんな一枚だった。
ジャケットの裏面に写っているロレイン・ゲラーの表情に惹かれた。
彼女の録音は少ない。このアルバムが録音された5年後の1960年、30才でその短い生涯を終えた人だから当然だ。こうしたことも購入動機の一つになった。
家に帰ってきてすぐにターンテーブルに乗せる。フレッシュで勢いのあるハーブ・ゲラーのアルトが響き渡るが、それに負けないくらいロレイン・ゲラーのピアノが力強く感じられる。この音だけを聴いていれば彼女のような白人女性がそのピアノを弾いているとは思えないくらいの迫力だ。しかしこれはこれで夫婦の息がぴったり合った演奏であることには違いない。全体に何となくアットホームな雰囲気が漂うのもそのせいだろう。
それにしても美人薄命とはよく言ったものだ。
残されたハーブは彼女の後を埋めることができず相当なスランプが続いたと聞く。
この演奏を聴けばそれも納得できる。色々な意味で感慨深い一枚である。